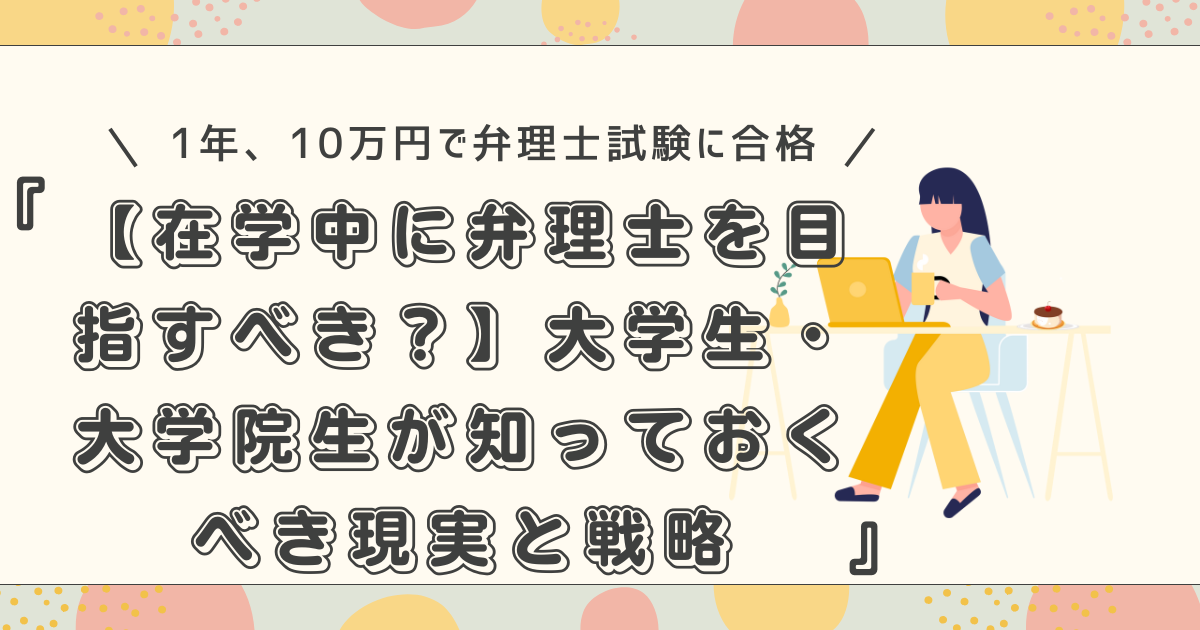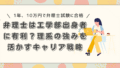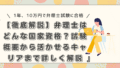はじめに:在学中に弁理士を目指すという選択肢
「在学中に弁理士を目指すのって、アリなのだろうか?」
そんな疑問を抱える理系大学生・大学院生は、近年少しずつ増えています。知財業界では、若手の人材不足が続いており、法律系資格の中でも弁理士は理系出身者との親和性が高い国家資格です。将来的なキャリアの幅を広げるためにも、「在学中のチャレンジ」は、非常に意義深いものになりえます。
私自身、理系大学院を卒業後にメーカーで開発職としてキャリアをスタートさせました。しかし、ある特許研修で出会った知財部の弁理士の方の話をきっかけに、この資格に魅力を感じるようになり、在職中に勉強を開始。現在は知財部で働きながら、弁理士資格を活かしてキャリアを築いています。
そんな実体験をふまえながら、この記事では「在学中に弁理士を目指すことのメリット・デメリット」や「現実的なスケジュール」「勉強方法」「就職・転職との関連」などを総合的に解説していきます。単なる情報の羅列ではなく、「いま行動する価値があるのか」を一緒に深掘りしていきましょう。
第1章:なぜ今、在学中に弁理士を目指す学生が増えているのか?
ここ数年で、法学部だけでなく、理工系学部・大学院から弁理士試験を目指す学生が増加傾向にあります。その背景には、以下のような理由があります。
1. 知財・特許への社会的ニーズの高まり
IT、バイオ、AI、半導体など、先端分野における知財の重要性は年々増しています。企業は自社の技術を守るため、優秀な知財人材を求めており、専門性のある若手は貴重な戦力として注目されています。
2. 若手・未経験でもチャレンジできるキャリアパス
弁理士は実務経験がなくても、資格さえ取得すれば知財業界に飛び込める「入り口の広い専門職」です。在学中に合格しておけば、企業や特許事務所への就職時にも強力なアピール材料となります。
特に修士課程在学中に合格すれば、卒業後すぐに弁理士としてのキャリアをスタートできるのは大きなメリットです。
3. 法律知識ゼロでも、理系バックグラウンドが活かせる
弁理士試験は、法律科目に加えて理系的な素養が問われる「理系寄りの法律資格」です。民法や特許法を学ぶ必要はありますが、暗記だけでなく論理的な思考力が重視されるため、理系出身者にとって実は親和性の高い試験でもあります。
第2章:在学中に弁理士試験に合格するための現実的なスケジュールと戦略
弁理士試験は、決して簡単な国家試験ではありません。合格までに平均3〜4年かかるとも言われており、合格率も全体で約7〜8%と低めです。しかし、在学中という比較的時間の自由がきく期間をうまく活用すれば、十分に合格を目指せる資格でもあります。
ここでは、大学生・大学院生が弁理士試験合格を狙うために意識すべきポイントとスケジュールについて、実体験を交えて紹介していきます。
1. 試験制度の概要を正しく理解する
弁理士試験は大きく3段階に分かれています。
| 試験区分 | 試験内容 | 実施時期 | 合格率(目安) |
|---|---|---|---|
| 短答式試験 | 択一式(特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権・不正競争防止法など) | 5月 | 約15〜20% |
| 論文式試験 | 論述(特許・意匠・商標) | 7月 | 約10〜15% |
| 口述式試験 | 口頭試問(特許・意匠・商標) | 10月 | 約90%(ここで落ちる人は少数) |
特に短答・論文で多くの受験生がふるい落とされます。早い段階で全体像を理解し、長期的な学習計画を立てることが大切です。
2. 在学中に合格するための理想スケジュール
以下は、私が考える在学中合格を狙うための学習モデルです(修士1年〜2年を想定)。
| 時期 | 主な学習内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 修士1年4月〜10月 | 特許法・実用新案法のインプット中心 | 条文を読む癖をつける |
| 修士1年11月〜翌3月 | 意匠法・商標法・著作権などのインプット+短答演習開始 | 過去問に慣れる |
| 修士2年4月〜6月 | 短答試験対策に集中 | 5月が本番 |
| 修士2年6月〜7月 | 論文試験対策へ切り替え | 過去問中心に演習 |
| 修士2年8月〜10月 | 口述対策+論文再対策 | 集団練習が効果的 |
※学部生の場合はもう1年余裕を持たせて、3年計画を推奨。
3. 独学に限界を感じたら?通信講座の活用を検討すべき理由
私自身、最初は市販書籍での独学を考えていましたが、時間効率と情報の網羅性を重視して通信講座を導入しました。特に在学中のように試験に割ける時間に限りがある状況では、「何を・いつ・どこまで」を設計してくれる講座は非常に心強い存在になります。
なかでもスタディング弁理士講座は、スマホ一つで学習できるため通学の移動時間やスキマ時間を有効活用できます。動画解説が中心で、法律の初学者にもやさしく設計されているため、在学中に学習を始める方にも最適です。
▼私が実際に使って合格した講座はこちらの記事で詳しくレビューしています:
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)第3章:弁理士資格が在学中にあれば、就職・転職はどう変わる?
「弁理士に合格したはいいけれど、就職でどんなメリットがあるの?」
こういった疑問を抱える方も多いでしょう。実は、弁理士資格を在学中に取得することには、就職活動や転職活動において非常に大きなアドバンテージがあります。
この章では、特に理系の大学生・大学院生を想定し、資格取得がキャリアに与える影響について、具体的に説明します。
1. 弁理士資格は“実務経験なし”でも市場価値がある
弁理士試験は実務経験がなくても受験・合格が可能です。
さらに合格後の「未登録弁理士」の段階でも、就職においては非常に強力な資格となります。
- 特許事務所(特に中小・若手弁理士が経営する事務所)では「未経験OK・合格者歓迎」の求人も多く存在
- 企業の知財部でも、採用担当者が弁理士資格を強く評価するケースが多い(特に製造業、医薬、IT分野)
- 「知財実務未経験でも将来性あり」として内定を出す企業もある
これは他の法律系資格、たとえば司法試験や行政書士などと比較しても、極めて特徴的なポイントです。
2. 大学での研究テーマや専門分野も評価されやすい
理系バックグラウンドを持つ学生が弁理士資格を取得すると、「技術的な理解力+法律的素養」という2軸を評価されます。
とくに以下の分野では需要が強く、資格の相性も良好です。
| 技術分野 | 主な就職先例 |
|---|---|
| 機械、制御、材料系 | 製造業の知財部、機械系特許事務所 |
| 化学、薬学系 | 製薬会社の知財部、化学特許事務所 |
| 情報、通信、AI、ソフトウェア | IT企業の知財部、ソフトウェア特許事務所 |
これらの分野は今後の知財市場でも中核を担う領域であり、「若くて専門性の高い人材」は常に求められています。
3. 実際に求人を探す際に活用すべき転職支援サービス
在学中の就職活動や卒業後の転職活動で、知財業界に特化した求人を見つけるには、一般的な転職サイトでは不十分なこともあります。
その点でおすすめなのが、リーガルジョブボードです。
📝 リーガルジョブボードは、知財・法務・弁理士業界に特化した転職支援サイトで、未経験可の求人や若手歓迎の案件も多く掲載されています。
たとえば、
- 「弁理士試験合格者で実務未経験OK」
- 「理系出身歓迎」
- 「在学中からインターン可」
といった条件での求人を見つけることができ、在学中にキャリアを切り開くための強力な武器となります。
また、コンサルタントが弁理士業界に精通しているため、自分の強みや不安をしっかりヒアリングした上で、適した求人を紹介してもらえるのも魅力です。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
4. 就職後のキャリアパスにも好影響
在学中に弁理士試験に合格し、就職・転職活動で有利に進めると、その後のキャリアでも加速度的にチャンスが広がります。
- 20代前半で年収500万超スタートも現実的
- 特許事務所で実務経験を積んで独立を目指す道も
- 企業知財部でインハウスキャリアを築く道も
実際に弁理士資格を活かして年収を大幅にアップさせた体験談もまとめていますので、参考にしてみてください。
第4章:在学中の弁理士受験を成功させるために読むべき本・参考書
弁理士試験は、専門性が非常に高い国家資格であり、独学で挑むには「正しい教材選び」が成功の鍵を握ります。とくに在学中から学習を始める場合、いきなり条文や判例集に手を出してしまい、挫折する人も少なくありません。
そこでここでは、法律の予備知識がない理系学生にもわかりやすく、かつ合格に必要な基礎が身につく参考書・教材をご紹介します。
1. 弁理士試験の勉強は「導入書」でスタートすべき
多くの受験生が最初に失敗しがちなのが、分厚い過去問集や判例解説集など「中上級者向け」の教材から手を付けてしまうことです。
しかし、最初に必要なのは、法律の世界観・制度の仕組みをざっくり理解すること。
この段階では、細かい条文の暗記や判例の理解は後回しで問題ありません。まずは、「知的財産権って何?」「特許と商標の違いは?」といった、概念的な理解を確実に固めましょう。
2. 初学者におすすめの一冊:『弁理士スタートアップテキスト』
こうした初学者向けの導入書として評価が高いのが、
👉 『弁理士スタートアップテキスト』(技術評論社) です。
この本の特徴は、
- 法律に苦手意識のある人でもスッと読めるやさしい文章構成
- 実務経験者が執筆しており、試験の全体像だけでなく、弁理士のリアルな仕事像までカバーしている
- イラストや図解が豊富で、大学生にもとっつきやすい
「勉強を始める前にざっと読んでおくことで、今後の学習の効率がまったく違ってくる」
という声も多く、まさに在学中から弁理士試験を志す人にこそ読んでほしい一冊です。
3. その他に押さえておきたい教材
もちろん、導入書籍だけで試験に合格できるわけではありません。
ステップアップとして、以下の教材も併用していくことをおすすめします。
| カテゴリ | 教材例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 条文集 | 工業所有権法(産業財産権)逐条解説 | 制度の背景理解に有用 |
| 問題集 | 弁理士試験短答過去問題集(LECやTAC) | 短答式試験対策に必須 |
| 論文対策 | 論文マニュアル(法文集付き) | 文章構成や表現のクセを養う |
これらの教材は、必要なタイミングで段階的に取り入れることがポイントです。まずは「導入→基礎固め→演習」という3段階の流れを意識しましょう。
第5章:在学中に弁理士を目指すあなたへ——行動する勇気が未来を変える
ここまで、在学中に弁理士試験に挑戦するというテーマで、制度の概要から勉強法、就職・転職の展望まで解説してきました。
では、最後にもう一度問いかけます。
「なぜ、あなたは在学中に弁理士を目指そうとしているのですか?」
それは、単に資格があると“就職に有利”だからでしょうか?
それとも、“何かに挑戦してみたい”という内なる衝動があるからでしょうか?
理由は人それぞれかもしれませんが、在学中のあなたが今ここで「弁理士」という選択肢に興味を持っていること自体、すでに大きな第一歩です。
1. 若いうちに挑戦する価値は“時間”にある
社会に出てから弁理士試験を目指すと、多くの人が「時間の確保」に苦労します。フルタイムで働きながら、家庭と両立しながら、日々のプレッシャーを受けながら勉強するのは容易ではありません。
その点、在学中には“自分で使える時間”があります。
もちろん、研究やバイト、就活など忙しい時期ではあるでしょう。でも、「勉強に集中できる時間帯を自分で設計できる」というのは、社会人にはない大きな武器です。
たとえ合格できなかったとしても、学んだ知識や論理力、タイムマネジメント能力は将来のあらゆるキャリアに直結します。
2. 迷ったまま何もせず終えるのが一番もったいない
「今やるべきか迷う」
「法律なんて勉強したことない」
「本当に自分にできるのか?」
そうした不安は、挑戦の前に必ずやってきます。
でも、それは“向いていない”からではなく、“未知の世界”に飛び込む怖さです。
むしろ、その不安があるからこそ真剣に向き合える。
やってみてダメだったら、その時はその時です。でも、やらなかったことはいつまでも後悔として残り続けます。
3. 未来は“何を持っているか”ではなく、“何を選んだか”で決まる
弁理士資格を持っているだけで自動的に成功するわけではありません。
でも、「在学中にこの資格に挑戦した」という経験は、必ずあなたの人生の土台になります。
- 挫折したとしても、試験勉強で培った力は次の挑戦に活かせる
- 合格すれば、就職の選択肢が大きく広がる
- 知財の道に進まなくても、“学ぶ力”そのものは武器になる
つまり、持っている資格ではなく、自分で何を選び、どう行動したかが、将来を大きく左右するのです。