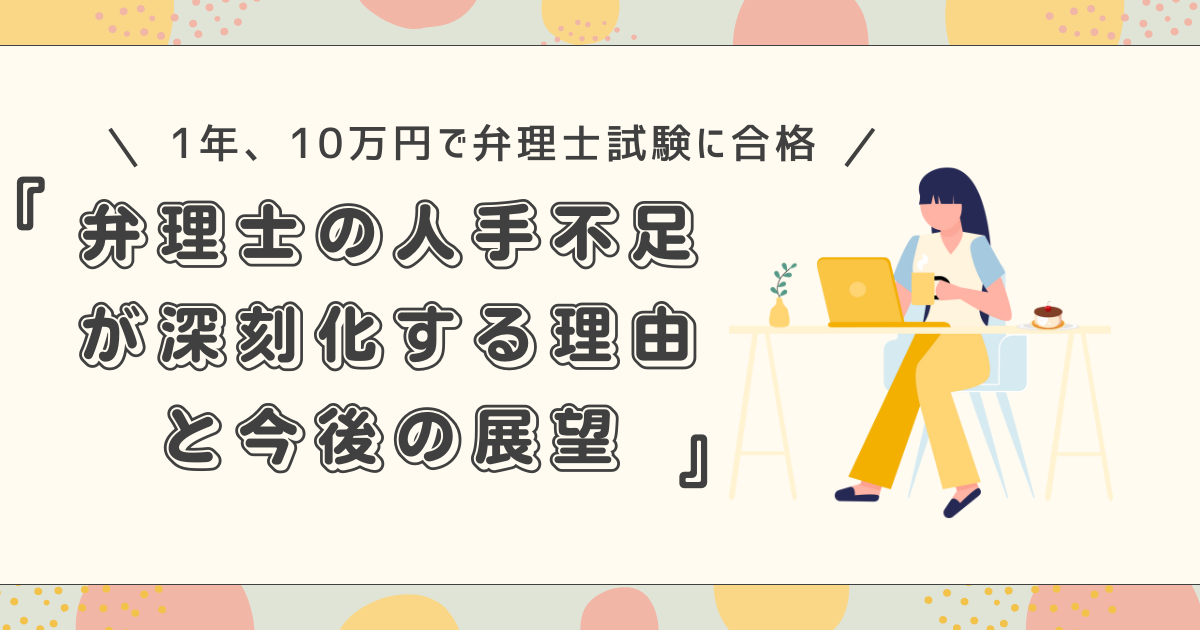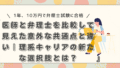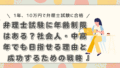はじめに:見過ごされがちな“弁理士の人手不足”
弁理士というと、「高年収」「専門職」「難関資格」といったポジティブなイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし近年、知的財産を扱う最前線では**「弁理士が足りない」という深刻な問題**が現場を悩ませています。
特に企業の知財部門や特許事務所では、採用に苦労しているという声が年々増加。AIの台頭やグローバル化など、知財の役割が大きく変わる中、なぜこのような“逆転現象”が起きているのでしょうか? 本記事では、
- 弁理士が人手不足になる本質的な理由
- 弁理士に今求められているスキルとは
- 今後の知財業界におけるキャリアの可能性
について、実体験をもとに深掘りしていきます。
弁理士の登録者数は「増えている」のに人手不足?
まず、表面的なデータから見ると、弁理士の登録者数は一定のペースで増加しています。2020年代初頭から弁理士試験の合格率は10%前後と、他の国家資格と比べて比較的安定しており、毎年新しい弁理士が誕生しています。
しかし、それにもかかわらず「人手が足りない」という声が現場から上がっている理由は、以下のように複雑です。
① 若手弁理士の確保が難しい
現場では、20〜30代の若手弁理士が非常に少ないという問題があります。弁理士試験の難易度、法律と理系知識のハイブリッドな学習負担、そして資格取得までの年数の長さ…。その結果、若手が敬遠しがちになっているのが実情です。
弁理士資格取得が難しい=人が集まらない
弁理士試験の難しさは業界でも有名です。理系知識(特許の技術的背景)と、民法・特許法などの法律知識をバランスよく習得しなければなりません。そのため、「理系で法律に苦手意識がある人」や「社会人で忙しい人」にとっては非常に高いハードルとなっています。
私自身も、理系大学院卒業後にメーカーで開発職として働きながら弁理士試験に挑戦しましたが、働きながら独学で突破するのはかなり厳しいと痛感しました。
そんな中、私が活用したのがオンラインで効率よく学べるスタディングの弁理士講座でした。
✅ 実体験で感じたスタディングのメリット
- スキマ時間を活かして、効率的に学習ができる
- 法律が初学者でも動画でかみ砕いて説明してくれる
- テキストだけではわからない“出題の傾向”も掴める
資格取得までのスピードを重視する方や、費用対効果の高い講座を探している方には非常におすすめです。
▼私が実際に使って合格した講座はこちらの記事で詳しくレビューしています:
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)📘 関連書籍紹介:
『弁理士スタートアップテキスト』
法律に苦手意識がある方でも理解しやすい構成で、弁理士試験の全体像を初歩からやさしく解説しています。受験前にまず読むべき一冊です。
企業の知財部でも弁理士人材が不足している理由
特許事務所だけでなく、メーカーやIT企業などの“企業内知財部”でも弁理士の人手不足は深刻です。これは単なる採用難だけではなく、知財業務の質と量の急激な変化によるものです。
① AI・IoT・DXの進展により知財の業務領域が拡大
かつて知財部の仕事といえば、発明届の取りまとめや出願手続き、拒絶理由への対応が中心でした。しかし近年では、以下のような業務にも関わる必要があります。
- AI・IoT関連の発明に対する知財戦略立案
- 海外への出願・権利化(PCT出願や米国・中国対応など)
- 自社・他社の知財ポートフォリオ分析
- DXによる社内情報の保護体制構築(データガバナンス)
つまり、弁理士として「単なる出願の代行者ではなく、経営戦略の一部としての知財人材」が求められるようになってきたのです。
② 知財部は“ジョブローテーション”で育成されづらい
一般的な大企業では、ジョブローテーション制度により人事・法務・経理・知財などを横断的に経験させて育成します。しかし、知財分野は専門性が高すぎてローテーションの対象になりにくいのが現実です。
その結果、以下のような課題が生じます:
- 知財の専門家としてキャリアを歩みたい人が少ない
- 配属されても数年で他部署へ異動してしまう
- 弁理士を採用しても社内で孤立しやすい
このような背景から、弁理士として知財部で腰を据えて働く人材が育ちにくいのです。
▼関連記事:
③ キャリアアップや転職の選択肢が豊富すぎる
弁理士は企業内に限らず、特許事務所、コンサル会社、スタートアップ、さらには独立開業までキャリアの幅が広い職業です。だからこそ、企業で育てた人材が他のフィールドへ流出しやすいという問題もあります。
とくに近年では、年収や裁量を求めて転職を選ぶ若手弁理士が増加中。その背景には、「年功序列でキャリアが進みにくい企業」よりも「実力で評価される事務所やスタートアップで働きたい」という意識の変化があります。
人手不足が続く一方で“知財部に入りたい人”も多い矛盾
ここまで読むと、「弁理士が不足しているなら知財部に入りやすいのでは?」と思われるかもしれません。実はその通りで、知財未経験でも意欲のある理系出身者ならポテンシャル採用される例は増えています。
しかし、問題はそこからです。
⚠ 入社後、専門知識のキャッチアップが必須
たとえ採用されたとしても、特許制度や出願実務、特許調査、契約業務などを一から学ぶには時間がかかります。とくに未経験者にとっては、技術と法律のダブルの知識習得が負担となります。
だからこそ、現場ではこうした声が上がっています:
「採用しても育成する余裕がない」
「法的な基礎を理解していないと戦力化が遅い」
「勉強してくれる人が少ない」
このような状況で活躍するには、やはり弁理士資格を取得し、専門性を持っておくことが強みになります。
弁理士の将来性:人手不足は「ピンチ」ではなく「チャンス」
ここまで弁理士の人手不足について課題を中心に見てきましたが、視点を変えればこれは大きな**「チャンス」**でもあります。
今後、AIの発展やグローバル化、オープンイノベーションの拡大により、知的財産の価値はますます高まると予測されています。それに比例して、弁理士という専門家の需要も確実に増えていくと考えられます。
① AI時代でも「弁理士の仕事」はなくならない
AIにより一部の作業は自動化されるかもしれませんが、以下のような知財業務は人間による判断や創造力が不可欠です。
- 特許性の判断(進歩性・新規性など)
- 技術の本質を捉えたクレーム作成
- ライセンス・訴訟戦略に関する助言
- 経営や研究開発部門と連携した知財戦略構築
こうした「思考する仕事」や「コミュニケーション型業務」は、今後もAIに置き換わることはありません。つまり、技術と法律の両面に強い弁理士の価値はむしろ高まる一方なのです。
② 今後は「知財 × IT × 英語」が鍵になる
グローバルビジネスが当たり前となった現代では、特許出願や係争も日本国内にとどまりません。米国、中国、ヨーロッパへの出願戦略や外国出願書類の対応など、英語スキルが求められる場面が圧倒的に増えています。
また、AI特許・ソフトウェア関連・ビジネスモデル特許など、IT系の特許領域も急拡大中。プログラミングの基礎やIT法務の知識を持った弁理士のニーズは極めて高いです。
実際に、私自身も2024年にITパスポート・基本情報・応用情報を取得し、「知財×IT」のスキルセットの強みを実感しています。
このような複合スキルを身につければ、知財戦略における“架け橋”となれる存在になれるのです。
③ 弁理士資格があると「年収アップ」の転職も可能に
現在の職場に不満がある方や、知財業界へのキャリアチェンジを考えている方にとっても、弁理士資格は非常に強力な武器となります。
たとえば以下のような例があります:
- 特許事務所→大手メーカー知財部への転職で年収200万円アップ
- 知財部員→弁理士登録+転職でマネージャークラスに昇進
- 大学研究者→弁理士資格を活かして産学連携コンサルへ
いずれも共通しているのは、「弁理士資格があることで“専門職”として市場価値が跳ね上がる」という点です。
求人市場から見る“今が狙い目”の理由
最後に、人手不足のいまだからこそチャンスが広がっている求人市場の話をしておきましょう。
弁理士や知財経験者向けの求人は、年々ニーズが拡大しています。特に以下のような傾向があります。
- 経験年数が少なくても「ポテンシャル採用」されやすい
- 在宅勤務可・フレックスタイム制の求人が増加
- 英語スキルやITスキルを活かせる職場も多い
- 年収600万円〜1000万円クラスの高待遇求人も
そうした求人を探す際に活用したいのが、知財・法務特化型の転職サイト「リーガルジョブボード」です。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
✅ 特徴:
- 弁理士・知財部専門の求人が豊富
- 匿名でキャリア相談ができる
- 企業側の「本音」も聞きやすい
まとめ:弁理士の人手不足はチャンス!今こそ挑戦のタイミング
弁理士の人手不足は、業界全体にとって深刻な課題である一方、弁理士資格を持つ人にとっては大きなチャンスです。
- 弁理士試験の難易度の高さや、知財部門での専門性の求められ方から、若手人材の確保が難しい
- AI時代でも専門的な判断力やコミュニケーション力が求められ、弁理士の価値は今後も高まる
- 知財×IT×英語のスキルを磨くことで、業界内での存在感や転職市場での優位性が増す
- 年収アップやキャリアアップのチャンスが豊富にある
最後に:人手不足だからこそ“あなた”の挑戦が必要です
知財業界は今、変革と拡大の時代にあります。そこに専門家として関わる弁理士の存在は、かつてないほど求められています。
このブログを通して、少しでもあなたの弁理士への挑戦を後押しできれば幸いです。