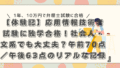特許に関わる仕事と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
「専門職で安定してそう」「理系じゃないと無理そう」「なんだか難しそう」……そんな声が聞こえてきそうですが、一方で最近では「ノルマがきつい」「ブラック」というネガティブな評判もSNSや掲示板で見かけるようになってきました。
実際、私自身も弁理士資格を取得して知財部や特許事務所で実務を経験してきた中で、「これはきついな」と感じた局面があったのは事実です。しかし、それは単なる労働時間や業務量の問題だけではなく、仕事の性質や組織文化、評価制度など、複合的な要素が絡んでいると強く感じます。
この記事では、弁理士・知財部員として働く中で見聞きした「ノルマの実態」や、「特許業界のリアル」について、現場感覚に基づいてしっかり深掘りしていきます。もちろん、対策やキャリアの選択肢についても触れていきますので、
- 弁理士を目指しているが、業界の雰囲気に不安がある
- 知財部や特許事務所への転職を検討している
- 特許実務のリアルな働き方を知りたい
ノルマが存在するのはどこ?知財部と特許事務所の違い
まず最初に明確にしておきたいのは、「特許業務にノルマがある=すべての職場でノルマに追われる」というわけではない、という点です。実は、知財部と特許事務所ではノルマの有無や厳しさが大きく異なります。
メーカーの知財部におけるノルマの実態
私は2021年からメーカーの知財部で勤務していますが、少なくとも私の所属している企業では「ノルマ」と呼べるような明確な数値目標はありません。発明発掘や出願件数などに目安はあるものの、あくまで参考値レベルで、実際の評価はもっと多面的です。
例えば、
- 発明者や開発部門との連携の質
- 担当案件の難易度や価値
- 係争対応や中間処理の的確さ
など、定量では測れない「質」の部分も重要視されます。
とはいえ、「うちはノルマなし」と言い切るのも危険で、企業の文化や上司のスタンスによっては、「なんで出願件数が少ないの?」「今年は目標達成しないとマズイぞ」といった実質的なプレッシャーがかかるケースもあるのが現実です。
特許事務所は“請負業務”なのでノルマが明確
一方で、特許事務所は基本的にクライアントから依頼された案件をこなす「請負業務」の側面が強く、明確な売上ノルマが設定されていることも少なくありません。
- 月に〇件の明細書作成
- 月の売上〇十万円以上
- 年間の報奨金制度(達成度で変動)
こうした数値が毎年提示される事務所もあり、「ノルマを達成しないと給料に響く」構造になっている場合も多いのです。
このような背景から、「特許 ノルマ きつい」という声は、主に特許事務所勤務の方々から出てくることが多いと感じます。特に新人や中堅が「量をこなして一人前」と見なされがちな事務所では、かなり厳しい状況になることもあります。
企業知財部の仕事についてはこちらでご紹介しています。
「ノルマがきつい」と感じる本当の理由とは?
前のセクションでは、特許業務におけるノルマの実態を、知財部と特許事務所に分けて解説しました。ここでは、さらに深掘りして、「なぜ特許業務のノルマがきつく感じられるのか」という根本原因を探っていきます。
1. ノルマの基準が“数”ではなく“質とスピード”の両立だから
例えば営業職であれば、ノルマは「契約〇件」「売上〇万円」といった明確な数字であり、成否がはっきりしています。しかし、特許業務においては「明細書を〇件書け」というだけでは評価されません。
なぜなら、特許明細書はそのまま法的効力を持つ文書だからです。明細書の品質が低ければ、特許が取れないばかりか、後々の無効審判や訴訟でも敗けてしまうリスクがあります。そのため、1件書くにも
- 技術内容の深い理解
- 発明のポイント整理
- クレームと実施例の整合性確保
- 拒絶理由通知に備えた記載の工夫
など、高い知識と注意力を要求される作業が多数発生します。
つまり、単なる“数”ではなく、「短期間で高品質な成果物を安定的に出す」ことが求められるのです。このプレッシャーが、特に経験の浅い弁理士や特許技術者にとって大きな壁となります。
2. 成果が見えにくく、フィードバックが少ない
特許業務の厄介な点は、出願した成果がすぐに評価されないことです。例えば、明細書を作成しても、その案件が登録されるまでに1年以上かかるのが一般的。その間に転職したり、評価者が変わったりして、「自分の成果って何だったんだろう?」と虚無感を感じてしまうこともあります。
また、上司や先輩が忙しい場合、レビューやフィードバックが形式的になりやすく、成長実感が薄いという側面もあります。この「やってもやっても達成感がない」構造も、ノルマを重く感じさせる原因です。
3. 技術+法律+文章力のトリプル要求がきつい
特許の仕事は、単なる技術文書の作成ではありません。そこには
- 技術的な正確性
- 法的に抜けのない記載
- 論理的な日本語表現
という三重苦があるため、「少し頑張ればこなせる」という業務ではなく、総合力が常に問われる世界です。どれか1つでも欠けると、クレームが通らない、出願が却下されるといった結果に直結します。
そのため、「経験年数が浅いから楽な案件を」という考えは通用しづらく、新人でも即戦力として扱われる現場も多いのが特徴です。こうした期待とのギャップが、ノルマのプレッシャーとして圧し掛かってきます。
ノルマがきついなら「転職」も視野に入れるべきか?
これまで見てきたように、特許実務におけるノルマは、量的な要求だけでなく質・スピード・責任の重さが複合的に絡むことで、かなりのストレス源になります。では、「自分にはきつすぎる」と感じた場合、転職してもいいのでしょうか?
答えはYESです。特許業界は、弁理士・知財実務者にとって意外と“選択肢が広い”業界です。
1. 「きつさ」は職場の文化と業務の種類で激変する
まず知っておきたいのは、特許の“きつさ”は企業や事務所によって全く異なるという点です。
たとえば、
- 「年間明細書80件、1人で書いてね」という事務所もあれば、
- 「特許の構想・発明提案から丁寧に進めよう」という社内知財部もあります。
つまり、「この仕事向いてないかも」と感じても、それは今の職場の文化や体制が自分に合っていないだけという可能性もあります。
転職によって、下記のような“働きやすい環境”に移ることも可能です:
| タイプ | 特徴 | おすすめな人 |
|---|---|---|
| 社内知財部(大手メーカー) | ノルマが緩やか。発明提案~戦略まで一貫して関われる。 | 長期視点で技術に関わりたい人 |
| 中小事務所 | 個人案件が多いが、フレキシブルに働ける場合も。 | 働き方を調整したい人 |
| 外内専門事務所 | 英文特許が中心。納期管理がしっかりしている。 | 英語に抵抗がない人 |
| 出願支援企業(特許翻訳など) | 明細書は書かないが周辺業務に関わる | 特許業界の周辺職に興味がある人 |
つまり、「特許=ブラック」ではなく、「合う職場を選べば快適」というのが実情です。
2. 弁理士資格・知財経験は転職市場で強い
私は実際に、弁理士合格後に転職を検討したことがありました。調べてみて驚いたのは、知財経験があるだけで想像以上にスカウトが届いたことです。特に、
- 弁理士資格を持っている
- 明細書作成経験がある
- 技術分野に詳しい(電気・機械・化学など)
という条件が揃うと、年収600〜900万円スタートの求人も複数存在します。しかも、多くの企業は
- ノルマ少なめ
- フルリモート可
- ワークライフバランス重視
といった条件を打ち出しており、転職により今より穏やかな職場に移ることも十分に可能です。
3. 特許業界に強い転職サービスを活用しよう
特許・知財業界の求人は、一般的な転職サイトにはあまり出回りません。そのため、特許専門の転職エージェントを活用するのが効果的です。
例えば、下記のような転職サービスは、弁理士・知財実務経験者向けに非公開求人を豊富に保有しています。
✅おすすめ転職サイト:👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
このようなサイトでは、知財業界に特化した求人が豊富で、希望条件に合った案件が見つかりやすいです。登録・閲覧は無料なので、まずは情報収集から始めてみてください。
また、弁理士資格取得後の転職についてはこちらの記事にまとめています。
特許業界で生き残るには「正しい武器」を持つべき
ここまで読んできて、「やっぱり特許の仕事ってきついな…」と感じた方も多いと思います。しかし、私はこうも考えています。
特許業界は“正しいスキルと戦略”を身に着ければ、十分にラクに生きられる世界である。
実際、私自身は以下の流れでキャリアを組み立ててきました。
- 弁理士試験を効率的に突破
- 企業知財部で経験を積む
- 必要に応じて職場の環境を見直す
- 常に“潰しがきく”スキル(IT、英語、文書力)を強化
そして、この「正しいスキルと戦略」を効率的に学ぶツールとしておすすめしたいのが、次のセクションでご紹介する【弁理士試験対策講座】です。
弁理士試験は「効率化」こそが突破のカギだった
ここまで「特許業界のきつさ」についてお伝えしてきましたが、もし今あなたが「この世界に飛び込んでみたい」「でも難しそう…」と感じているなら、私はこう言いたいです。
弁理士試験は、正しい方法で取り組めば誰でも突破できる。
これは私自身の経験に基づいた実感です。
私は2020年10月から弁理士試験の勉強を始め、約1年3ヶ月で合格しました。
しかも、当時はフルタイムで働きながら、平日は早朝1時間+昼休み30分+夜に2時間、休日はまとめて5〜6時間という学習スタイル。いわゆる“社畜合格組”です。
そんな中でも合格できた最大の要因は、教材選びに妥協しなかったこと。
具体的には、スタディング弁理士講座を選んだことが、私の合格戦略の中核にありました。
スタディング弁理士講座が「働きながら合格」を支えた理由
私は、スタディング講座をメインに使いながら、過去問・青本・条文ベースのアウトプットを独自に組み合わせて学習を進めました。その中でも、スタディングの以下の機能は本当に神ツールだと今でも思っています。
① スキマ時間にサクッと学習できる「動画講義」
通勤中や昼休みなど、5分〜10分の細切れ時間を積み重ねられるのは、働きながら勉強する上で本当に重要です。
スマホ一つで動画を再生できるので、電車の中やジムの休憩中でも、講義を視聴して知識を定着させることができました。
しかも、講義内容が「初学者でも理解できるようにかなり丁寧」なのが特長。私は文系教養ゼロの理系出身ですが、それでも民法・著作権など法律系の科目にもすんなり入っていけました。
② スマホで問題演習ができる「WEB問題集」
紙のテキストを持ち歩く必要がなく、いつでもどこでも演習できるのが最高です。
私は「講義を観る→問題を解く→不正解だけチェック→復習」のサイクルを毎日繰り返し、少しずつ得点力を積み上げていきました。
また、AI機能が搭載されており、**「苦手な論点を自動で可視化・優先的に出題」**してくれるので、独学で陥りがちな“やみくも勉強”を防げたのも大きいです。
③ 圧倒的なコストパフォーマンス
これが何よりの魅力。私は受講料を含めて総額10万円以下で弁理士試験に合格できました。
他の予備校では最低でも30万円〜50万円という費用がかかる中で、この価格帯は破格です。
スタディング講座はこんな人におすすめ
私の体験からして、以下のような人にはスタディングがとてもフィットします:
- 働きながら弁理士を目指している社会人
- できるだけ費用を抑えて合格したい人
- 通学の時間が取れない地方在住の方
- 勉強の習慣づけが苦手な人(学習管理機能が助けになる)
※無料お試し講座もあるので、「自分に合うかどうか」を体験してから判断するのがおすすめです。
また自身の体験についてもこちらでご紹介しています。
特許業界は「転職」が普通?:知財職の転職事情と選択肢
「ノルマがきつい」「評価が不明確」「上司との関係がストレス」「将来が見えない」――。
もし、あなたが今の職場に疑問や限界を感じているなら、転職という選択肢を現実的に考えてもよい時期かもしれません。
特許業界、特に知財部や特許事務所の世界は、転職が比較的当たり前に行われる業界です。
実際、私の周囲でも「年収を上げたい」「もっと専門性を高めたい」「労働環境が合わない」などの理由で転職した人が何人もいます。
なぜ知財職は転職しやすいのか?
理由は大きく2つあります。
1. スキルが汎用的に通用するから
特許明細書を書く力、審査対応をする力、法律知識、論理的思考――これらは会社が変わっても使えるスキルです。
特に明細書作成経験がある人は事務所でも即戦力とされやすく、経験年数に応じて高待遇で迎えられることも。
2. 人材が慢性的に不足しているから
知財系の仕事は専門性が高い一方、年々応募者数が減少傾向。
そのため、一定の実務経験がある人材は非常に貴重とされており、企業・事務所ともに常に良い人材を探しています。
「きつさ」を感じたら、まずは環境を疑う
「自分が仕事に向いていないのかも」と悩む前に、まずは**職場環境が自分に合っていないだけでは?**と疑ってみてください。
特許事務所でも、ブラックなところからホワイトなところまで幅があります。企業知財部も、開発と兼務なのか、専門部署なのかで大きく異なります。
私自身も「もっと自分に合う環境があるのでは?」と考え、実際に転職活動を視野に入れたことがあります。
結果的には続けることを選びましたが、選択肢を知るだけでも気持ちがだいぶラクになったのを覚えています。
迷ったら「情報収集」だけでもOK
転職するかどうかは、すぐに決断する必要はありません。
ですが、情報を集めるだけでも、自分のキャリアの選択肢が広がります。
そして何より、「今の環境がすべてではない」と知ることが、精神的な安心につながるのです。
まとめ:特許業界の「きつさ」は、環境と準備で乗り越えられる
ここまで、「特許業界のノルマがきつい」というテーマを軸に、現場のリアルや業界の構造的な問題、そして解決のヒントをお話ししてきました。
結論から言えば――特許業界の“きつさ”は、自分自身に問題があるというよりも、「職場環境」や「準備不足」が原因であることが多いのです。
✔ ノルマが異常に厳しい
✔ 人手が足りず残業が慢性化している
✔ 上司が明細書をろくにチェックせず全責任がこちらに回ってくる
こうした状況では、どんな優秀な人でも疲弊してしまいます。
ですが、選択肢は常にあります。
たとえば――
- より良い職場環境を求めて転職する
- 自分の実力を高めて評価を勝ち取る
- 弁理士資格を取得してキャリアの選択肢を広げる
これらの手段は、どれも「今の悩みを未来で解決する力」になり得ます。
弁理士資格は「選べるキャリア」のパスポート
私自身、弁理士試験を通して思ったことがあります。
それは、この資格があることで“選べる”人生になるということです。
弁理士資格があれば、社内での昇進や専門職への道が開けますし、特許事務所やフリーランスとして独立するという選択肢も見えてきます。
「今の職場ではもう限界かもしれない」
「でも、せっかく知財をやってきたし、何か道はないかな」
そう思っている方には、弁理士資格取得というチャレンジは決して無駄にならない選択肢です。