こんにちは!今回は、私が基本情報技術者試験に合格した実体験をお伝えします。私は企業内で弁理士として働いており、IT業務には直接携わっていませんが、最近の業務でITの基礎知識が必要だと痛感し、勉強を始めました。
特に、プログラミング経験ゼロからの挑戦だったので、同じように「文系出身・IT未経験」な方々に役立つ情報をお届けしたいと思います。
2024年7月に受験し、無事に合格できました。特に150〜200時間という学習時間で、なぜ合格できたのか、その理由とノウハウを詳しく解説していきます。
知財業務にITスキルが必要な理由
知財部門はこれまで「法務寄りの部署」と見られがちでしたが、近年のDX(デジタルトランスフォーメーション)やIT化の進展により、技術理解の重要性が増しています。具体的には以下の理由があります。
1. ソフトウェア関連特許・AI特許の増加
近年の出願の多くは、AI、IoT、クラウド、モバイルアプリなどソフトウェアに関連しています。
これらの特許の明細書を読む、発明者と打ち合わせをする、請求項を作成する際には、基本的なアルゴリズムやシステム構成の理解が求められます。基本情報技術者試験で学ぶ知識は、こうした技術理解の基盤になります。
2. OSS(オープンソースソフトウェア)ライセンス管理
企業の製品・サービスは、OSSを多数組み込んで開発されることが一般的になっています。
知財部では、GPL、MIT、Apacheなどのライセンス条件を理解し、コンプライアンスを確保する役割が増えています。
基本情報技術者試験では、OSSの概要やライセンス種別の基礎が学べるため、契約リスクの評価やエンジニアとの議論がスムーズになります。
知財部が関わるOSSについてはこちらで解説しております。
3. セキュリティ・情報管理
情報漏洩、サイバー攻撃、脆弱性対応など、企業のITリスクは知財戦略にも直結します。
例えば、営業秘密管理や技術情報の保護には、ネットワークやデータベースの基礎知識が不可欠です。
基本情報技術者試験では、セキュリティ対策の基本概念が出題されるため、知財部門でも大いに役立ちます。
4. 社内DX推進における橋渡し役
最近では、知財データの可視化、AIによる特許調査、IPランドスケープなど、知財部門もDXの波に直面しています。
システムベンダーや社内IT部門とのコミュニケーションを円滑に進めるためには、ITリテラシーが求められます。
こうした背景から、知財部門においてもIT資格の取得はキャリア形成上の強みとなり、社内評価や転職市場でも大きな武器になります。
知財業務全体についてはこちらでご紹介しておりますので、ご参照ください。
1. 基本情報技術者試験とは?
基本情報技術者試験は、情報処理推進機構(IPA)が主催する国家資格の一つで、ITエンジニアの登竜門とも呼ばれます。ITパスポートよりも高度な試験で、技術系・マネジメント系・戦略系まで幅広い知識を問われるのが特徴です。
- 試験形式:CBT方式(コンピューター上で実施)
- 試験科目:科目A(知識問題)・科目B(プログラミング問題)
- 合格率:令和5年度は47.1%(近年はやや易化傾向)
ITパスポートに合格した際の記事についてはこちらをご参照ください。
2. 私の試験結果
2024年7月受験の結果は次の通りです:
- 科目A:770点 / 1000点(合格点600点)
- 科目B:735点 / 1000点(合格点600点)
特に科目Bはギリギリでの突破となりましたが、未経験者にとっては大きな達成感がありました。
3. 試験内容の詳細
科目A: 基礎知識と計算問題
科目Aでは、ITの基礎からマネジメントまで幅広い範囲が出題されます。出題範囲には以下のような分野があります:
- テクノロジ系(コンピュータシステム、開発技術)
- マネジメント系(プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント)
- ストラテジ系(システム戦略、企業と法務)
サンプル問題(科目A)
「ボットネットにおけるC&Cサーバの役割として、適切なものはどれか?」
- ア) Webサイトのコンテンツをキャッシュし、本来のサーバに代わってコンテンツを利用者に配信する
- イ) 利用者認証時のパスワード盗聴を防止する
- ウ) ワンタイムパスワードを発行することにより、認証時のパスワード盗聴を防ぐ
- エ) 侵入したコンピュータに対して、不正な操作をするよう外部から命令を出す
科目B: プログラミングとアルゴリズム
科目Bでは、主に疑似言語を用いた問題が出題されます。プログラミングの基礎やアルゴリズム、情報セキュリティの知識が問われます。特に、問題解決のための論理的思考が求められます。
サンプル問題(科目B)
「以下のプログラム中に入れる正しい答えを選びなさい」
pseudoコードをコピーする整数型: fee(整数型: age)
整数型: ret
if (age <= 3)
ret ← 100
elseif ( )
ret ← 300
else
ret ← 500
endif
return ret
解答群:
- ア) (age が 4 以上) and (age が 9 より小さい)
- イ) (age が 4 と等しい) or (age が 9 と等しい)
- ウ) (age が 4 より大きい) and (age が 9 以下)
- エ) age が 4 以上
4. 私の学習方法と勉強時間
- 総学習時間:150〜200時間
- 1日の勉強時間:1〜2時間
- ITパスポートの知識を活用:基礎があったのでスムーズでした。
- 重点学習:科目Bの演習を繰り返し、アルゴリズムの理解を強化。
5. スタディングを利用した感想と利点
私が使ったオンライン講座は「スタディング」です。結論から言うと、これがなければ合格は厳しかったと思います。特に以下の点で優れていました。
- スキマ時間学習:スマホで講義を倍速再生し、通勤時間も有効活用。
- わかりやすい動画講義:未経験者にも配慮した丁寧な説明。
- 直前対策模試:本番形式の模試で得点感覚を磨けた。
- 進捗管理機能:自分の学習状況を見える化でき、モチベ維持に効果大。
\無料体験はこちらから/
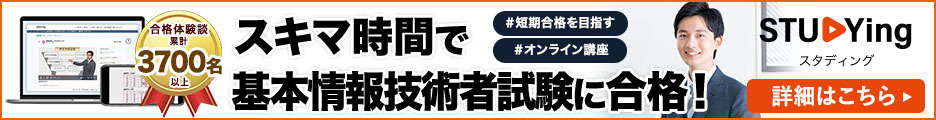
6. 実務未経験者のB問題対策
私はプログラミングの実務経験が全くなかったため、科目B(プログラミング問題)の演習には特に時間をかけました。以下の対策を行いました。
- YouTubeでの解説動画視聴
- 【初心者向け】基本情報技術者試験 科目B|アルゴリズムをゼロから理解するという動画を繰り返し視聴し、理解を深めました。
- 問題集を購入
- 演習が不足していると感じたため、オリジナル問題集を購入し、さらに問題を解くことで実践力を高めました。以下の問題集がおすすめです。
7. 試験合格のためのポイント
最後に、基本情報技術者試験に合格するためのポイントをお伝えします。
- 早めに試験範囲を把握する
- 早期に試験範囲を確認し、効率よく学習を進めることが大切です。
- 繰り返し問題を解く
- 特に科目Bは演習が重要。問題集を繰り返し解き、理解を深めることが必要です。
- 集中して学習時間を確保する
- 毎日少しずつ学習を続けることで、試験前に焦ることなく合格ラインをクリアできます。
8. 知財部の視点から見たITスキルの必要性
企業の知的財産部(知財部)は、ITと直接関わらないと思われがちですが、近年のIT化・DX推進により以下の知識が重要視されています。
- ソフトウェア特許の理解:アルゴリズムやデータ処理手法の基礎理解。
- OSSライセンス管理:ソフトウェア開発部門との連携強化。
- セキュリティの基礎:サイバー攻撃に関する契約・交渉・リスク管理。
私自身、基本情報技術者試験を通じてITの基礎知識を得たことで、社内の技術者との会話がスムーズになり、業務の幅が広がりました。
9. FAQ:基本情報技術者試験のよくある質問
Q1. 未経験者でも合格できますか?
A. 可能です。特に科目Aは知識問題なので対策しやすく、科目Bは演習量でカバーできます。
Q2. ITパスポートと併願するべきですか?
A. まずITパスポートで基礎を固め、その後基本情報に進む流れが効率的です。
Q3. どの参考書がおすすめですか?
A. 『キタミ式イラストIT塾』シリーズとスタディング講座の組み合わせが初心者には最強です。
Q4. 社会人が独学できますか?
A. 可能ですが、忙しい社会人にはスタディングなどのオンライン講座が圧倒的に効率的です。
10. まとめ
基本情報技術者試験は、文系・未経験者でも150〜200時間の学習で合格可能な資格です。
特に以下のポイントが重要です。
- 科目B対策に力を入れる。
- スタディングのようなオンライン講座を活用。
- 知財部など非IT部門でも役立つ知識を得られる。
IT未経験の方やスキルアップを考えている方には、ぜひチャレンジしてほしい資格です。
また、私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)






