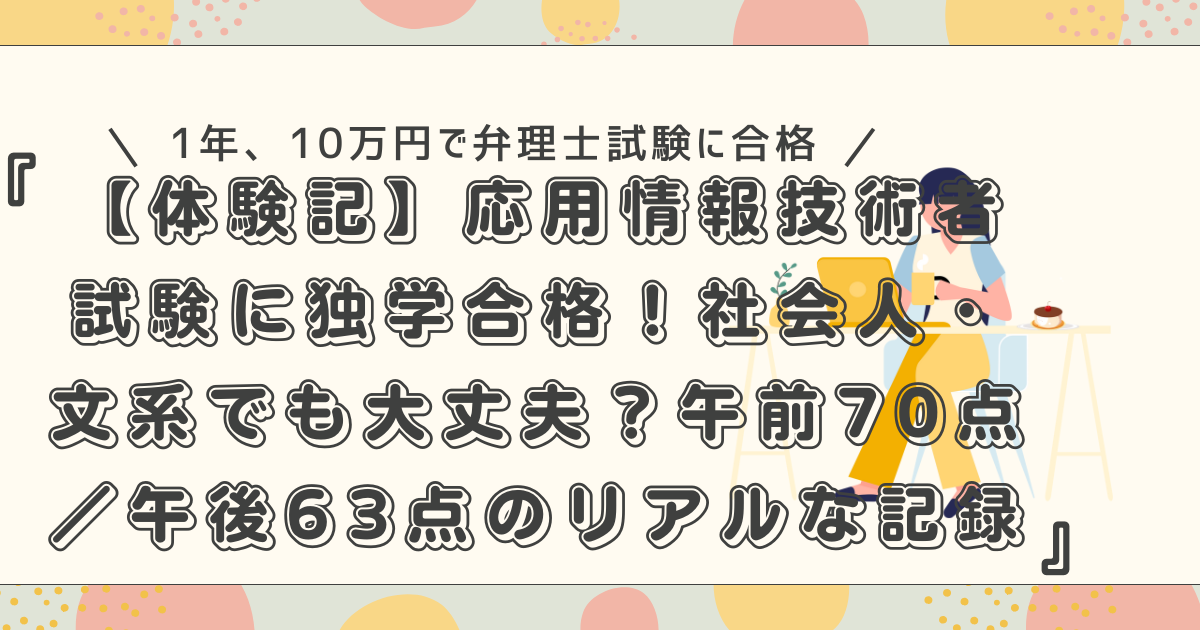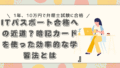1. 応用情報技術者試験を受けた理由【社会人の挑戦】
こんにちは、ブログにご訪問いただきありがとうございます。
運営者のcoffeeです。
今回は、2024年12月に合格した応用情報技術者試験について、実際のスコアや勉強法、試験当日の感想などを交えながら、働きながら合格を目指す社会人の方に役立つ内容をシェアしていきたいと思います。
自己紹介を簡単にすると、私は2018年に理系大学院を修了後、メーカーの開発職に就職。
2021年には社内異動で知財部に移り、2022年に弁理士試験に合格しました。
2024年にはITパスポート→基本情報技術者→応用情報技術者と段階的に情報処理技術者試験を取得しています。
特にこの応用情報は、国家試験としてのレベルも高く、「IT人材としての基礎力+応用力」が問われる試験。
個人的にも、弁理士としてIT技術に強くなりたいというキャリア戦略の一環として、本気で取り組んだ試験でした。
合格結果(2024年12月)
- 午前試験:70点(合格ライン60点)
- ストラテジ系:20点
- マネジメント系:7.5点
- テクノロジ系:42.5点 - 午後試験:63点(合格ライン60点)
- 選択問題:1(情報セキュリティ)、2(ネットワーク)、7(プロジェクトマネジメント)、9(システム監査)、10(組込み)
午後がギリギリだったので、合格の手応えは正直微妙でしたが、「ちゃんと勉強すれば社会人でも合格できる」という手応えを感じました。
2. 応用情報技術者試験とは?難易度・評価・キャリアパスの位置づけ
■ 試験の基本情報
応用情報技術者試験(AP)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験で、情報処理技術者試験の中では中上級レベルに位置づけられます。
「基本情報技術者(FE)」の上位資格であり、ITエンジニアだけでなく、IT×マネジメント、IT×戦略、IT×監査など、より実務寄りな知識を問われるのが特徴です。
■ 合格率と難易度
- 合格率:約20%前後(毎回変動あり)
- 試験方式:午前・午後の2部構成
- 午前:選択式(マークシート)、午後:記述式
午後試験の難しさがこの試験の肝とも言われており、「実務に近い場面で、どう考えて行動するか」が問われます。
また選択問題制のため、得意な分野を選べる一方で、苦手分野が出た場合のリカバリーは難しいという面もあります。
■ 資格のメリット
この資格はただの「お勉強」ではなく、以下のようなキャリアアップに直結するメリットがあります。
- 履歴書での評価が高い(国家試験)
- 大手企業では資格手当の対象となることも多い
- SE/プログラマはもちろん、ITコンサルや知財部門でも価値がある
- 転職市場でも「応用情報を持っている=最低限のIT基礎力+業務理解力がある」と判断される
実際、私のような知財の仕事に携わる人間にとっても、ソフトウェア特許やセキュリティ関連の知識は非常に実務的です。
特にAI・IoT時代において、「ITがわかる弁理士・知財人材」はかなり価値が上がってきていると感じます。
■ IT初心者・文系でも合格できる?
「理系じゃないと無理では?」「午後問題が難しそう…」といった声もよく聞きますが、実際には文系出身でも合格している人は多数います。
ただし、午後の記述問題は「文脈を読み取って自分の言葉で解答する」必要があるため、本質的な理解をベースとした学習が不可欠です。
私自身は理系出身ですが、午後の記述問題にはかなり苦戦しました。
一方で、ある程度過去問のパターンを掴めば、出題傾向が読める試験でもあります。
■ 勉強の第一歩におすすめの一冊
ちなみに、応用情報の全体像をつかむには、まず一冊、体系的にまとまった教材を読むのが近道です。
私が最初に手に取ったのは、以下の書籍です。
📘【PR】『キタミ式 応用情報技術者 令和最新版』
図解が豊富で「ITってこういう構造だったのか!」と気づかされることが多かったです。
午後対策としても、各分野のつながりをイメージしやすくなり、基礎固めにぴったりでした。
3. 応用情報の勉強法と使った教材、スケジュール管理のコツ【社会人独学でもOK】
■ 勉強期間:基本情報合格直後から応用情報へシフト
私が応用情報の勉強を始めたのは、2024年8月に基本情報技術者試験に合格した直後でした。
「せっかく基礎ができた今なら、応用情報まで一気にいけるはず」と考えて、間髪入れずに勉強をスタート。実質、4ヶ月程度の学習期間となりました。
▽ 勉強時間の確保:1日1〜1.5時間が限界
弁理士としての業務が日中フル稼働、かつ知財の社内対応や発明者ヒアリングも多く、平日にまとまった勉強時間を取るのは困難でした。
そこで私がとった作戦は以下の通りです:
✅ 朝時間とスキマ時間を活用
- 平日朝:30分(通勤前 or 通勤電車内にて動画視聴 or 要点確認)
- 昼休み:15〜20分(午前問題の一問一答 or 用語チェック)
- 帰宅後夜:30〜45分(午後問題の読解トレーニング)
✅ 休日は「午後試験対策」に集中
- 午前知識は平日コツコツ積み重ね
- 土日祝などの休日には、記述対策や事例問題の読み込みに特化
このように平日はインプット中心、休日はアウトプット中心というサイクルで、学習のバランスを整えました。
▽ なぜ「短期集中型」がよかったか?
社会人の学習は、とにかく「長期戦にするとモチベーションが落ちる」のが難点です。
私の場合、4ヶ月というゴールが見えやすい期間設定だったことが、以下の点で効果的でした。
- 「いつまでに何を終えるか」が逆算しやすい
- 緊張感をもって日々の勉強に向き合える
- 「とりあえず今日はやらなくていいか…」という甘えを防げる
また、基本情報の知識がまだ新鮮なうちに応用情報に挑んだことで、復習時間を減らせたのもメリットです。
第2節:スタディング応用情報技術者講座レビュー【社会人の独学を強力にサポート】
応用情報の勉強を始めた当初、私もまずは書籍と過去問で進めていました。
でも、午後試験の記述問題対策がどうしても不安だったこと、そして通勤や昼休みなどのスキマ時間をもっと有効活用したかったことから、途中からスタディングの応用情報技術者講座を導入しました。
結論から言うと、
「社会人で時間がないけど、確実に合格したい」という人にはかなりおすすめできる講座
です。
以下に、私が実際に感じたメリットと、活用のポイントを整理してご紹介します。
✅ ポイント①:音声講義×倍速再生で“ながら学習”が捗る
スタディング最大の特徴は、全講義が動画+音声で構成されていること。
- 通勤中:スマホ+イヤホンで講義を2倍速再生
- 帰宅後:自宅でタブレット視聴&そのまま問題演習
- 家事中:Bluetoothスピーカーで“耳だけ”復習
このように、座って机に向かわなくても学習ができる設計になっているのが大きな強みです。
社会人にとっての最大の壁は「まとまった時間が取れない」こと。
その壁を崩すのが、まさにこのスキマ時間学習の仕組みです。
✅ ポイント②:午後問題対策も“記述の読み方”が分かる構成
午後問題って、設問が長文で、しかも「自分の言葉で書け」と言われる…つまり、単なる暗記じゃ通用しません。
私がスタディングで「これはありがたい」と思ったのは、
✅ 設問文のどこをどう読んで、どのように解釈するか
✅ 答案に必要なキーワードの選び方
といった思考プロセスのナビゲーションまでしてくれるところ。
特に「情報セキュリティ」「プロジェクトマネジメント」「システム監査」などは、記述にクセがある分野なので、プロ講師による丁寧な解説が武器になります。
✅ ポイント③:復習しやすい設計と進捗管理
社会人にとって「今日はどこまでやったか?」「あと何が残ってるか?」が分かりにくい教材は致命的です。
その点、スタディングは
- 学習進捗をグラフ表示
- 復習タイミングを自動リマインド
- 1単元ごとの学習時間も記録
といった学習管理機能が充実しているため、「試験日までに何をすべきか」が常に見える化されて安心感があります。
✅ 料金も良心的&コスパ高い
書籍+過去問+講座の組み合わせは、金銭的に負担になるかと思っていましたが、スタディングは1〜2万円台で一通り揃うので、むしろ割安に感じました。
- ✅ 分かりやすさ
- ✅ 時間効率
- ✅ 合格への再現性
これらを考えると、コスパの良さは市販教材以上だったと言えます。
▶ スタディング公式サイトはこちら【PR】
働きながらの資格取得を本気で目指すなら、まずは無料講座体験をチェックしてみるのがおすすめです👇
↓ スタディング 応用情報技術者講座を見てみる
応用情報技術者はこちらまとめ:応用情報は、社会人のキャリアを広げる“武器”になる
応用情報技術者試験は、決して「一夜漬けでどうにかなる」ような甘い試験ではありません。
ですが、正しい戦略と適切な教材を選べば、社会人でも無理なく合格を狙える試験です。
私自身、知財部門で働きながら、忙しい毎日の中で1日1〜1.5時間を積み重ねる勉強法を徹底し、最終的には合格を勝ち取ることができました。
特に、午後問題対策に不安がある方や、時間を効率的に使いたい方には、スタディングのようなオンライン講座が大きな助けになります。
スキマ時間での動画学習や、音声講義での「ながら勉強」は、働く社会人にとって強力な武器になるはずです。
また、これまでに【ITパスポート】【基本情報技術者試験】についても、同じように社会人目線でまとめた記事を公開しています。
どちらも初学者や文系の方にも役立つ内容なので、よかったらぜひこちらも読んでみてください👇
社会人でも、30代でも、文系でも。
正しいやり方を知って、あきらめずに続ければ、ITスキルは着実に武器になります。
ぜひこの記事が、これから資格取得を目指すあなたの背中を押すことになればうれしいです!