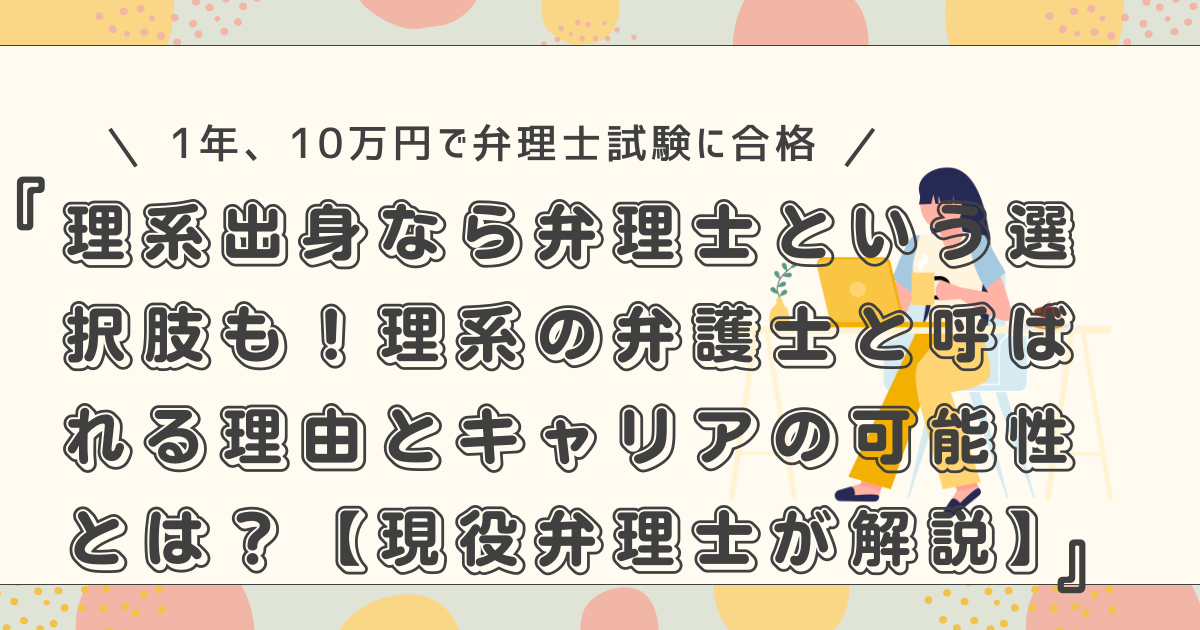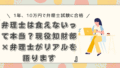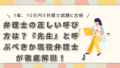理系出身者が「弁理士=理系の弁護士」と呼ばれる理由とは?
「理系出身なんだけど、将来このままでいいのかな…」「専門知識を活かしてもっとステップアップしたい…」そんなふうに感じたことはありませんか?
こんにちは。当ブログを運営している現役弁理士のcoffeeです。
私は2018年に理系大学院を卒業し、メーカーの開発職に就きました。その後、2020年に弁理士試験の勉強を始め、2022年に合格。現在は企業知財部で、特許関連の実務に携わっています。
理系から法律の世界に…?
一見かけ離れているように見えるかもしれませんが、実は「弁理士」は理系出身者にこそ向いている国家資格なんです。
「理系の弁護士」と言われる弁理士とは?
弁理士という資格は、あまり一般的に知られていないかもしれません。
しかし、弁理士は「特許・実用新案・意匠・商標」など、知的財産(=知財)に関する法律業務の専門家です。
特に特許出願では、発明の内容を技術的に理解した上で、法的に有効な書面を作成しなければなりません。ここに理系的な素養が必要不可欠になるのです。
そのため、弁理士はしばしば「理系の弁護士」とも呼ばれます。
なぜ理系出身者に向いているのか?
理由は大きく3つあります。
① 特許・発明の本質を理解できる
理系出身であることは、発明や技術の構造・原理を理解する力につながります。
これは、弁理士が特許明細書を書く際に非常に重要です。
② 論理的思考力が活きる
技術的なバックグラウンドを持つ方は、論理展開や因果関係の整理に長けています。
これは法律文書を扱う上でも大きな武器になります。
③ 法律は勉強で補える
理系出身者にとってハードルになるのは「法律」の知識。
ですが、これは後から勉強して身につけられます。現に私も法律は初学者でしたが、働きながら最短ルートで合格できました。
その際に非常に役立ったのが、オンライン講座の「スタディング弁理士講座」です。
通勤中にもスマホで学習でき、法律初学者にも優しい解説が特徴です。
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)弁理士と弁護士の違いとは?共通点とあわせて解説
弁理士が「理系の弁護士」と呼ばれることがありますが、実際には弁理士と弁護士は別の国家資格であり、役割や業務範囲も異なります。
ここではその違いを明確に整理し、理系出身者がなぜ弁理士を目指しやすいのかを掘り下げます。
【比較表】弁理士と弁護士の主な違い
| 項目 | 弁理士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 業務範囲 | 知的財産権(特許、商標、意匠など)に特化 | 民事・刑事・商事など法律全般を扱う |
| 資格取得難易度 | 難関(合格率約6〜8%) | 非常に難関(司法試験合格率約30〜40%) |
| 主な顧客 | 発明者、企業の知財部、スタートアップ企業 | 個人、企業、行政など幅広い |
| 専門性 | 理系分野に強い知識が求められる | 法律全般の深い知識が求められる |
| 出願代理業務 | 〇(特許庁への出願代理が可能) | ×(出願代理は不可) |
| 裁判への関与 | △(一部、特許訴訟における補佐人として関与可能) | ◎(全面的に代理人として裁判可能) |
弁理士は「技術×法律」のハイブリッドな専門職
特許や実用新案の仕事では、技術内容を正しく理解し、それを法的に有効な形に落とし込むスキルが求められます。
このような業務を担う弁理士は、まさに「理系知識を土台にした法律専門職」と言えます。
弁護士のように民法や刑法を駆使して離婚や刑事事件を扱うわけではなく、知的財産権に特化したスペシャリストであるため、理系出身者のスキルがダイレクトに活かせるフィールドです。
弁護士と違って、理系バックグラウンドが強みになる
弁護士は基本的に文系出身が多く、理系知識を活かす場面はあまりありません。
一方、弁理士は逆です。むしろ理系出身であることが評価されやすく、業務の理解もスムーズです。
特に下記のようなバックグラウンドを持っている方には、弁理士資格は強い武器になります。
- 機械、電気、化学、バイオ、IT系の学位
- 研究開発・製造技術職としての経験
- 理系分野の大学院修了者
このような理系スキルを活かして、企業内知財部や特許事務所でのキャリア構築が可能になります。
理系×法律の強みを活かしたキャリア形成
実際に私自身も、理系大学院卒 → メーカーの開発職 → 知財部 → 弁理士というキャリアをたどっています。
技術的な理解ができるからこそ、発明の本質を押さえた強い特許が書けるようになり、社内での評価や年収にもつながっていきました。
また、弁理士資格を取得したことで、以下のようなキャリアの可能性も開けてきます:
- 大手企業知財部への転職(年収アップも現実的)
- 特許事務所での専門職(在宅勤務や副業の自由度もあり)
- 将来的な独立開業(自分の名前で仕事ができる)
転職市場でも「弁理士×理系」という組み合わせは非常に希少で価値が高く、特に20〜40代の理系出身者にはおすすめできるキャリアです。
📚 補足:弁理士の仕事内容が気になる方へ
理系出身者が弁理士試験に向いている理由と、苦手な「法律」をどう克服するか
弁理士試験というと、「法律の勉強が大変そう…」というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
特に理系出身の方にとって、法律は未経験の分野であり、最初は戸惑いもあると思います。
ですが、結論から言えば理系出身者のほうが弁理士試験に向いている側面も多くあるのです。
ここではその理由と、勉強上の工夫・実践的な対策をご紹介します。
理系の強み①:複雑な概念を論理的に整理する力
理系の大学や大学院で身につけてきた「論理的思考力」は、弁理士試験でも非常に活きます。
例えば、特許法の条文を読む際、構造的に整理して理解する力が必要です。これは、理系分野でいうところの「数式を構造的に理解する力」と似ています。
特に、以下のような思考パターンが活きます:
- 前提条件を正確に押さえる
- 概念の関係性を構造的に理解する
- 「なぜそうなるのか」を因果で説明できる
このような力は、まさに理系の得意分野です。
理系の課題:法律用語や文系的表現への慣れ
一方、最初につまずきやすいのが「法律の言い回し」や「抽象的な表現」です。
たとえば「実施可能要件」「新規性喪失の例外」「専用実施権」など、初学者には耳慣れないワードが並びます。
これを無理に一から理解しようとするよりも、まずは**「よく出るパターン」から押さえていくのがコツ**です。
私自身、スタディング弁理士講座を活用して、法律の基礎用語に早めに慣れることができました。
スマホ学習と動画講義を組み合わせれば、法律アレルギーもかなり軽減できます。
合格に必要な参考書の選び方も重要
弁理士試験は「過去問の繰り返し」と「基本書の精読」がカギとなります。
法律に慣れていない方は、法律の全体像をやさしく解説した入門書を1冊手元に置いておくと安心です。
📘 おすすめ書籍:『弁理士スタートアップテキスト』
→ 弁理士試験の全体像をやさしく解説しており、法律に苦手意識がある方にも最適な入門書です。
理系出身者こそ、知財業界への転職が有利になる
弁理士資格を取得したことで、私自身キャリアの選択肢が一気に広がりました。
特に理系出身者は、企業の知財部や特許事務所で**「即戦力」として求められる**傾向にあります。
たとえば下記のような求人は、理系バックグラウンドを活かせる典型的な例です:
- 化学・機械・電気系出身者歓迎の特許技術者
- メーカー知財部での特許出願業務(年収500万〜800万円)
- 弁理士資格取得支援ありの特許事務所
こうしたポジションを効率よく探したい場合には、知財・法務系に特化した転職エージェントの活用が有効です。
🎯 知財・特許・法務職に強い転職エージェント:リーガルジョブボード
→ 弁理士・特許技術者などの非公開求人が豊富。知財業界を熟知したキャリアアドバイザーがサポート。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
まとめ:理系出身者が弁理士を目指すべき理由と成功へのポイント
この記事では、「理系出身の方が弁理士というキャリアを選ぶ意義」について、現役弁理士としての私の経験も交えて解説しました。
理系の強みが活きる専門資格
弁理士は「理系の弁護士」とも称されるほど、技術的知識と法律知識の両方を駆使する専門職です。
理系出身者は技術の本質を理解できるため、特許や知的財産権の分野で非常に強みを発揮します。
法律は努力で補える部分
確かに法律は理系の方にとって初めて学ぶ分野で難しく感じるかもしれません。
しかし、体系的に学べば誰でも理解できる内容です。私自身、法律初心者でしたが、最短ルートで合格を果たしました。
キャリアの選択肢が広がる
弁理士資格を取得すれば、企業の知財部、特許事務所、場合によっては独立開業まで多様なキャリアパスがあります。
特に理系のバックグラウンドがある人は、即戦力として評価されやすく、転職市場でも高い需要があります。
勉強のポイント
- 全体像をつかむこと
- 理系の論理的思考を活かすこと
- 苦手な法律は焦らず基礎から固めること
- 過去問演習を地道に続けること
このようなポイントを押さえつつ、無理なく継続することが成功のカギです。
私のブログでは、これからも理系出身者が弁理士を目指す上で役立つ情報を発信していきます。
疑問や質問があればいつでもお気軽にコメントくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。