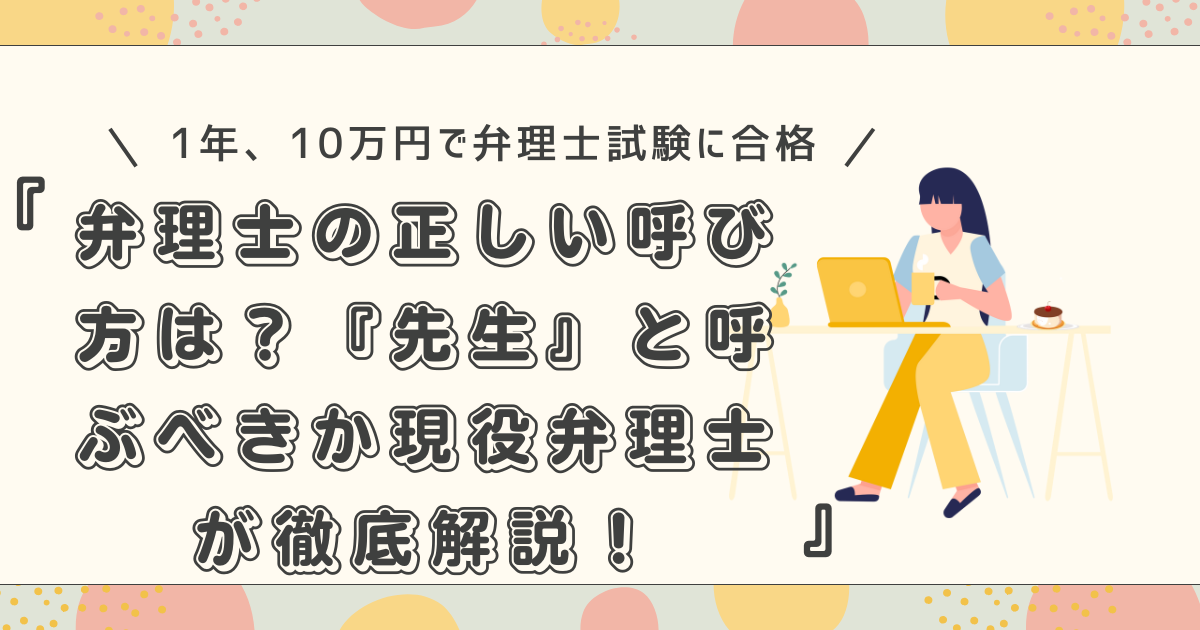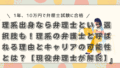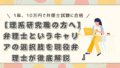このブログにご訪問いただきありがとうございます。サイト運営者のcoffeeと申します。
私は理系大学院を卒業後、メーカーの開発職を経て知財部に異動し、令和3年度の弁理士試験に合格しました。現在は現役の弁理士として日々の業務に取り組んでいます。
今回は、「弁理士の呼び方」について深掘りします。特に「弁理士を『先生』と呼ぶべきか」という疑問は、知財業界だけでなく一般社会でもよく話題になります。
実際のところ、弁理士の呼び方には明確なルールがあるわけではありませんが、業界内外でのマナーや慣習があります。
この記事では、その背景や現場での呼称事情、また私自身の経験を踏まえた見解をお伝えします。これから弁理士を目指す方や知財に興味がある方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
弁理士の呼び方にまつわる疑問
法律の専門家として知られる弁護士や司法書士は、一般的に「先生」と呼ばれます。
しかし弁理士に対しては「先生」と呼ぶべきか、あるいは単に「弁理士さん」や「○○さん」と呼ぶのが適切なのか、迷うこともあるでしょう。
この違いは、弁理士の歴史的な社会的地位や実際の業務形態、また業界慣習に関係しています。
次章でそのあたりを詳しく解説していきます。
私が弁理士を目指したきっかけと経験
私は2018年に理系大学院を卒業し、メーカーの開発職に就きました。
2020年10月に弁理士試験の勉強をスタートし、翌年には知財部に異動。2022年1月に弁理士試験に合格しました。
会社の研修で受けた特許研修の講師が弁理士資格を持つ知財部の方で、その仕事の専門性とやりがいに惹かれたのがきっかけです。
理系バックグラウンドを活かせるキャリアとして弁理士を選び、働きながら最短ルートで合格しました。
このブログでは私の体験談を交えつつ、弁理士の呼び方の話題も含め、知財業界のリアルを発信しています。
弁理士の呼び方の歴史的背景と社会的立場
弁理士は知的財産権の専門家として、特許庁に登録された国家資格者です。
弁理士制度自体は1959年に創設され、約60年以上の歴史があります。
一方、弁護士は江戸時代からの法曹の伝統があり、「先生」と呼ばれる文化が根付いています。司法書士や税理士なども同様に「先生」と呼ばれることが一般的です。
しかし弁理士の場合、法律に関わる専門職ではあるものの、裁判業務は行わず、知財の出願や権利化支援が主な仕事です。そのため、社会的認知度や呼称文化はまだ発展途上とも言えます。
なぜ弁護士は「先生」と呼ばれ、弁理士は呼ばれにくいのか?
これは社会的認知と業務の性質によるものです。
弁護士は「法廷での代理人」としての役割が明確であり、法律相談の代表格として市民に広く知られています。
対して弁理士は主に技術や発明の専門家として裏方で活躍し、一般の方にはまだなじみが薄いことが理由の一つです。
また、弁理士の多くは企業の知財部門や特許事務所で働いており、社内や取引先など限られたコミュニティで呼ばれ方が固定されやすいという事情もあります。
まとめると
- 弁理士は法曹ではないが法律資格者である
- 裁判業務は行わないため「先生」文化は薄い
- 社会認知度が弁護士ほど高くないため呼称が多様化している
- 業務環境や関係性により呼び方は異なる
働きながら弁理士試験を目指すなら「studyingの弁理士講座」がおすすめ
弁理士試験は難関資格として知られており、効率的な学習計画と質の高い教材が合格の鍵です。
私自身も働きながら合格を目指す中で、オンラインでいつでもどこでも学習できる「studyingの弁理士講座」に大変助けられました。
理系出身者にもわかりやすい解説と豊富な問題演習が特徴で、独学に不安な方や時間が限られている方に最適です。
興味がある方は無料体験も可能なので、まずは公式サイトをチェックしてみてください。
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)現場での弁理士の呼び方とマナー
実務の場では、弁理士の呼び方は職場の文化や関係性によって異なります。
1. 企業知財部や特許事務所の場合
多くの場合、名字+「さん」や役職名で呼ばれることが多いです。
例えば「山田さん」や「山田主任」といった呼び方が一般的です。
特に社内の知財部では、フラットな呼び方が多く、堅苦しく「先生」と呼ぶことは稀です。
2. 取引先やクライアントとの関係
外部の弁理士事務所の方を敬意を込めて「先生」と呼ぶケースもあります。
ただし、これも地域や業界によって異なり、必ずしも必須ではありません。
相手の希望や社内ルールを尊重することが大切です。
3. セミナーや講演会など公の場
講師として登壇する場合は、「先生」と呼ばれることが多いですが、弁理士の肩書きと名前を併用することも一般的です。
呼び方で迷ったらどうする?
- 基本は相手の希望に合わせること
- 会社や事務所の慣習を確認すること
- 敬意は言葉遣いや態度で示すことが何より重要
このように柔軟に対応するのが現場のマナーと言えます。
知財業界でのキャリアアップや転職を考えるなら「リーガルジョブボード」が便利
知財・法律業界に特化した求人情報を探すなら、「リーガルジョブボード」が非常に役立ちます。
私自身もキャリアの節目で情報収集に活用し、業界の求人動向を把握できました。
豊富な求人案件と専門スタッフによるサポートで、知財部や特許事務所での転職活動を効率的に進められます。
ご興味のある方は公式サイトをチェックしてみてください。
知財系の求人に強く、弁理士や知財部の転職に特化したキャリアアドバイザーが在籍しています。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
弁理士を目指すなら最初の一冊に最適な参考書
弁理士を目指す方にとって、最初の壁は「法律への苦手意識」ではないでしょうか。
理系出身である私も最初はまったくの法律初心者でした。特許法や実用新案法といった聞き慣れない言葉の連続に、正直圧倒された記憶があります。
そんなときに出会って本当に役立ったのがこちらの一冊。
📘 『弁理士スタートアップテキスト』
この書籍は、弁理士試験の全体像をやさしく、図解を交えて解説しており、初学者にとって最適な入門書です。
- 法律が苦手でもスッと読める
- 実際の試験制度や試験範囲を把握できる
- 学習開始前に「地図」として使える
という点が魅力で、知識ゼロの状態からでも不安なくスタートできます。
私はこの本で「弁理士ってどんな資格なのか」「何を勉強すべきなのか」を具体的にイメージできました。
これから学習を始める方には、間違いなく最初の1冊としておすすめです。
👉 詳しくは『弁理士試験に必要な参考書を解説した記事』でも紹介しています。
呼び方に関するよくある誤解とQ&A
最後に、「弁理士の呼び方」についてよくある誤解や、SNSや現場で実際にあった質問にQ&A形式でお答えします。
Q1:弁理士は絶対に「先生」と呼ばないと失礼?
A:いいえ。状況や職場文化に応じて「さん」付けでも問題ありません。
むしろ事務所や社内では「さん」「役職名」の方が自然なケースも多いです。
Q2:名刺交換のとき、どう呼びかけるのが適切?
A:最初は「○○先生」と呼び、相手が訂正したらそれに従うのが無難です。
ビジネスマナーとしての柔軟性が大切です。
Q3:「先生」と呼ばれることに違和感を持つ弁理士もいる?
A:はい、います。
特に社内の立場や年齢が若い場合、「先生」と呼ばれるのはむしろ気恥ずかしいと感じる方も。私も最初は「いや、先生じゃないので……」と否定していました(笑)。
【まとめ】弁理士の「先生」呼びは状況次第。相手への敬意がすべて
この記事では、「弁理士 呼び方 先生」というキーワードを軸に、呼称の実情、社会的背景、現場でのマナー、さらに勉強・転職・参考書情報まで幅広く解説してきました。
改めて要点を整理すると…
- 弁理士を「先生」と呼ぶかは相手との関係性と職場文化によりけり
- 呼び方に絶対のルールはなく、相手の意向に合わせるのが最も礼儀正しい
- 呼称の背景には、弁護士との違いや社会的認知度の差がある
- 初学者には『弁理士スタートアップテキスト』での基礎固めが非常におすすめ
- キャリアアップにはリーガルジョブボードのような専門転職サイトを活用
- 働きながら合格を目指すなら「studying」のオンライン講座が効率的
おまけ:知財部でのリアルな働き方が気になる方へ
弁理士資格を取得したあと、多くの方が目指す進路の一つが企業の知財部です。
ですが「実際に知財部で働くってどんな感じ?」「特許の仕事ってどうやるの?」といった疑問を持たれる方も多いと思います。
そんな方にこそおすすめなのがこちらの書籍👇
📗 『知財部という仕事』
実際の知財部業務の流れ、社内での役割、特許戦略などを、現場目線で丁寧に解説した一冊。
特許や商標などの理論だけでなく、「実務としての知財」に関心がある方に最適です。