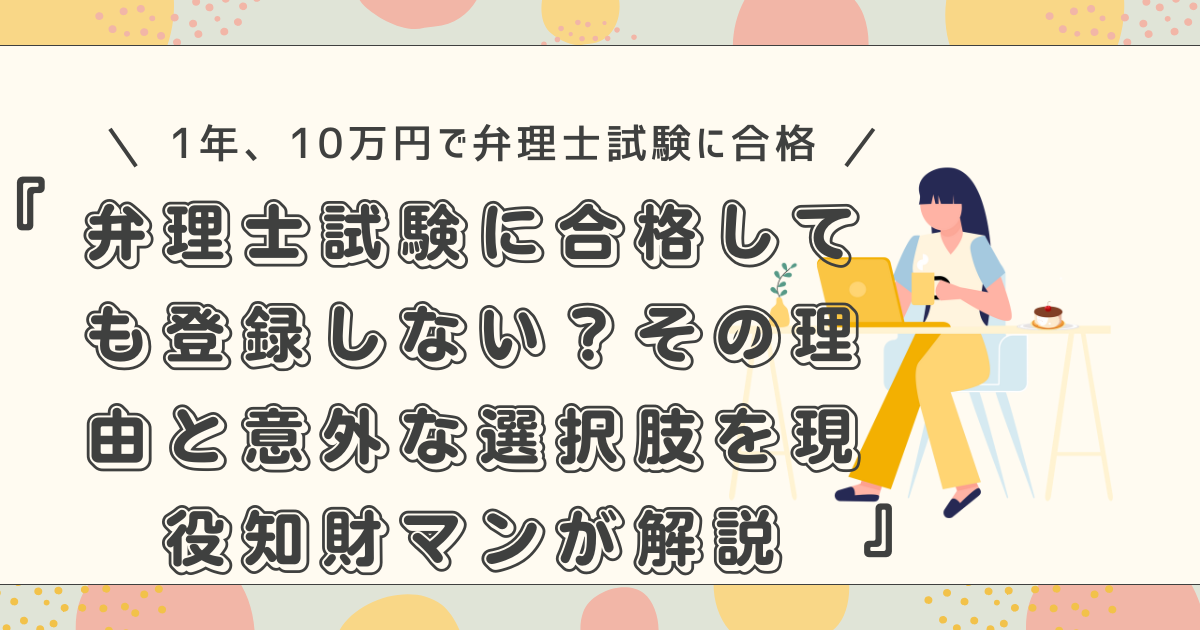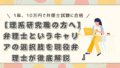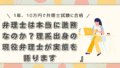弁理士試験に合格しても登録しない?
こんにちは。ブログ運営者のcoffeeです。
私は2022年に弁理士試験に合格し、現在はメーカーの知財部で働いています。
この記事では、「弁理士試験に合格したのに登録しない人がいるのはなぜか?」というテーマについて、実体験と周囲の事例を交えながら解説していきます。
登録しない人が意外と多い?
弁理士試験は合格率7〜9%前後の難関国家資格。長期間の勉強の末に合格したにも関わらず、「登録しない」という選択を取る人が実は少なくないのです。私の周囲でも、合格後しばらくは登録しなかった人が複数います。
「え?せっかく合格したのに登録しないの?もったいなくない?」
そう思う方が大半でしょう。ですが、弁理士として登録しない=失敗というわけではありません。そこには、明確な理由が存在するのです。
登録しない理由①:費用負担が重い
まず最初にネックとなるのが、登録費用と維持費用の高さです。
■ 登録にかかる初期費用
- 登録免許税:60,000円
- 弁理士会登録手数料:42,000円
- 登録免許状の交付:約3,500円
合計:約105,500円〜110,000円
■ 年会費など維持費用(年間)
- 日本弁理士会年会費:6万円超(初年度は日割り)
つまり、初年度だけで16〜17万円ほどのコストが発生します。
この費用を「今すぐ払っても使う予定がない」と感じれば、登録を先送りするのは合理的な判断とも言えます。
登録しない理由②:企業内知財部で登録は必須ではない
特許事務所と違い、企業の知財部では弁理士登録が必須でない場合がほとんどです。
私自身、弁理士試験に合格後もすぐには登録せず、知財部内で経験を積むことを優先しました。企業では、弁理士登録がなくても出願・中間処理・契約対応などの業務がこなせます。
そのため、
- 登録してもしなくても仕事内容に変化がない
- 上司や同僚に未登録の合格者が多い
という環境だと、「まあ後でいいか」と考える人も出てきます。
むしろ、一定の実務経験を積んでから登録する方が、自分のキャリアプランに沿った動きができるとも言えます。
登録しない理由③:転職や独立を見据えた“保留”
一方で、将来的に転職や独立を視野に入れている人は、「そのタイミングで登録すれば良い」と考えてあえて保留しているケースも多くあります。
たとえば、
- 転職先で「登録弁理士であること」が歓迎される場合
- 副業や個人受任をしたい場合
- 独立・開業を予定している場合
このような方々にとっては、登録の「タイミング」が重要になります。
登録しない人も弁理士試験合格を活かせる!
ここで強調したいのは、**「弁理士として登録していなくても、合格という実績は大きな武器になる」**という点です。
たとえば、企業内で知財業務に取り組む上では、弁理士試験に合格しているだけで以下のような評価を得られます。
- 専門性の証明になる
- 研修講師や育成担当として重宝される
- 昇進や評価において優遇されるケースも
実際、私も登録前から社内での信頼や裁量が大きくなったことを感じました。
また、将来的に知財部から転職を考えている方にも、「弁理士試験合格」の実績は非常に強力なアピール材料になります。
登録しないまま弁理士資格を活かす方法とは?
弁理士として登録しなくても、「試験合格」という事実自体が強力なキャリアの武器になることは前述しました。ここでは、登録なしでも有効に活用できる方法を具体的にご紹介します。
方法①:企業内での知財スペシャリストとしての地位確立
知財部では、弁理士登録の有無よりも、実務経験×資格合格実績の方が評価されやすいことがあります。たとえば以下のような場面です。
- 特許明細書のドラフトレビューで上司からの信頼が高まる
- 弁理士試験の勉強内容を活かして契約書や拒絶理由通知の対応がスムーズになる
- 社内研修の講師役として登壇する機会が増える
こうした実績は、昇進や他部門からの引き合いにもつながりやすくなります。
方法②:転職市場での強力なアピール材料になる
私が知財部で過ごす中でも痛感したのは、弁理士試験合格者=超希少人材だということ。とくに理系バックグラウンドを持ちながら知財の専門性もある人材は、企業からの引き合いが非常に強いです。
実際、弁理士試験合格だけで内定が出る求人も多数存在しています。そうした求人に出会うには、業界特化の転職サイトの利用が効率的です。具体的な転職方法については後述します。
方法③:勉強ノウハウや知財の知見を副業・発信に活かす
登録をしない=仕事ができない、ではありません。むしろ、
- ブログやYouTubeで勉強法を発信する
- 試験勉強の個別指導を副業で行う
- 企業研修の講師を務める
といった選択肢も生まれてきます。最近では、勉強系コンテンツや知財の入門解説コンテンツは需要が高く、「弁理士試験合格」という信頼性ある肩書が強く効いてきます。
弁理士試験は独学だけでは非効率。最短合格を目指すなら?
弁理士試験に合格すれば登録しなくてもキャリア上の価値は大きい。
──とはいえ、合格するまでのハードルが極めて高いのも事実です。
私自身も、働きながら試験勉強をしていたので、独学で効率的に進めるのはほぼ不可能でした。そんな中で出会って最も効果的だったのが、スタディング弁理士講座です。
【おすすめ講座紹介】スタディング弁理士講座
スタディングは、スキマ時間を活用してスマホ1台で学べる超効率特化型の講座。特にこんな方におすすめです:
- フルタイムで働いていて、机に向かう時間が取りにくい方
- 初学者で、何から手を付けていいか分からない方
- 法律の勉強に苦手意識がある理系出身者
私は以下のような流れでスタディングを活用していました:
| 時間帯 | 活用方法 |
|---|---|
| 通勤中 | 音声講座で基礎理解 |
| 昼休み | スマホで過去問演習 |
| 就寝前 | 理解が浅い論点の動画視聴 |
結果として、働きながらでも1年半で合格ラインまで到達することができました。
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)試験合格後の登録・非登録は「戦略次第」
重要なのは、「合格したからすぐ登録する」「しないと損」という思考ではなく、「今のキャリアにおいて登録が必要かどうか」を判断することです。
- 企業での昇進が狙えるなら、あえて登録せずに費用を抑える
- 転職や副業・独立の準備が整ったタイミングで登録する
- 登録せずに副業や情報発信で実績を作る
このように、弁理士資格は自分の戦略に合わせて使える柔軟な国家資格でもあるのです。
登録せずに転職したい!知財系転職市場のリアル
弁理士資格を取得しても、すぐに登録しないまま転職活動をする方は一定数存在します。私自身も、知財部で働きながら周囲の転職事例を見てきましたが、登録なしでも転職は可能です。
ただし、注意すべき点もいくつか存在します。
登録なしの転職活動で注意すべき3つのポイント
① 求人内容に「登録弁理士必須」と書かれていないかをチェック
事務所によっては「弁理士登録者のみ応募可」と明示しているところもあります。
企業知財部の求人では比較的柔軟な傾向がありますが、特許事務所の実務担当ポジションでは登録の有無がシビアに見られることもあります。
②「登録予定」か「登録の意思なし」かは明確にしておく
面接などで聞かれる可能性が高いため、「今は登録していませんが、転職後に登録予定です」「現時点では登録は考えていません」など、一貫した理由と計画性を持って答えられるようにしておくことが重要です。
③ 書類上は「弁理士試験合格」と正しく記載する
登録していない以上、「弁理士」とは名乗れません。履歴書・職務経歴書にも「弁理士試験合格」と明記するようにしましょう。
知財系転職は“情報戦”。専門エージェントで非公開求人を狙う
知財業界の求人は、他業界に比べて公開情報が少なく、専門性が高いのが特徴です。
特に、
- 弁理士試験合格者向けの非公開求人
- 登録が不要な企業知財部の好待遇ポジション
- 柔軟な働き方(リモート・フレックス)が可能な事務所
などは、一般的な転職サイトには掲載されていないことが多いです。
そこで活用したいのが、知財・法務専門の転職エージェントです。
【おすすめ転職支援】リーガルジョブボード
リーガルジョブボードは、知財・法務・士業に特化した転職エージェントで、
「弁理士試験合格済・未登録者向けの求人」や、
「企業内知財部の年収アップ求人」が豊富に掲載されています。
こんな方におすすめ:
- 登録なしで転職活動をしたい方
- 自分の市場価値を知りたい方
- 弁理士登録に迷いがあり、今後のキャリアを相談したい方
エージェントとの面談では、現状のスキルや資格取得状況に応じて、「登録すべきか否か」も含めて相談できます。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
登録しない選択も“戦略”。転職や副業でキャリアを築く道
ここまで解説してきた通り、弁理士登録をしないことは「戦略的選択」です。
登録しなくても、転職で条件を良くしたり、社内で評価を得たり、副業や情報発信で収入を得るなど、柔軟なキャリア形成が可能になります。
ただし、そのためには自分の方向性をしっかり見定めた上での準備が欠かせません。
まとめ:弁理士登録は「今すぐ」ではなくてもいい。自分のキャリアに合った選択を
弁理士試験に合格したら、すぐに登録しなければいけない──。
そんな思い込みにとらわれる必要はありません。実際には、多くの人が「登録しない」という選択をしていますし、それがキャリアの停滞を意味するわけでもありません。
むしろ、以下のような考え方のもとで、自分の状況に応じて柔軟に判断することこそが大切です。
登録しない選択が有効な場面
- 登録費用・年会費の負担が大きく感じられる場合
- 企業知財部で登録せずとも実務をこなせる環境にいる場合
- 登録タイミングを戦略的に考えたい(転職・独立・副業など)場合
登録していなくても弁理士試験合格は価値ある実績
- 企業内での専門性の証明になる
- 昇進や評価の材料になることも
- 転職市場での希少性・評価が高い
- 情報発信や副業に活かせる
大切なのは、「試験合格=ゴール」ではないということ
私自身、試験に合格してからも「どのタイミングで登録するのがベストか」を考え続けてきました。そして、今後のキャリアパスやライフプランに応じて、登録のタイミングを柔軟に選ぶことの大切さを日々実感しています。
「登録していないから自分は弁理士として未完成だ」
そんな風に感じる必要はまったくありません。大切なのは、資格をどのように自分のキャリアに組み込んでいくかです。
今後もこのブログでは、弁理士試験や知財業界、転職や学習法について、実体験ベースで記事を発信していきます。
ご覧いただきありがとうございました。