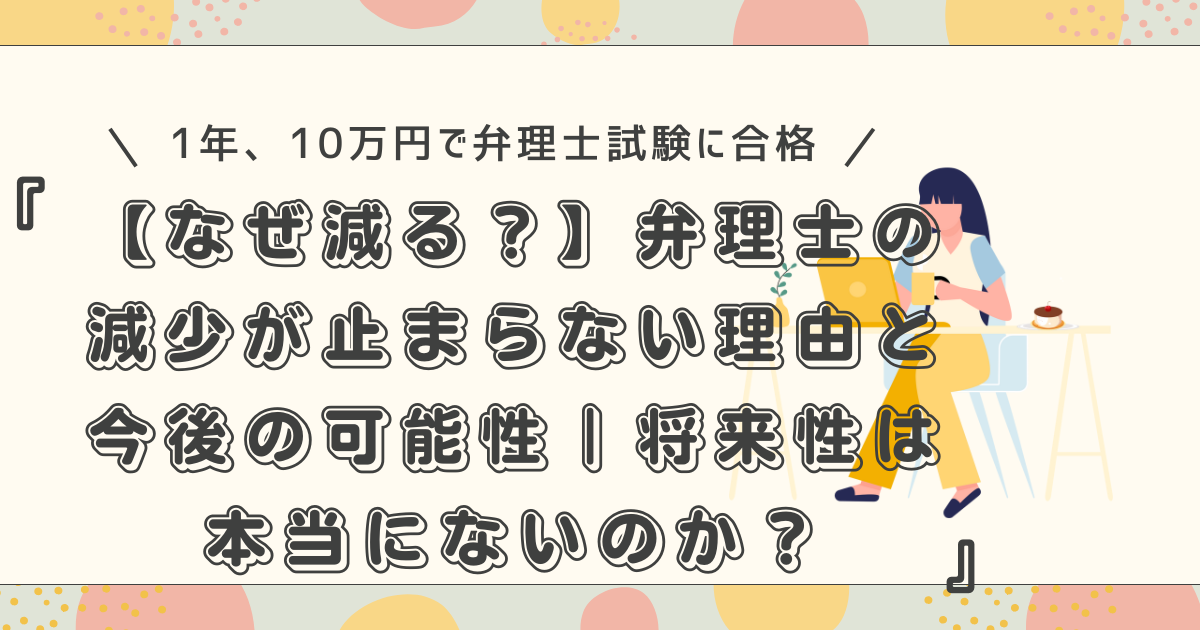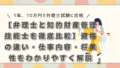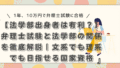なぜ今「弁理士の減少」が話題になるのか?
近年、「弁理士の数が減っている」「将来性がないのではないか」といった話題を目にする機会が増えてきました。
実際、弁理士試験の出願者数や合格者数は年々減少傾向にあり、特許庁や知財業界の関係者も頭を悩ませています。
私は理系出身で、メーカーの開発職から知財部に異動し、その後弁理士試験に合格しました。現在は実務を行う傍ら、このブログで知財や弁理士試験に関する情報を発信していますが、肌感覚としても「弁理士を目指す人が減っている」ことを強く感じます。
しかし、これは単なる資格人気の衰退だけではなく、社会構造や業界の変化が複雑に絡み合っている現象です。
この記事では「なぜ弁理士が減っているのか」「将来性はあるのか」「これから目指す価値はあるのか」といった点について、実体験を交えながら深掘りしていきます。
1章:実際に弁理士は減っているのか?数字で見る現実
まず本当に「弁理士が減っている」のか、客観的なデータから見てみましょう。
● 登録弁理士数は増えているが、現役は減っている?
日本弁理士会の公表しているデータによれば、登録弁理士の総数は一見して微増または横ばいに見えます。しかし、これは「登録はしているが、実際には業務を行っていない人」も含まれており、実務に従事する弁理士数は減少傾向にあると考えられます。
とくに都市部以外の特許事務所では、求人を出してもなかなか人が来ないという声もあります。
このように、表面的な人数と実態には乖離があるのです。
● 弁理士試験の出願者数は年々減少
もっと顕著なのが弁理士試験の出願者数です。
| 年度 | 出願者数 |
|---|---|
| 2010年 | 約9,000人 |
| 2015年 | 約5,500人 |
| 2020年 | 約3,500人 |
| 2024年 | 約2,500人(推定) |
わずか10年ちょっとで出願者数が3分の1以下に。
「国家資格」としては異例の落ち込みとも言えます。
● 合格者数の調整が行われている?
近年では試験の合格者数を一定以上に保つ方針があるとも言われていますが、それでも受験者数が少ないため、全体の供給が追いつかないという声もあります。
第2章:なぜ弁理士が減っているのか?主な理由を解説
弁理士が減少している背景には、複数の要因が絡んでいます。ここでは代表的な理由を解説していきます。
理由①:試験の難易度が高すぎる
弁理士試験は、日本の国家資格の中でもトップクラスの難関試験です。
法律の専門知識はもちろん、論文試験や口述試験といった複数のハードルを越える必要があります。
理系出身者にとって、法律科目はとくに大きな壁になります。私自身も、**最初は「用語の意味すら分からない」**というところからのスタートでした。
しかし、近年ではオンライン教材なども整備されており、効率的な学習が可能になっているのも事実です。
私が合格した際に活用したのが、Studying(スタディング)弁理士講座でした。
スキマ時間を有効活用できる動画教材に加え、過去問演習や論文対策までスマホ一つで学習できたのが大きかったです。
▼私が実際に使って合格した講座はこちらの記事で詳しくレビューしています:
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)理由②:知財業界の将来に不安を感じる人が増えている
近年のAI技術の発展やグローバル化の流れのなかで、特許業務の一部が自動化・効率化されつつあります。
「AIで特許明細書を書く時代が来るのでは?」
「いずれ仕事がなくなるのでは?」
という漠然とした不安が、特に若手層の間で広がっています。
また、企業の研究開発投資が減っているケースも多く、出願件数そのものが横ばい〜微減の傾向にあることも、業界全体の将来性を不安視する要因の一つです。
ただし、このような変化は弁理士の仕事が完全になくなるということではなく、求められるスキルの変化と捉えるべきです。
たとえば「外国出願対応」「企業内知財戦略の立案」「契約・係争対応」といった高度な業務は今後も人間の役割として残るでしょう。
理由③:弁理士資格だけでのキャリアアップが難しいと感じる人が増えた
以前は「弁理士資格さえ取れば、食いっぱぐれはない」と言われていた時代がありました。
しかし現在では、資格を取ってもキャリアアップにつながらない人もいるという現実があります。
■ 資格はあっても、実務経験がないと厳しい
■ 特許事務所の報酬水準が昔ほど高くない
■ 企業知財部でも弁理士資格が昇進の条件とは限らない
このような事情から、「弁理士を目指すメリットが少ない」と判断してしまう人が増えているのです。
しかし、これは裏を返せば「資格を活かせる場所を自分で選びにいけば、十分に活躍できる」ということでもあります。
実際、弁理士資格を活かして年収アップを実現している人も多数存在します。
実際に弁理士資格を取得し、転職で年収を200万円以上アップさせた事例を紹介した記事もあります。
キャリアの可能性を具体的にイメージしたい方は、こちらもご覧ください。
第3章:弁理士減少時代だからこそ、逆に「狙い目」である理由
ここまで読むと、「やっぱり弁理士は将来性ないのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
しかし実は、今こそ弁理士を目指すべきタイミングだという見方もあります。
● 市場全体が縮小しているのではなく、人材の供給が減っている
弁理士が減っているのは、試験が難しすぎたり、キャリア設計の不安が先行していることが主な原因です。
一方で、企業の知財ニーズは依然として存在しており、特に経験者や資格保持者への求人はむしろ増えているのが現実です。
実際、知財職専門の転職支援サービス「リーガルジョブボード」では、弁理士資格者向けの非公開求人も数多く取り扱っています。
初めて知財業界にチャレンジする方から、経験豊富なベテランまで幅広い案件があり、キャリアの幅を広げたい人には最適です。
→ 詳しくは リーガルジョブボード公式サイト をチェックしてみてください。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
● 競争が減っている=実力次第で活躍の場が広がる
出願者数が減少している今は、ライバルが少ないボーナスタイムとも言えます。
過去には出願者1万人超だった時代と比べて、合格者1人あたりの市場価値も相対的に高まっているのです。
● 若手弁理士の価値が急上昇中
弁理士の高齢化も進んでおり、特に40代以下の若手層が希少な存在となりつつあります。
企業の知財部や特許事務所では、長期的な組織運営の観点から「若手の弁理士を確保したい」というニーズが高まっているのです。
実際、私の周囲でも「弁理士資格を取ってから転職活動をしたら一気に選択肢が増えた」という声は非常に多く聞かれます。
これはまさに、供給が減っているからこそ、価値が上がっている証拠です。
また、弁理士は専門職であるため、年齢や学歴よりもスキルや実務経験のほうが重視される世界です。年齢を気にせずキャリアを築きたい方にも向いている職業と言えるでしょう。
第4章:弁理士として活躍するには「資格+実務知識」が重要
ここまでの流れから、「弁理士資格を取得すれば可能性は広がる」ということが伝わったかと思います。
しかし現実には、資格だけで活躍できるわけではなく、実務的な知識や知財業界の理解も重要になってきます。
たとえば以下のようなスキルが、企業や事務所から高く評価されます。
- 特許明細書の作成スキル(特許技術者との協働力)
- 係争・無効審判などの対応経験
- 外国出願(PCT/パリルート)の知識
- ビジネス視点での特許戦略立案スキル
こういったスキルは、実際に働きながら身につけることが多いですが、基礎力を事前に固めておくことで実務にもスムーズに入っていけます。
● 初学者・若手向けに最適な書籍:『弁理士スタートアップテキスト』
もしこれから弁理士試験を受けようと考えている方、あるいは知財に携わり始めたばかりの方には、まず全体像を丁寧に解説してくれる入門書を手に取ることをおすすめします。
私が特に推したいのは『弁理士スタートアップテキスト』です。
弁理士試験の出題範囲を網羅しつつ、法律に苦手意識がある人でも読みやすい構成になっており、「そもそも弁理士ってどんな仕事をするの?」という疑問にやさしく答えてくれます。
第5章:知財部というキャリアの選択肢もある
弁理士のキャリアと聞くと「特許事務所で働く」というイメージが強いかもしれませんが、近年では企業知財部で活躍する弁理士も非常に増えています。
実際に私も開発職から知財部に異動して感じたのは、知財部こそが「技術×ビジネス×法務」のすべてに関われる非常に戦略的な部署であるということです。
企業の知財部では、弁理士資格を持っていることで次のようなメリットがあります。
- 外部弁理士との折衝で説得力を持てる
- 発明者とのやり取りで信頼されやすい
- 社内での地位向上や昇進に有利
- 海外出願や係争案件でのリーダー的役割を担える
これらの理由から、社内で弁理士資格を奨励している企業も増えているのが実情です。
また、知財部というフィールドは、技術と法務の両面に精通している人材が非常に重宝される場です。
理系出身の方にとって、まさにスキルを最大限に活かせる環境とも言えるでしょう。
第6章:弁理士になるために今どう動くべきか?
ここまで読んで「やっぱり弁理士、狙ってみたいかも」と感じた方もいるのではないでしょうか?
その気持ちは間違っていません。
弁理士が減っている今だからこそ、資格取得の価値はむしろ上がっていると断言できます。
ただし、弁理士試験は独学では非常に厳しいため、正しい教材と戦略が必須です。
先述のように私自身は「Studying(スタディング)」を使って合格しましたが、これは「最短距離で受かる」ために最適な選択肢でした。
理由としては:
- 忙しい社会人でもスキマ時間で学べる動画教材
- スマホひとつでインプット・アウトプットが完結
- 過去問の解説が体系的で、繰り返し復習しやすい
- 論文・口述対策まで網羅している
こういった効率的な学習環境が整っていれば、働きながらでも十分に合格を目指すことが可能です。
第7章:弁理士減少の裏にある「チャンス」を掴むには?
最後に、この記事で最も伝えたいことをまとめます。
確かに、弁理士の受験者数は減少しています。
それに伴い、「将来性がないのでは」とネガティブに捉える声もあるのが現実です。
しかし、減っているのはあくまでも供給側(受験者・若手人材)であり、需要側(企業・特許事務所)は依然として人材を求めているのです。
つまり今は、少数精鋭が活躍しやすい「穴場の時代」とも言えるでしょう。
資格を持っているだけで引き合いがあり、転職市場でも好条件のオファーを受けやすいタイミングです。
そして、これから目指す方には以下のような選択肢があります:
- Studyingを使って効率的に試験突破を狙う
- 書籍でまず全体像をつかみ、着実に進める
- キャリアとして知財部も視野に入れる
- 資格取得後は、リーガルジョブボード等で転職を検討
まとめ:弁理士が減る今だからこそ、価値がある
弁理士は減っています。
でもそれは、「なる人が減っている」というだけで、「求められていない」という意味ではありません。
むしろ、これからの弁理士には、より広い活躍のチャンスがあると私は思っています。
特許制度の高度化、国際出願の増加、そしてAIやITとの融合。これらはすべて、知財の専門家にとっての追い風です。
だからこそ、もしあなたが今「弁理士ってどうなんだろう」と思っているなら、
その問いの答えはこうです。
「目指す価値は、むしろ今の方がある。」
これが私の実体験からの結論です。