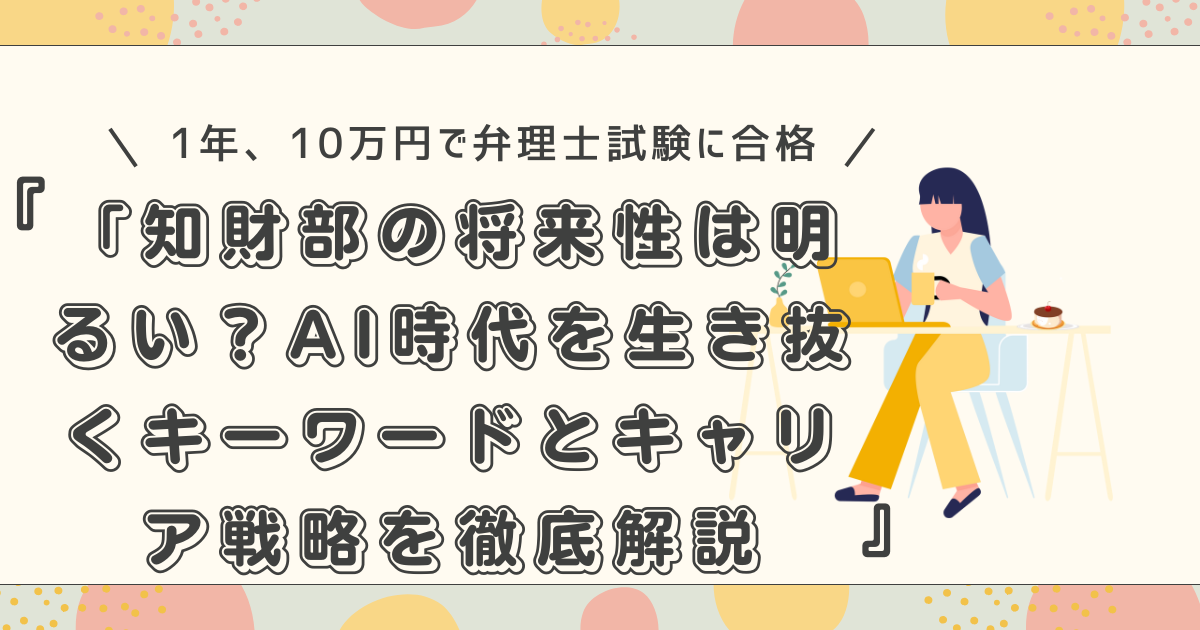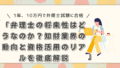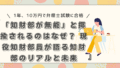このブログにご訪問いただきありがとうございます。サイト運営者のcoffeeと申します。
略歴
- 2018年 理系大学院卒業後メーカー開発職に就職
- 2020年10月弁理士試験勉強開始
- 2021年 同メーカー知財部に異動
- 2022年1月 弁理士試験合格
- 2022年5月 ブログ開始
- 2024年6月 IT パスポート合格
- 2024年8月 基本情報技術者試験合格
- 2024年12月 応用情報技術者試験合格
弁理士試験を受けようと思ったきっかけは、会社の研修でたまたま受けた特許研修で、講師の方が弁理士資格を持った知財部の方だったことです。その話を聞いて、自分の進みたいキャリアと理系としてのバックグラウンドを総合的に考慮した結果、弁理士資格を取得して知財業務に携わりたいと思い、決断しました。私は令和3年度弁理士試験に、働きながら最短・最安で合格した自負があります。
もちろん、何か特殊な能力があったわけではなく、どうすれば合格できるかを毎日考え、効率的に勉強した結果、最短ルートで進むことができたのだと思います。このブログが、資格に興味があって迷っている人、弁理士にどうしてもなりたい人の助けに少しでもなれば幸いです。具体的には、勉強方法や実際の知財の仕事内容をシェアしていきたいです。さらに、知財業界自体が今より盛り上がっていくことに期待して書き続けます。
近年、AI技術の発展は目覚ましく、多くの専門職がその影響を避けられないと言われています。知的財産(知財)を扱う部署である「知財部」も例外ではありません。「知財部の仕事はAIに奪われるのではないか」「将来性はあるのか」と不安に感じている人もいるかもしれません。
しかし、結論から言うと、知財部の将来性は非常に明るいと言えます。ただし、これまで通りの業務を漫然とこなすだけでは、その明るい未来を掴むことは難しいでしょう。これからの知財部員には、AI時代を生き抜くための新しいスキルや視点が求められます。この記事では、知財部の仕事がどう変化していくのかを掘り下げ、これから知財部で活躍するために必要なスキルやキャリアパスについて、具体的なアクションプランとともに解説していきます。知財部の将来に不安を感じている方、これから知財業界を目指したいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
知財部の役割はAI時代にどう変わるのか?
これまで知財部の中心的な仕事は、特許の権利化、つまり出願書類を作成したり、特許庁とのやり取りを行ったりすることでした。また、先行技術調査も重要な業務の一つで、自社の技術が他社の特許を侵害していないか、あるいは自社の出願前に類似技術がないかなどを調べる作業です。これらの業務は、多くの時間と専門知識を要するため、知財部員の主要な時間を占めていました。しかし、AIの進化により、これらの定型的な業務は徐々に自動化されていくと予測されています。
1. 定型業務はAIに代替され、より高度な業務が求められる
特許出願書類の作成や先行技術調査は、特定のルールに基づいて情報を整理・分析する作業です。AIは、大量のデータからパターンを認識し、効率的に処理する能力に長けています。そのため、近い将来、AIがこれらの作業を大幅に効率化し、人間が担う必要性は薄れていくでしょう。しかし、これは知財部の仕事がなくなることを意味しません。むしろ、AIが定型業務を肩代わりすることで、人間はより高度で戦略的な業務に集中できるようになるのです。具体的には、以下のような役割がより重要になってきます。
- 知財戦略の立案と実行
- 企業の経営戦略と連動した知財ポートフォリオを構築する
- 競合他社の知財動向を分析し、自社の競争優位性を高める
- 新規事業や技術開発の方向性を、知財の観点から助言する
- 発明発掘と社内コンサルティング
- 開発部門や事業部門に入り込み、発明の種を見つけ出す
- 発明者と対話しながら、特許として価値のあるアイデアを形にする
- 知財に関する社内教育や啓蒙活動を行う
- 知財の事業活用
- 保有する特許を他社にライセンス供与する
- 知財を担保にした資金調達を検討する
- M&Aにおける知財デューデリジェンスを実施する
このように、これからの知財部員は、「知財の専門家」であると同時に、「経営戦略のパートナー」としての役割を担うことが求められます。知財部の仕事についてもっと詳しく知りたい方は、「知財部の仕事について解説した記事」もぜひ参考にしてみてください。
2. AI時代の知財部員に求められる3つのスキル
AI時代を生き抜く知財部員になるためには、単に法律や技術の知識を持つだけでは不十分です。以下の3つのスキルを意識的に磨くことが重要になります。
- AIリテラシー:AIの仕組みを理解し、業務にどう活用できるかを考える力です。AIが出力した調査結果を鵜呑みにせず、その妥当性を判断する能力も含まれます。
- ビジネス・経営視点:知財を単なる「権利」として捉えるだけでなく、企業の利益にどう貢献するかを考える視点です。経営層や事業部門と対等に議論できるだけのビジネス知識が求められます。
- コミュニケーション能力:知財の専門家ではない開発者や経営層に、知財の重要性や戦略をわかりやすく伝える力です。知財を「守り」の道具としてだけでなく、「攻め」の武器として活用するためには、社内外の関係者との円滑なコミュニケーションが不可欠です。
知財部員として将来性を高める具体的なキャリアパス
知財部の将来性が明るいと言っても、具体的なキャリアパスが見えなければ不安は解消されないでしょう。ここでは、知財部員として将来性を高めるための2つのキャリアパスを紹介します。
キャリアパス1:企業内弁理士としてスペシャリストを目指す
知財部員としてキャリアを積む上で、弁理士資格の取得は非常に強力な武器になります。弁理士は、特許などの知的財産権に関する専門家として唯一、独占業務を行うことができる国家資格です。企業内で弁理士として働く「企業内弁理士」は、法律と技術の両方に精通した希少な存在として、社内で高い評価を得ることができます。特に、AI時代の知財部員に求められる「経営視点」や「戦略立案能力」は、弁理士試験の学習を通じて体系的に身につけることが可能です。
私自身、メーカーの開発職から知財部に異動し、働きながら弁理士試験に合格しました。弁理士資格は、知財部での業務の幅を広げるだけでなく、自身のキャリアの選択肢を大きく増やすことにもつながります。弁理士試験は難関ですが、働きながらでも十分に合格を目指せます。私も実際にそうでした。特に、近年はオンラインで完結する通信講座が充実しており、忙しい社会人でも自分のペースで学習を進められます。例えば、studyingの弁理士講座は、スマートフォンでスキマ時間に学習できるのが大きな魅力です。講義動画は1回あたりが短くまとまっており、通勤時間や休憩時間など、ちょっとした時間を有効活用できます。弁理士試験の勉強を始めるにあたって、まずは弁理士という仕事の全体像を把握することから始めるのがおすすめです。
私も活用したstudyingの弁理士講座は、働きながら合格を目指す方に特におすすめです。実際の合格体験記もご覧いただけます。
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)法律に苦手意識がある方でも読みやすい入門書として、『弁理士スタートアップテキスト』がおすすめです。やさしい言葉で試験の全体像を解説しており、私も最初にこの本で勉強を始めました。
キャリアパス2:知財の経験を活かし、他業界へのキャリアチェンジ
知財部での経験は、知財業界以外でも高く評価されます。特に、企業知財部で培った特許調査能力や契約書レビューの経験は、IT企業やコンサルティングファームなど、幅広い業界で重宝されるスキルです。例えば、知財の知識を持つことで、新規事業の立ち上げ時に知財リスクを事前に評価したり、M&Aの際に買収先企業の知財価値を正しく評価したりすることができます。また、特許事務所で実務経験を積んだ後、企業内弁理士として転職するキャリアパスも一般的です。もし知財の知識を活かしてキャリアアップや転職を検討しているなら、知財業界に特化した転職エージェントを利用するのがおすすめです。
リーガルジョブボードのようなエージェントは、知財業界の求人情報を豊富に扱っており、知財専門のキャリアアドバイザーがあなたのスキルや希望に合わせた転職先を紹介してくれます。弁理士資格を使って転職で大幅に年収を上げた人の記事も参考にしてみてください。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
AI時代を生き抜くための「知財戦略」と「人間力」
AIが進化しても、人間が担うべき役割は決してなくなりません。むしろ、AIは人間の創造性や戦略性を引き出すための強力なツールとなり得ます。これからの知財部員には、以下の2つを両立させることが求められます。
1. データ駆動型知財戦略の構築
AIは、膨大な特許情報や市場データから、これまで人間が見つけられなかったパターンやトレンドを抽出することができます。このAIの分析結果を基に、知財戦略を構築することが重要です。
- 競合分析の高度化:AIが特許ポートフォリオを分析し、競合他社の技術動向や開発ロードマップを予測する
- 技術トレンドの早期発見:AIが最新の論文やニュースを解析し、将来有望な技術分野を特定する
- 出願戦略の最適化:AIが過去の審査履歴から、特許が成立しやすいクレーム文言を提案する
このように、AIを「データ分析のパートナー」として活用することで、より精度の高い、データ駆動型の知財戦略を立案できるようになります。
2. 人間にしかできない「価値創造」
AIはあくまでツールであり、最終的に価値を創造するのは人間です。特に、以下のような業務は、AIには代替できない人間の強みが活かされる領域です。
- 発明者との対話:開発者の想いやアイデアを深く理解し、特許という形に落とし込む作業は、人間同士の信頼関係や共感が不可欠です。
- 経営層への提言:知財戦略を経営層にわかりやすく説明し、会社の方向性を議論する役割は、高度なコミュニケーション能力と人間力が求められます。
- 新たなビジネスモデルの創出:知財を単なる権利としてではなく、ビジネスモデル全体に組み込むような発想は、人間の創造性があってこそ生まれます。
知財の仕事についてもっと深く知りたい方は、『知財部という仕事』という書籍もおすすめです。知財部の業務の全体像や、企業における知財部の役割が具体的に描かれており、キャリアを考える上で非常に参考になります。
まとめ
知財部の将来性は、AIの進化によって仕事がなくなるどころか、より高度で戦略的な役割を担う部署へと進化していくため、非常に明るいと言えます。ただし、その未来を掴むためには、これまでの定型業務に終始するのではなく、AIをツールとして使いこなし、経営視点やコミュニケーション能力を磨いていくことが不可欠です。
特に、弁理士資格の取得は、知財の専門家としての市場価値を高めるだけでなく、自身のキャリアパスを大きく広げるための強力な武器になります。
働きながら資格取得を目指すのは大変ですが、オンライン講座や効率的な勉強法を駆使すれば、決して不可能ではありません。この記事が、あなたの知財部でのキャリアを考える上で、少しでも役立てば幸いです。