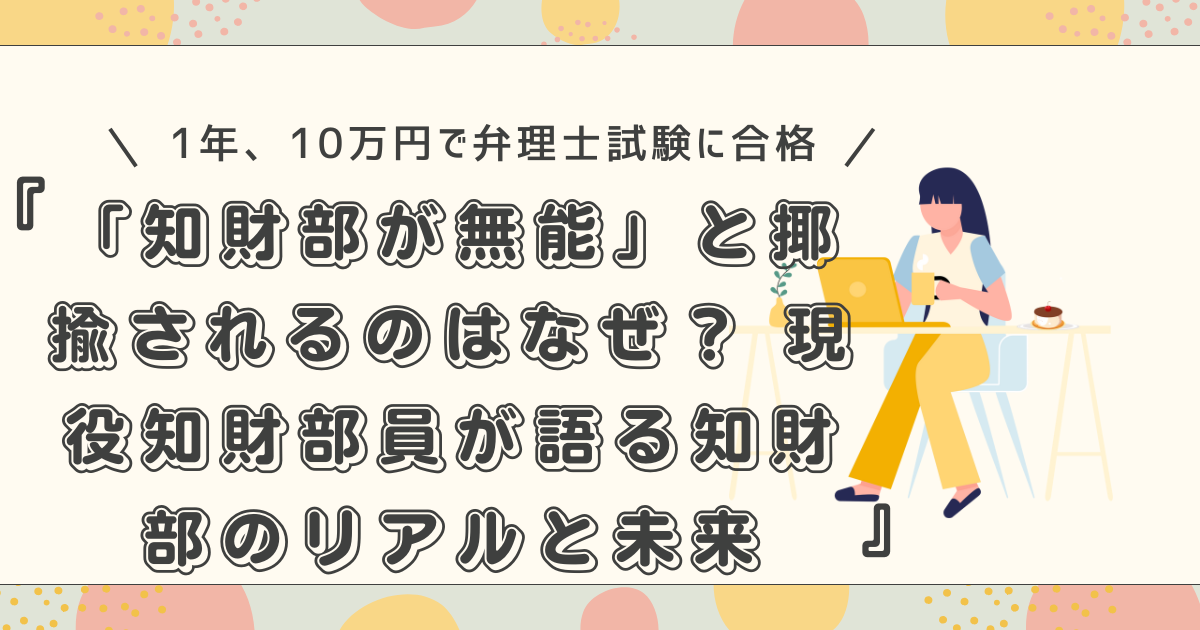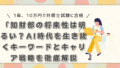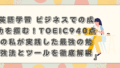はじめに:なぜ「知財部が無能」と言われるのか?
はじめまして。サイト運営者のcoffeeと申します。
このブログにご訪問いただきありがとうございます。 この記事を読んでいるあなたは、もしかしたら「知財部って何をしているのかわからない」「いつも特許を出せって言ってくるけど、実態が伴ってない」と感じているのかもしれません。あるいは、ネットで「知財部 無能」と検索して、このページにたどり着いたのかもしれませんね。
正直に言って、現役の知財部員である私も、この言葉を耳にするたびに胸が痛みます。しかし、この言葉が生まれる背景には、知財部と他部署との間に横たわる深い溝があるのも事実です。
この記事を読み終える頃には、知財部に対するあなたの印象はきっと変わっているはずです。そして、もしあなたが知財部員であれば、これから進むべき道が見えてくるかもしれません。
知財部員・coffeeの自己紹介
まずは簡単に私の自己紹介をさせてください。
私は2018年に理系大学院を卒業後、とあるメーカーの開発職として社会人生活をスタートさせました。日々研究開発に没頭する中で、会社の研修でたまたま受けた特許研修が、私の人生を大きく変えるきっかけとなりました。
その研修の講師は、なんと弁理士資格を持った知財部の方でした。その方のお話を聞くうちに、私は知財という分野に強く惹かれるようになりました。自分の進みたいキャリア、そして理系としてのバックグラウンドを総合的に考慮した結果、「弁理士資格を取得して、知財に関する業務をしてみたい!」と強く決心したのです。
そして、2020年10月から弁理士試験の勉強を開始。猛勉強の末、2021年には念願の知財部への異動が叶い、2022年1月には働きながら弁理士試験に合格することができました。
現在も知財部員として働きながら、このブログを通じて、知財の仕事の魅力や、弁理士試験の勉強方法などを発信しています。
知財部の仕事って何? なぜ誤解が生まれるのか
知財部が「無能」と言われる最大の原因は、その仕事内容が他部署から理解されにくいことにあります。
多くの部署は、製品開発や営業活動のように、目に見える成果を追求します。しかし、知財部の仕事は、企業の競争力を目に見えない形で守り、高めることにあります。
たとえば、
- 特許の出願・権利化
- 他社特許の調査・分析
- 商標権や著作権の管理
- 知財戦略の立案
といった業務は、どれも地味で、成果がすぐに現れるものではありません。
しかし、これらの業務がおろそかになれば、開発した製品が他社の特許を侵害してしまい、多額の賠償金を支払う羽目になったり、会社のブランドイメージが毀損されたりするリスクが高まります。
知財部が「無能」と言われる具体的な3つの理由
では、なぜ知財部は「無能」とまで言われてしまうのでしょうか。具体的な理由を3つに分けて解説します。
理由①:専門用語の壁とコミュニケーション不足
知財の世界には、特許法や商標法といった法律用語、そして出願手続に関する専門用語が溢れています。 「新規性」「進歩性」「先行技術調査」「拒絶理由通知」……。
私たちは日々これらの言葉を当然のように使っていますが、開発や営業の担当者からすれば、まるで外国語を聞いているようなものです。
知財部員が一方的に専門用語を使って説明し、他部署の担当者がそれを理解できない。このコミュニケーションの壁が、「知財部は何を言っているのかわからない」「役に立たない」という不信感を生み出してしまいます。
理由②:評価が難しい仕事内容
先ほども述べたように、知財部の仕事は「企業の競争力を守り高める」という目に見えにくい成果が中心です。
- 「他社特許の侵害を未然に防いだ」
- 「将来的に競合を排除できる特許を取得した」
これらは非常に価値のある成果ですが、定量的な評価が難しいため、他部署からは「何をやっているのかわからない」と思われがちです。
特に、特許出願の件数や権利化率といった数字だけで評価されるような状況では、本当に価値のある特許を生み出すための本質的な活動が見過ごされてしまう可能性があります。
理由③:ビジネス感覚の欠如
知財部員の中には、法律や技術の専門知識は豊富でも、ビジネス全体を俯瞰する視点に欠けている人がいるのも事実です。
「この技術は将来的に大きなビジネスチャンスを生み出す可能性があるから、特許を取っておこう」という視点ではなく、「とにかく特許の要件を満たしているから出願しよう」という、単なる手続きとして知財業務を捉えてしまうケースも少なくありません。
このような場合、開発担当者が熱意を持って提案した発明に対しても、冷徹に「特許性がない」とだけ返してしまうため、「開発の夢を壊す邪魔者」として見られてしまうこともあります。
知財部が「無能」のレッテルをはねのけるために
では、知財部員はどのようにして「無能」のレッテルをはねのけ、会社にとって不可欠な存在になることができるのでしょうか。
① 専門性を高め、根拠のある説明をする
知財の専門家として、常に最新の法律や判例、技術動向をキャッチアップすることが不可欠です。
特に、他部署の担当者から質問された際、「なんとなく」「おそらく」ではなく、「〇〇という理由から、〇〇という判断になります」と明確な根拠を示して説明することが重要です。
そのためには、特許法や商標法といった法律の知識だけでなく、知財戦略やビジネスモデル特許に関する知識も深めておく必要があります。
② 他部署とのコミュニケーションを密にする
知財部が他部署から信頼されるためには、コミュニケーションの改善が何よりも重要です。
- 専門用語を避けて、わかりやすい言葉で説明する:相手の知識レベルに合わせて、かみ砕いた表現を使う工夫をしましょう。
- 相手の立場に立って考える:開発担当者であれば「この特許が取れれば、こんなにすごい製品が作れる」、営業担当者であれば「この商標が取れれば、安心してブランドを育てられる」といった、相手にとってのメリットを明確に伝えることが重要です。
- 積極的に他部署の会議に参加する:開発の初期段階から知財部が関わることで、将来的に特許になる可能性のある発明を早期に発掘したり、特許侵害のリスクを事前に回避したりすることができます。
③ 弁理士資格で「圧倒的な専門性」を証明する
先ほどの理由①で述べたように、専門性を高めることは非常に重要ですが、それを客観的に証明する手段として弁理士資格の取得は非常に有効です。
弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標に関する専門家として、法律で認められた国家資格です。この資格を持つことで、社内外に対して「知財のプロフェッショナル」であることを明確にアピールできます。
私も知財部への異動後、弁理士試験に合格したことで、他部署の担当者からの信頼度が格段に上がったことを実感しています。専門家として、より深い相談を受ける機会が増えましたし、知財戦略の立案にも積極的に関われるようになりました。
弁理士資格がもたらす3つのメリット
弁理士資格を取得することで、単に専門家として認められるだけでなく、様々なメリットを享受できます。
- キャリアの選択肢が広がる: 知財部のスペシャリストとして社内でキャリアアップを目指せるだけでなく、弁理士事務所や他の企業の知財部への転職も可能になります。
- 年収アップの可能性: 弁理士資格は、多くの企業で資格手当の対象となります。また、転職市場でも非常に価値が高く、大幅な年収アップにつながるケースも珍しくありません。
- 自己成長の実感: 弁理士試験の学習を通じて、特許法だけでなく民法や商法など幅広い法律知識が身につきます。これは知財部員としてだけでなく、社会人としての大きな武器となります。
弁理士試験は難しい? 働きながら合格を目指す方法
「弁理士試験は難しいって聞くけど、働きながらなんて無理でしょ?」
そう思われる方も多いかもしれません。確かに、弁理士試験は司法試験や公認会計士試験と並んで「三大難関国家資格」の一つに数えられます。しかし、正しい勉強方法と効率的な学習ツールを使えば、働きながらでも十分に合格を目指すことができます。
私も働きながら、2年間の勉強で合格を勝ち取ることができました。
私が合格した際に利用していたのが、オンラインの弁理士講座です。オンライン講座の最大のメリットは、自分の好きな時間に、自分のペースで学習を進められることです。通勤時間や休憩時間、就寝前のわずかな時間でも、スマートフォン一つで講義を視聴したり、問題演習に取り組んだりできます。
特に私がおすすめしたいのが、スタディング 弁理士講座です。この講座は、スマートフォンで完結できる学習システムが非常に優れており、通勤時間などのスキマ時間を有効活用したい社会人に最適な講座です。
実際の合格体験記もご覧いただけます。
👉 スタディング弁理士講座の無料体験はこちらから
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)弁理士試験に合格した後のキャリアについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
知財部員のキャリアパスと転職市場の現状
「今の会社では知財部員として評価されない」「もっと知財の専門性を活かせる場所で働きたい」と考えている方もいるかもしれません。
知財部員のキャリアパスは、大きく分けて2つあります。
① 社内でのキャリアアップ
- スペシャリスト: 特許技術者として、特定の技術分野の専門性を高めていく道。
- マネジメント: 知財部の部長や課長として、組織全体をマネジメントする道。
- 知財経営: 経営層の一員として、会社の事業戦略に知財の視点から貢献する道。
② 転職によるキャリアアップ
弁理士資格を取得したり、特定の技術分野での専門性を高めたりすることで、より待遇の良い企業や、専門性の高い弁理士事務所への転職が可能になります。
特に、近年ではDX化やグローバル化の進展に伴い、知財人材の需要は高まっています。知財の専門知識と、ビジネス感覚を兼ね備えた人材は、まさに引く手あまたです。
知財専門の転職エージェントを活用しよう
知財部員が転職を考える際、一般的な転職サイトだけでなく、知財専門の転職エージェントを活用することをおすすめします。
知財専門のエージェントは、
- 知財業界の最新動向
- 各企業の知財部の特徴
- 非公開求人の情報
- キャリアプランニングのアドバイス
など、知財業界に特化した専門的な情報を提供してくれます。
私も転職を検討していた時期に利用していましたが、知財の仕事内容や企業風土について、とても深い情報を得ることができ、非常に役立ちました。
特におすすめなのが、リーガルジョブボードです。知財業界に特化しており、弁理士や知財部員の求人情報が豊富です。専門のコンサルタントが親身に相談に乗ってくれるので、漠然と転職を考えている段階でも、一度相談してみる価値はあります。
👉今よりも働きやすい事務所に転職できる。 弁理士・特許技術者求人サイト【リーガルジョブボード】
知財のプロフェッショナルになるための必読書
「これから知財について学んでいきたいけど、何から手をつければいいかわからない」という方も多いでしょう。
ここでは、知財の知識を深めたいあなたにおすすめの書籍を2冊ご紹介します。
法律初心者におすすめの入門書
まず、弁理士試験の受験を検討している方や、法律の勉強に苦手意識がある方におすすめなのが、『弁理士スタートアップテキスト』です。
この書籍は、弁理士試験の全体像をやさしく解説しており、法律に苦手意識がある方にも最適な入門書です。難しい法律用語をかみ砕いて説明してくれるので、初めて特許法に触れる方でもスムーズに読み進められます。
弁理士試験の学習を始める前に、全体像を把握しておくことで、その後の勉強が非常に効率的になります。
知財部の仕事全体を理解したい方へ
次に、知財部という仕事全体を俯瞰的に理解したい方におすすめなのが、『知財部という仕事』です。
この本は、知財部の仕事の具体的な流れや、他部署との連携方法、知財戦略の考え方など、知財部員としての仕事の進め方を体系的に学ぶことができます。
特に、これから知財部に異動する方や、知財部の仕事に興味を持っている方にとっては、知財部のリアルな仕事内容を知る上で非常に役立つ一冊です。
まとめ:「無能な知財部」は過去のものへ
今回は「知財部 無能」という、少し耳の痛いキーワードをきっかけに、知財部の仕事のリアルと、知財部員が会社に貢献していくための具体的な方法について解説しました。
- 「知財部 無能」と言われるのは、仕事内容の理解不足、専門用語の壁、評価の難しさなどが主な原因
- 知財部員は、専門性を高め、コミュニケーションを改善することで、他部署からの信頼を勝ち取れる
- 弁理士資格は、自身の専門性を客観的に証明する強力な武器となる
- 弁理士資格は、年収アップやキャリアアップにも大きく貢献する
- 転職を考える際には、知財専門の転職エージェントを活用すると、より良いキャリアパスが見つかりやすい
知財の仕事は、会社の未来を創る、非常にやりがいのある仕事です。しかし、その専門性の高さゆえに、他部署から理解されにくいという側面があるのも事実です。
だからこそ、知財部員一人ひとりが、自らの専門性を高め、積極的に他部署とコミュニケーションをとっていく努力が求められます。
そして、その努力は必ず会社の成長に繋がり、「無能な知財部」というレッテルを過去のものに変えてくれるはずです。
もしあなたが、知財の専門家として、より深いキャリアを築きたいと考えているなら、まずは弁理士試験の勉強を始めてみることをおすすめします。きっとあなたの人生に、大きな変化をもたらしてくれるはずです。
最後までお読みいただきありがとうございました。