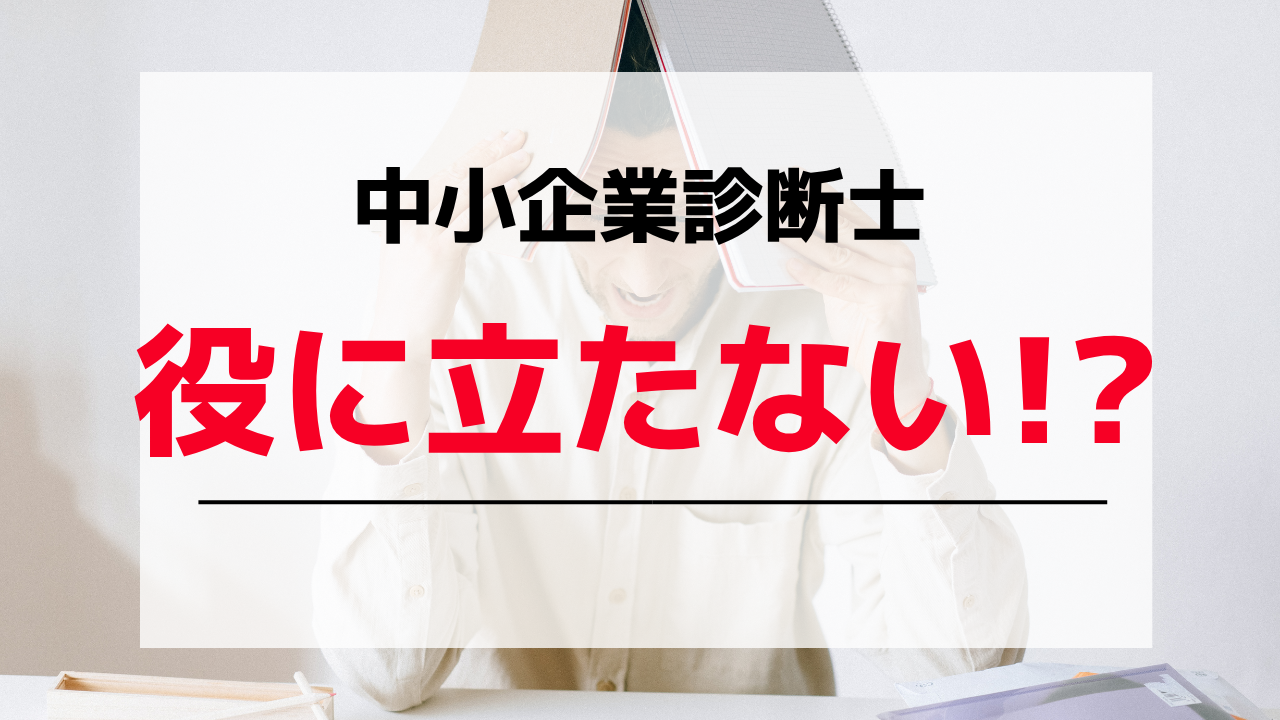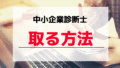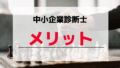「診断士なんて取っても意味ないよ」
そんな声、聞いたことありませんか?
実は、この意見には一理あります。でも、それは”使い方を間違えた場合”の話。
正しく活用すれば、中小企業診断士はあなたのキャリアを大きく変える武器になり得ます。
ポイントは次の3つ:
- ①実務と結びつける
- ②職種・業界の需要に合わせる
- ③独立・副業なら高ROIを狙う
この記事では、「役に立たなかった」というリアルな事例と、「役に立った」成功パターンの両面から徹底解説。
あなたが今、診断士を取るべきか?それとも見送るべきか?その判断材料をすべてお伝えします。
中小企業診断士が「役に立たない」と言われる5つの現実
診断士は”経営の総合格闘技”と呼ばれる資格です。でも残念ながら、万能の魔法ではありません。
「役に立たない」という声の裏には、制度・評価・活用環境のミスマッチが潜んでいます。
私自身、最初は「資格さえ取れば状況が好転する」と思っていました。
でも実際は…取得後の動き方が9割だったんです。
ここを理解しておかないと、時間もお金もムダになってしまいます。以下の5つの現実を、まずは冷静にチェックしていきましょう。
①企業での資格手当が期待外れ――平均5,000円未満のケースも
「資格を取れば手当がもらえる!」
そう期待していたのに、蓋を開けてみたら月3,000〜10,000円程度…なんてケースは珍しくありません。
むしろ、資格手当がない会社も多数存在します。
| 項目 | 金額・期間 |
|---|---|
| 学習コスト総額(教材・模試・二次対策・実務補習込み) | 30〜50万円 |
| 資格手当(平均) | 月3,000〜10,000円 |
| 手当だけで回収にかかる期間 | 5〜10年 |
さらに厳しいのは、「特定部門のみ対象」といった適用制限がある会社も。税理士や社労士といった独占業務系資格と比べると、正直言って分が悪いです。
→ 費用対効果を考えるなら、昇進・異動・転職での収入増まで視野に入れた回収設計が必須です。
学習の最短設計については、独学で最短400時間合格した7STEPが参考になりますよ。
②実務経験ゼロでは「机上の空論」扱いされる
経営は“現場の文脈”が命です。
「資格を取ったからコンサル職に転職できる!」——そう思っていたら、現実は相当厳しいです。
採用担当者が見ているのは、資格の有無ではなく実績・人脈・成果物。
たとえば「メーカー営業5年→診断士取得→未経験で戦略コンサル応募」というケースでは、実務での成果物(企画書・改善レポートなど)がないと、評価がまったく伸びません。
資格を”実務化”できるかどうか——ここが分かれ道になります。
実務補習(15日間)でしっかりレポートを作り、社内プロジェクトで成果を残すなど、実務への翻訳作業が絶対に必要です。
③職種によっては履歴書の隅に書くだけで終わる
製造現場のオペレーション、専門特化したIT開発、医療系の業務…
こうした職種では、”経営の総論”が直接効きにくいのが現実です。
人事評価に「資格加点」がない会社では、資格を取っても活用場面が生まれないまま埋もれてしまうことも。
職種×資格活用度を事前に棚卸しして、以下のような診断士が活きる職種への異動・転職をセットで考えるのが現実的です:
- 経営企画
- 事業開発
- 営業企画
- PMO
- 金融法人営業
④独占業務がないため「名刺の飾り」になりがち
弁護士・税理士と違い、診断士には独占業務がありません。
つまり、無資格のコンサルタントとも競合するんです。
じゃあどうやって差別化するのか?
答えは専門領域×成果物で作るしかありません。
- 会計
- 人事労務
- 補助金
- DX
- データ解析
こうした“もう一枚の切り札”を早期に掛け合わせられる人だけが、単価と再現性を引き上げられます。
⑤年間維持費(登録料・更新研修)が地味に負担
初回登録、協会入会、更新研修(オンライン可)など…
年数万円規模の維持費は、地味にじわじわ効いてきます。
活用の見込みが薄いなら、登録を急がず「合格のみ」でいったん止めるという選択も現実的。
費用と活用のキャッシュフローは、必ず試算しておきましょう。
それでも「役に立つ」人がいる――3つの成功パターン
ここまで読んで、「やっぱり診断士って使えないんだ…」と思いましたか?
ちょっと待ってください。
「役に立たない」を「役に立つ」に反転させる鍵は、文脈づくりにあります。
以下の3つのパターンは、実際に成功者が多く、私の周囲でも結果につながっていました。
①すでにコンサル業務/管理職で実務経験がある人
現場で課題設定〜施策実装を経験している人は、診断士で理論の骨格を得ると言語化の精度が上がります。
社内の戦略検討、事業計画、投資判断の合意形成で威力を発揮するんです。
たとえば、あるメーカー部長の方は取得後に全社改善プロジェクトのオーナーとなり、意思決定の品質と社内説得力が大幅に向上しました。
→ このタイプは最短合格の学習設計がハマります。一次〜二次の橋渡しは一次突破ロードマップで効率化できますよ。
②独立・副業前提でブランディング材料にする人
個人で戦うなら、国家資格の信用力は“扉を開く鍵”になります。
商工会、よろず支援拠点、自治体支援など…案件導線に乗りやすく、初年度は年収300万円規模でも、専門×発信×紹介で3年後に800万円級を狙う実例が多数あります。
私自身、登録後に登壇・記事執筆を先に積み上げ、相談件数→有償化の流れを作りました。
③転職市場で「経営視点」を証明したい20〜30代
事業会社の経営企画/新規事業/営業企画や、総合/ITコンサルへの転職では、書類通過率が底上げされやすいです。
未経験でも「学習努力の証明」「論理型人材のシグナル」として効くことがあり、面接での議論の質が上がります。
→「学びながら成果物を作る」ためには、スキマ時間を活用できる通信講座が便利。スタディングはスマホ完結・映像最適化・記憶定着ドリルが強みで、無料体験で試せます。
失敗しない判断基準――あなたは取るべき?やめるべき?
診断士は向き・不向きがくっきり分かれる資格です。
ここでは数値でROIを見える化し、やる/やらないを決める材料を提供します。
費用対効果シミュレーション:3パターン比較
| パターン | 初期投資 | 回収見込み | ROI評価 |
|---|---|---|---|
| A:大企業会社員(手当5,000円/月) | 約40万円 | 手当のみで約80ヶ月(≒6.7年) 昇進・転職で+50〜150万円/年なら1〜2年で回収可能 | △〜◎ |
| B:独立志向(初年度+200万円) | 約60万円 (プロモーション・ツール費含む) | 1.5年で回収 専門×発信×紹介で3年800万円レンジ | ◎ |
| C:活用予定なし | 約40万円+維持費 | ほぼゼロ | × |
※数値は公開情報と実務ヒアリングに基づく目安。あなたの条件で再計算してください。
「こんな人は今すぐやめるべき」チェックリスト
以下の項目に3つ以上該当するなら、いったん保留が合理的です:
- ✓ 現職で経営/企画に全く関われない(今後の見込みもゼロ)
- ✓ 独立・副業の意思がない
- ✓ 1,000時間の学習を確保できない
- ✓ 資格手当がない&評価制度に加点なし
- ✓ 簿記・社労士・MBAなど他資格の方が直結
「取得を決断すべき人」の5つの条件
該当が多いほど、“使い切れる前提”が整っています:
- ✓ 経営層・事業責任者との接点がある(または作れる)
- ✓ 独立・副業意欲が明確
- ✓ 資格支援制度や学習環境を確保できる
- ✓ コンサル/企画への転職を本気で狙う
- ✓ 経営知識の体系化に価値を感じる
→ 学習の具体ルートは独学400時間の7STEPがそのまま使えます。
中小企業診断士より「使える」代替資格3選
診断士に固執する必要はありません。目的からの逆引きも有効です。
①簿記1級・公認会計士――数字で説得力を持つ
財務・管理会計は全業界で通用します。
簿記1級は約500時間で到達可能とされ、投資対効果が高い。公認会計士は難関ですが、独占業務×高単価で明確な差別化になります。
診断士を補完する資格としても相性が良いです。
②社会保険労務士――独占業務で安定収益
人事・労務は全企業で必須。就業規則・手続・顧問など継続収益を作りやすいのが魅力。
診断士×社労士のダブルは、経営×人事の包括支援で強力です。
③MBA・中小企業大学校――実務直結の学位・プログラム
MBAは費用が重い反面、転職市場でのブランド力が高い。
中小企業大学校は実践志向&良心的な費用で、人脈形成にも効きます。診断士の理論骨格を実装に落とす場としても優秀です。
後悔しない学習戦略――取ると決めたらこう動け
「やる」と決めたなら、最短ルートで。
私はこの流れで効果がありました。
最短合格ルート:効率重視の3ステップ
【STEP1】一次試験(7科目)は優先順位を決めて8か月
企業経営理論 → 財務 → 運営 → 経済 → 情報 → 法務 → 中小政策の順番で攻略。
【STEP2】二次試験(事例Ⅰ〜Ⅳ)は過去問15年×型化
与件要約 → 設問分解 → 因果で骨子 → 書く、の再現性を磨く。
【STEP3】口述試験は模擬3回で十分
筆記の再現答案から想定問答を作成。
詳細の手順は一次突破ロードマップと独学7STEPへどうぞ。
学習コストを最小化する方法
| 学習スタイル | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 独学 | 5〜10万円 | 最低限テキスト+過去問でOK |
| 通信 | 20〜30万円 | スキマ学習×復習導線で時短 |
| 通学 | 40〜60万円 | 強制力と即時質問が武器 |
教育訓練給付金や会社の資格支援を必ず確認しましょう。
スタディングはスマホ完結・映像最適化・記憶定着ドリルが強みで(無料体験はこちら)、勉強を楽しむ工夫とも相性抜群です。
合格後の「使い倒し」戦略――元を取る5つのアクション
合格しただけで満足してはいけません。ここからが本番です:
- 社内:経営企画・新規事業の公募に応募
- 副業:商工会・支援機関に専門家登録(月1〜3件)
- 人脈:研究会・支部活動で案件導線を作る
- 転職:企画・コンサルに応募(職務経歴書で”成果物”を提示)
- 発信:X/note/ブログで経営知見を継続発信
活用のリアルは「合格して人生が変わる理由」と「サラリーマンが取る5つのメリット」が具体的ですよ。
リアルな声――取得者100人の本音(要約)
私が聞き取りや掲示板レビューを横断した結果、ざっくり以下のような感触でした(2024〜2025年の観測ベース):
- 「満足」:48%
- 「不満」:34%
- 「どちらでもない」:18%
不満派の共通点:
- ①実務経験なし
- ②独立意思なし
- ③手当なし
- ④活用部門にいない
満足派の活用法:
- ①独立で専門×発信
- ②企業内で企画へ異動&昇進
- ③副業で講師・補助金・顧問を複線化
数字はあくまで目安ですが、活用設計の有無が評価を分けるのは間違いありません。
Q&A(4問だけ読む人向けダイジェスト)
Q1. 本当に役に立たないの?
A. 状況次第です。活用部門や独立・副業の意志がなければ薄く、実務×発信を組むと強いです。
Q2. 転職では有利?
A. 企画・コンサル系は有利に働きやすいです。一方、専門技術職では効きにくいのが現実。
Q3. 維持費はどのくらい?
A. 登録・更新で年数万円程度。活用の見込みが薄ければ登録を遅らせる選択も。
Q4. 独立で食べられる?
A. 初年度は苦戦が普通です。専門×紹介×発信の導線ができると3年で安定する例が多いです。