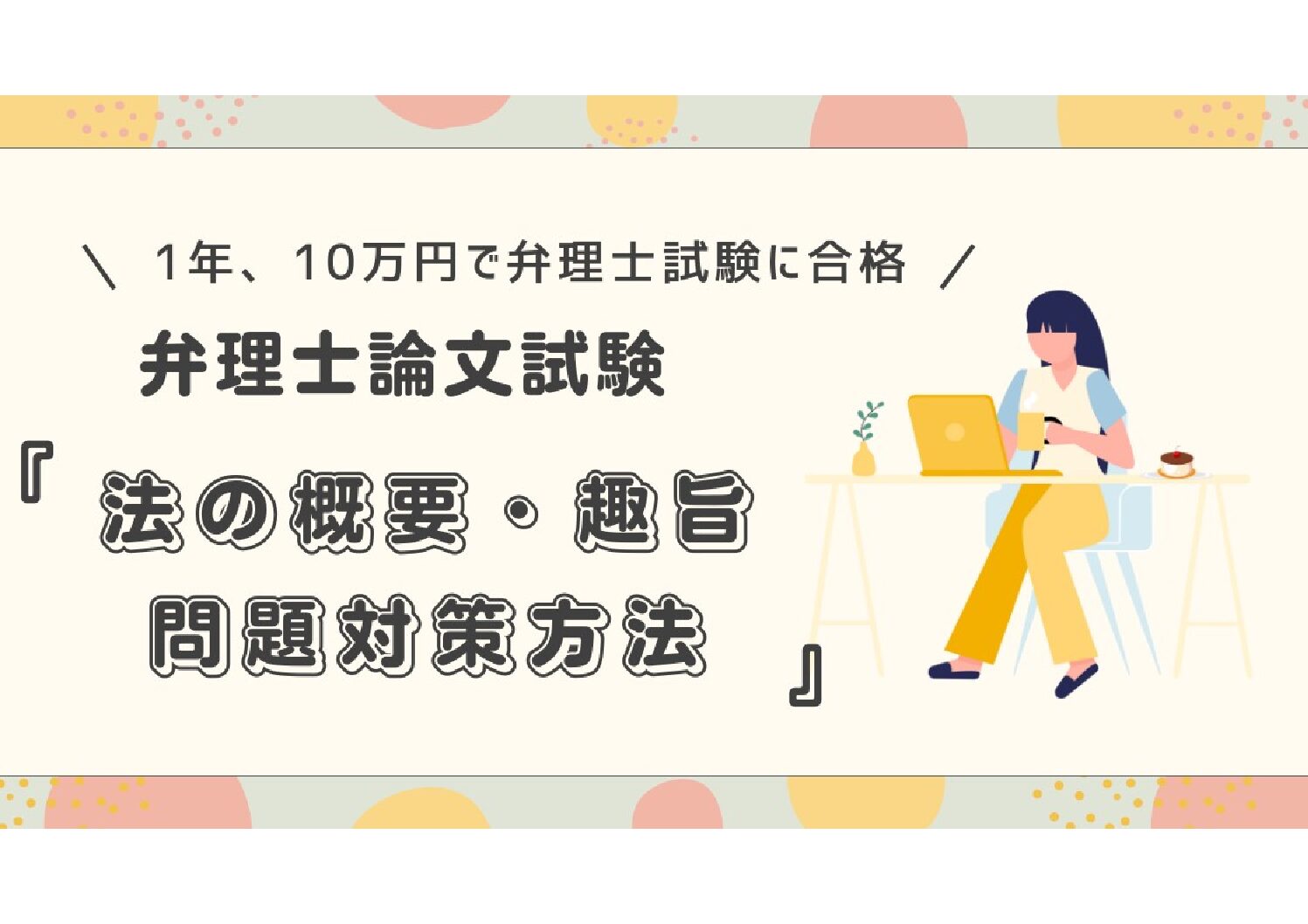この記事は、令和3年度に1年&10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士の実体験を元に書いています。
論文試験——本当に最初は何を書けばいいのかわからないですよね。今回はその「壁」をどう乗り越えるか、論文試験対策で意識すべきことをお伝えします。
前回の記事では、具体的な論文の勉強方法について解説しました。まだ読んでいない方はこちらを先にどうぞ👇
弁理士試験は「どんな人を弁理士にしたいか」を問う試験
論文試験の問題を見て「時間が足りない…」と感じた方は多いはず。でも、それも当然です。
さらに、法文集の持ち込みがOKになっている点にも注目してみましょう。
これはつまり、試験官=特許庁があなたに求めているのは「時間管理と実務遂行力」なんです。
昔は丸暗記の一行問題が中心だったと聞きますが、現在は完全に「実務対応能力重視」の流れに変わっています。あなたがどれだけ現場感覚で解答を作れるかが試されているのです。
論文試験で問われていること=弁理士としての資質
論文試験では、たとえばこんなことが問われます:
- 出願人の立場でどんな手続をとるべきか?
- 弁理士としてどのように助言・対応すべきか?
- 審査官ならどんな拒絶理由通知をするか?
つまり問われているのは、実務家としての的確な判断力・知識の活用力です。
これらを限られた時間で、法文集を活用しつつ、バランスよく書けるかがポイントです。
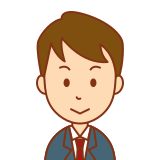
大学受験の予備校の先生で、『過去問は受験生へのメッセージ。過去問の声を聴け』と言ってる先生が居たなあ
【重要】論文試験で常に意識すべき3つの柱
私が本番・練習でずっと意識していたのは、以下の3点です。
- 問いに正確に答える(コミュニケーションできる人材か)
- 法文集を迅速に使いこなす
- 時間内に、偏りなく、最も点が取れる形で解答する
それぞれ詳しく解説します。
1,問いにきちんと答える力
これが何より重要。たとえば「拒絶理由は?」と聞かれているのに、出願人としての対応を書いてしまう。これ、実際によくあるミスです。このパターンのミスを見つけたら大いに反省してください。
これはつまり、相手の問いに対して正確にコミュニケーションが取れていないということ。
「話を聞かない人を弁理士にしたくない」という特許庁のメッセージとも読み取れますね。
これがまずは一番大事だと思いますし、間違えると大きく点数を引かれることになるので普段から意識しましょう。
弁理士試験は特別な解答を書いて点数をもらうよりは、穴の無い解答で点数を落とさないことがとにかく大事なので、絶対に問いに対する答え間違えをしてはなりません。

弁理士の仕事ってクライアントの話を聞いたり、発明者の話を聞いたりする仕事。聞かれた問いにきちんと答えられない人、話を聞かない人を弁理士にはしたくないって気持ちはわかるよね。。。
2,法文集を使いこなすスキル
持ち込みが許されている以上、「法文集を使って問題を解くスキル」は必須。
特に短答の段階から、一問一問、必ず法文を引く習慣をつけてください。
私が使っていたのは《PATECH企画出版部 知的財産権法文集 第28版》。本試験と同じ構成になっており、サイズもコンパクトで使いやすかったです。
メルカリなどで貸与法文集の中古を買うのもアリです。
最新版を下に貼っておきますね。
3,時間内に、偏りなく、点数が取れる形で書く
ここが最大の山場。ポイントは2つあります。
① 書くスピードと文字数の最適化
- 法文集の丸写しOKな部分は丸写し!
- 規範→事案への当てはめ→結論の流れを簡略化
- 「①~、②~」のような番号付きで簡潔に
- 表現を簡略化して文字数を削減
普段から「時間がある場合」「時間がない場合」で書く量を意識的にコントロールしましょう。
② 配点構造を意識して解く
弁理士試験は、おそらく要素ごとに点数が分かれているため、要素の抜け漏れが一番の失点要因になります。
たとえば:
国際出願を取り下げられたものとみなされないための手続きは?
✅ 翻訳文の提出
✅ 特許管理人の選任
✅ 出願審査請求
最低限、この3つの要素を書き出せれば、部分点は拾えます。
時間がなければ条文番号だけ、余裕があれば条文の中身まで書く。どこまで書けるかの戦略も試験対策です。
例えば、日本国の特許出願とみなされた国際出願が取り下げられたものとみなされないために、なすべき手続きについて問われた場合。
答えるべきは①翻訳文提出、②特許管理人の選任、③出願審査請求となるわけです。
まずはこの3つを答える。そして時間がなければ条文番号をカッコ書きで追加する。
時間があれば簡単に条文の内容を写す。
この中で②は難しいから最悪①と③は答えられるようにして、そこそこの点数を稼ぎたいとか作戦を考えながら解いていきましょう。
このように問題を解くときには、配点の要素を意識して、時間がたくさんあればここまで書こうとか、最低ここは書けるようにしたいなとかそういったところを意識してやっていきましょう。
以上を考えながら解けば
✔時間内に、偏りなく、点数が取れる形で書く
は達成できるかなと思います。
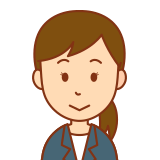
常に全体のバランスをと時間を配分を考えて解くのが大事だね~
実際の解き方についてはこちらでご紹介しています。
論文でやりがちなミス:時間配分と根拠不足に注意!
論文対策をしていると、多くの受験生が陥りやすい2大ミスがあります。それが「時間配分の失敗」と「主張に根拠がない答案」です。私もこの2つで何度も痛い目を見ました。
⏱️ やりがちミス①:時間配分が崩壊する
弁理士論文試験は「時間との戦い」です。実力があっても、時間が足りず白紙の設問が出れば一発アウト。特に注意したいのは以下のようなケースです。
- 配点が低い前半設問に時間をかけすぎる
- 答えやすい問題に没頭してしまい、難しい設問に手が回らない
- 書きながら構成を考える(=無駄なタイムロス)
このミスを防ぐには:
- 解答前にざっと全体を見て、「各設問にかけるべき時間」を決める
- 10分ごとの時間チェックを習慣化する
- 骨格(答案構成)を最初に軽く書き出しておく
私は「解きやすいところから手を付ける」「配点が大きい設問を優先する」など試験当日の戦略をルール化することで、白紙ゼロを実現できるようになりました。
💬 やりがちミス②:理由や根拠があいまいな主張
次に多いのが、「主張だけ書いて根拠が無い」ミスです。例えば、「この補正は認められるべきだ」とだけ書いてしまい、「なぜ?」に答えていない。
試験官は「この受験生はなぜそう判断したのか?」を見ています。理由・根拠のない主張は評価されないどころか、「わかっていない」と判断されて減点対象になります。
ありがちなパターン:
- 「結論」だけで本文が終わっている
- 条文番号を書かない
- 趣旨や判例に一切言及しない
- 当てはめが抽象的すぎる
このミスを防ぐには:
- 「主張→理由→根拠(条文・趣旨・判例)」の三段構成を癖づける
- 条文番号をカッコ書きでもいいから添える
- 書いた主張に対して「それ、なぜ?」と自問する練習をする
私は答案練習のたびに、「この文章、説得力あるか?法律家として説明できてるか?」とチェックしていました。最初はくどいくらいに書いてOK。削るのは合格が見えてからです。
まとめ:論文試験で意識すべき3つの鉄則
最後にもう一度、論文試験対策で大事なことを整理します。
✅ 問いに正確に答える
✅ 法文集を使いこなす
✅ 時間配分と配点構造を意識して、偏りなく解答する
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)