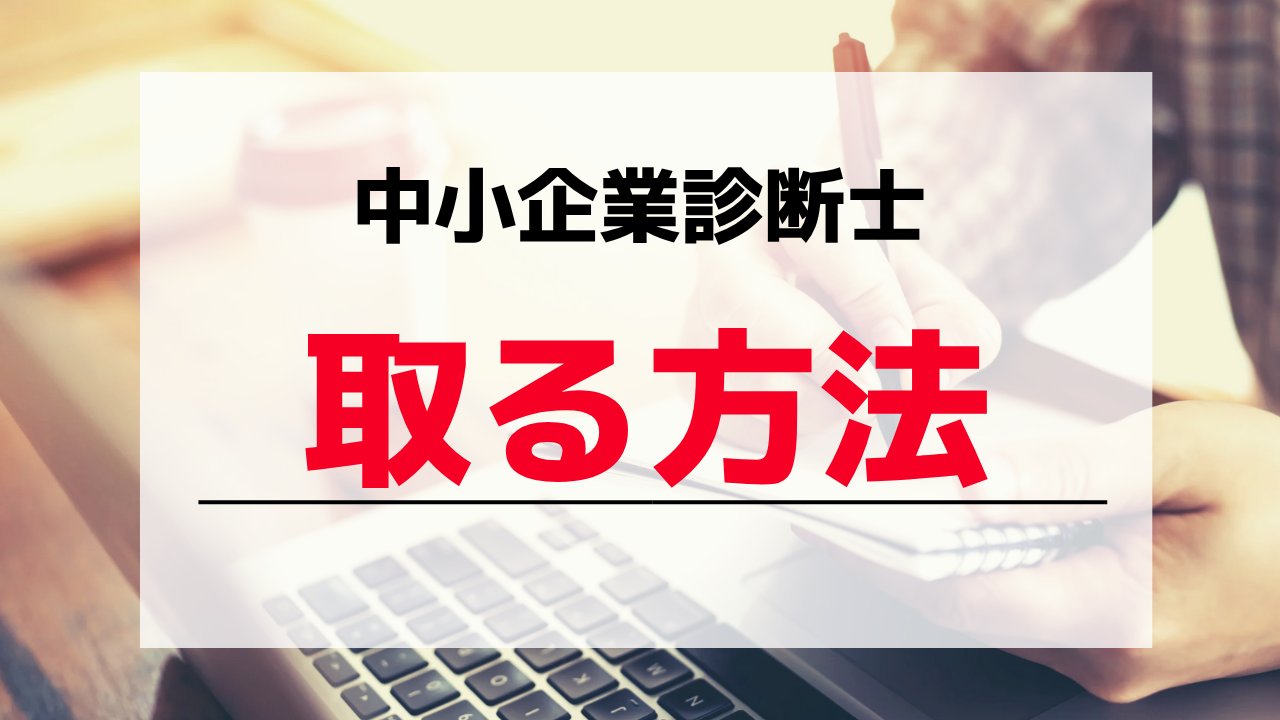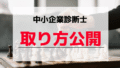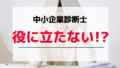中小企業診断士になるには、1次試験→2次試験→実務補習(または実務従事)→登録という4ステップが必要です。
合格率は1次約30%、2次約20%と難関ですが、正しい学習計画と自分に合う勉強法を選べば、働きながらでも1〜3年で到達可能。
ここでは受験資格から登録、費用、最短合格のコツまで、実体験と最新データをもとに分かりやすく解説します。
【結論】中小企業診断士になるための4ステップ全体像
診断士取得の全体像はシンプルです。
- ステップ1:1次試験(7科目・マーク式)
- ステップ2:2次試験(筆記4事例+口述)
- ステップ3:実務補習15日または実務従事
- ステップ4:登録(登録免許税・協会入会等)
超速で1年完走も不可能ではありませんが、社会人の現実解は平均2〜3年。
ポイントは「最終形(登録)から逆算した年間カレンダー」を作ること。
私は学習初期に”逆算カレンダー”を作り、週の固定学習枠と休暇取得計画まで先置きしました。その結果、迷いが激減し、学習量が安定。
全体の道筋は、私がまとめた独学最短400時間の7STEPが設計図になります。
併せて一次突破ロードマップを読み、1次→2次の橋渡しまでイメージしておくと、ギアチェンジが滑らかです。
受験資格は一切不要|年齢・学歴・実務経験ゼロでもOK
診断士試験は受験資格の制限がありません。
年齢・学歴・実務経験は不問で、受験者層は20代〜60代まで幅広いのが特徴。平均年齢は30代後半ですが、学生・主婦・定年後の再スタート組も増えています。
だからこそ重要なのは「自分に合う学習スタイル」と「確保できる学習時間」を早期に見極めること。
私の体感では、1日2時間×平日+週末5時間を基準に、無理のない計画を組める人ほど継続率が高いです。
学習の楽しみ方は体験談:勉強は楽しい!が参考になります。
まずは試験制度=誰でも挑戦できる国家資格という出発点を押さえましょう。
取得までにかかる期間と費用の目安
期間は超速1年〜標準2〜3年。
| 学習方法 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 独学 | 15〜20万円 | 自由度高、コスト低 |
| 通信 | 30〜40万円 | スキマ時間活用、継続しやすい |
| 通学 | 50〜70万円 | 強制力・仲間・即質問 |
※受験料、教材、模試、2次対策、実務補習費用約15万円などを合算
「費用対効果」の観点では、スキマ時間の換金性が高い通信講座が社会人と相性良し。
通勤・昼休み・家事の合間を”分割学習”に変えられるかが勝負どころ。
スマホ完結で学べるスタディングは、見やすい映像・記憶定着のドリル・復習レコメンドが強み。
無料体験でUIと復習導線を確認してから比較検討すると失敗が減ります。
失敗しない!中小企業診断士試験の全体制度を理解しよう
1次は7科目のマーク式、2次は記述中心の4事例+口述。
特徴は科目合格制度(有効3年)がある点で、忙しい人でも複数年で積み上げられます。
1次は知識の幅、2次は「経営者視点で因果を語る力」が問われるため、学習の質が変わります。
私も一次期から要約・整文の”素振り”を入れて、2次への橋をかけました。
制度の俯瞰→学習順序の設計→進捗KPI(週学習時間/過去問周回/答案添削)という順で固めると、迷いが消えて継続が楽に。
一次の時短はスタディング一次突破体験談の流れを借りると効率的です。
1次試験の科目構成と合格基準
科目は以下の7科目です。
- 経済学・経済政策
- 財務・会計
- 企業経営理論
- 運営管理(オペレーション・マネジメント)
- 経営法務
- 経営情報システム
- 中小企業経営・中小企業政策
合格基準:総得点60%以上かつ各科目40%以上(足切り)で合格。
得点源になりやすいのは企業経営理論・運営管理・経済、苦手が出やすいのは財務会計・法務という受験生傾向が多いです。
戦略は「伸ばせる科目で先行逃げ切り+足切り対策」。
複数年設計なら初年4科目→翌年3科目が王道。
私は過去問→論点復習→横断表の3ステップで周回を固定化し、出題頻度の高い論点から”得点の取りこぼし”をなくしました。
具体の回し方は独学400時間の7STEPに書いています。
2次試験(筆記・口述)の特徴と対策ポイント
2次筆記は事例Ⅰ〜Ⅳを各80分で解く”競技”。
与件要約→設問分解→因果で骨子→日本語で伝える型の再現性がすべてです。
独学の壁は客観添削の不足。ここは添削サービスや通信講座で外部目線を入れるのが近道でした。
口述は合格率が高いものの、想定問答の音読練習は必須。
二次対策の楽しみ方や継続コツは体験談:勉強は楽しい!に詳述。
スキマ学習×添削を両立したい人はスタディングの映像とドリル→復習提示の流れが時短に効きます。
【最短合格】あなたに合った勉強法の選び方|独学・通信・通学を徹底比較
学習法は「費用」「時間」「継続性」「フィードバック」の4軸で選びます。
| 方法 | 費用 | メリット | デメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 独学 | 5〜10万円 | 低コスト・自由度高 | 2次添削弱い・孤独 | 自己管理できる人 |
| 通信 | 20〜30万円 | 映像+演習+質問・時短 | 強制力やや弱い | スキマ時間活用したい人 |
| 通学 | 40〜60万円 | 強制力・仲間・即質問 | 高額・移動時間 | 1年完走を狙う人 |
私のおすすめは、一次=独学+通信/二次=添削重視のハイブリッド。
まずは無料体験でインターフェースの相性を見るのが失敗しないコツです。
比較や設計は一次突破ロードマップが詳しいです。
独学で合格した人が実践していた3つの共通点
独学成功者には共通点があります。
- 過去問10年分を最低3周(年度横断で論点の出現頻度を体に刻む)
- 苦手の早期特定→集中ドリル(特に財務・法務)
- 学習ログ公開で継続(SNS・ブログ)
私はGoogleスプレッドシートで「学習時間/周回数/正答率」を可視化し、週ごとに”やらないこと”を決めて失速を防ぎました。
独学の具体ルートは独学7STEPをそのままテンプレにできます。
初心者が挫折しない通信講座の選び方
見るべきは合格実績、質問導線、復習設計、価格。
私は「スマホ完結×復習の自動提示」を重視しました。
スタディングは授業を”撮って出し”ではなく映像教材として編集され、視覚的で理解しやすい構成。
脳科学ベースの暗記補助・問題練習機能で短時間でも点に変えやすいのが利点です。
まずは無料体験で自分の生活動線に合うか確認を。
通学講座のメリットと費用対効果
通学の最大価値は強制力と”人”による伴走。
疑問はその場で解消でき、同期ネットワークが一生の資産になります。
費用は高めでも、短期集中で1年合格を狙いたい人、自己管理に不安がある人には有効。
直前期の模試→個別面談→弱点補強のサイクルが作りやすい点も魅力です。
通学のデメリット(移動・拘束)を補うため、平日は通信、週末は通学のミックス運用も効果的です。
科目別攻略法|合格者が教える効率的な学習の進め方
共通の王道は過去問中心。
まずは企業経営理論→財務会計→運営管理の順で”軸科目”を固め、情報・法務・中小政策を直前期で積み増す流れが合理的。
論点マップを自作し、年度横断で「頻出・重要・時事」を色分け。
誤答ノートには”勘違いの理由”まで書き、再発を潰します。
二次を意識し、一次期から短文要約と因果で書く練習を週1で入れておくと、二次の立ち上がりが段違いに楽になります。
財務会計を制する者が1次試験を制す
財務は得点のレバー。
仕訳・CVP・NPV・WACC・意思決定会計など、出る論点は毎年似るので、問題形式で反復して身体化を。
簿記2級相当の知識があると有利ですが、なくても計算手順のテンプレ化で十分戦えます。
私は通勤で解法カードを見返し、帰宅後にドリルで”手を動かす”二段構えで安定しました。
一次の具体手順は一次突破ロードマップを参照。
暗記科目(経営法務・情報システム)の時短テクニック
暗記は直前濃縮型が効きます。
語呂合わせ/図解/マインドマップで記憶”引き出し”を増やし、改正点は最新版で上書き。
私は小テスト化(10問×5分)で回転数を上げ、朝イチと就寝前の”同じ問題”で記憶定着を促進。
映像→小テスト→弱点ドリル→再テストの短サイクルを回しやすいのは、スタディングの無料体験で確認できます。
2次試験対策は「80分間の思考訓練」が全て
設問の制約条件→因果→具体策の”型”を手に馴染ませます。
再現答案の比較で「採点者に刺さる日本語」を盗み、事例Ⅳは毎日1題で筋トレ。
独学の限界は自分の文章の弱点が見えづらいこと。
私は添削を定期投入し、指摘→修正→再提出の反復で点が安定しました。
二次の楽しさや継続ワザは体験談が役立ちます。
実務補習・実務従事とは?登録までの最終ステップ
2次合格後、実務経験がない場合は実務補習15日が必要。
5日×3回で、現地調査→課題抽出→改善提案→最終報告までやり切ります。
費用は約15万円+交通宿泊が目安。
企業内の方は実務従事で代替も可能ですが、要件・証憑がやや煩雑。
私は「ネットワーク形成」「案件型の学び」を重視して実務補習派を推します。
ここで得た指導員・同期の縁が、その後のキャリア・副業に直結しやすいからです。
登録後の活かし方は合格して人生が変わる理由でイメージを掴めます。
実務補習の内容とスケジュール【2025年最新】
日程は平日5日×3ターム(地域により連続/分散)。
チームで役割分担し、企業訪問→ヒアリング→分析→報告書→発表までを短期で統合します。
ドキュメントテンプレを事前に整備し、会議体の進め方を決めておくと深夜作業が激減。
申込みは先着のこともあるため、口述合格見込み段階から休暇・家庭の調整を始めるのが安全です。
実務従事で登録する場合の注意点
“診断業務として相当”と認められる仕事内容・期間・証憑が必要。
社内業務で満たせる人もいますが、証明の整備に手間がかかることがあります。
確実性と学びの濃度を優先するなら、やはり補習が無難。
どちらを選ぶにせよ、スケジュールと費用を早めに確保しておきましょう。
中小企業診断士取得後のキャリアパス|年収・働き方の実例
企業内は経営企画/事業開発/PMO/DXへの展開で昇進・手当・異動に波及。
独立は補助金・顧問・研修・事業承継など収益の複線化がしやすく、軌道に乗ると年収800万円以上も珍しくありません。
副業は週末コンサル/セミナー/執筆で+5〜15万円/月が現実的。
メリット5選と人生が変わる理由に、活用のリアルをまとめています。
【体験談①】会社員のまま取得してキャリアアップした35歳Bさん
メーカー営業から経営企画へ異動。社内の新規事業PJでリーダーに抜擢され、年収+100万円。
評価の理由は「経営の言語で提案できるようになったこと」。
診断士で”経営の共通語”を獲得した結果、経営層との往復がスムーズになりました。
【体験談②】独立して年収700万円を実現した42歳Cさん
取得後2年で独立。自治体案件+民間コンサルを組み合わせ、3年目には年収700万円。
初年度は整地期間で収入は不安定でしたが、補助金支援×業界知見の掛け算でリピートが増加。
実務補習での縁が案件の導線になったそうです。
【体験談③】副業診断士として月10万円稼ぐ38歳Dさん
平日は本業、土日限定で月10万円。
内容はセミナー講師・補助金申請サポート・記事執筆のポートフォリオ型。
本業の安定×副業の挑戦で、キャリアの選択肢が広がりました。
こうした実例は合格後の体験記にもまとめています。
よくある失敗パターンと挫折しないためのコツ
ありがちな失敗は以下の3つ。
- ①科目合格制度を知らずに1年で全科目狙い→過負荷
- ②二次を軽視して一次後に慌てる
- ③学習時間の事前確保をしない
回避策は、逆算カレンダーで週の固定枠を先にブロック、二次は一次期から週1本の素振り、家族・上司への根回しで学習環境を整えること。
私は「やらないことリスト」を週次で更新して、教材増殖を防ぎました。
迷ったら独学7STEPどおりに進めるのが一番速いです。
働きながらでも学習時間を確保する方法
通勤×音声、昼休み×10分小テスト、帰宅後×ドリルの三段活用。
朝活で“最重要1タスク”を終えると、1日の満足感が違います。
週末は過去問の長時間ブロックを1回。
家族に学習カレンダーを共有し、応援してもらえる関係を先に作るのもコツです。
モチベーションを維持する仕組みづくり
学習記録の可視化(累積時間の見える化)、仲間づくり(X・コミュニティ)、小さなご褒美。
合格後の未来像はメリット5つを読むと具体化します。
映像→小テスト→復習提示の短サイクルで前進感が出やすいのは、スタディングの無料体験で実感できます。
【まとめ】中小企業診断士になるには、今日から行動を始めよう
受験資格不要=誰でも挑戦可。
独学・通信・通学の選択肢があり、1〜3年で到達できます。
合格後は企業内の昇進・異動/副業拡張/独立と、キャリアの景色が一変。
まずは試験日程のカレンダー固定→主教材の決定→1週間の試走から。
学習設計の全体像は<a href=”https://benrishi-coffee.com/chusho-dokugaku/” target=”_blank” rel=”