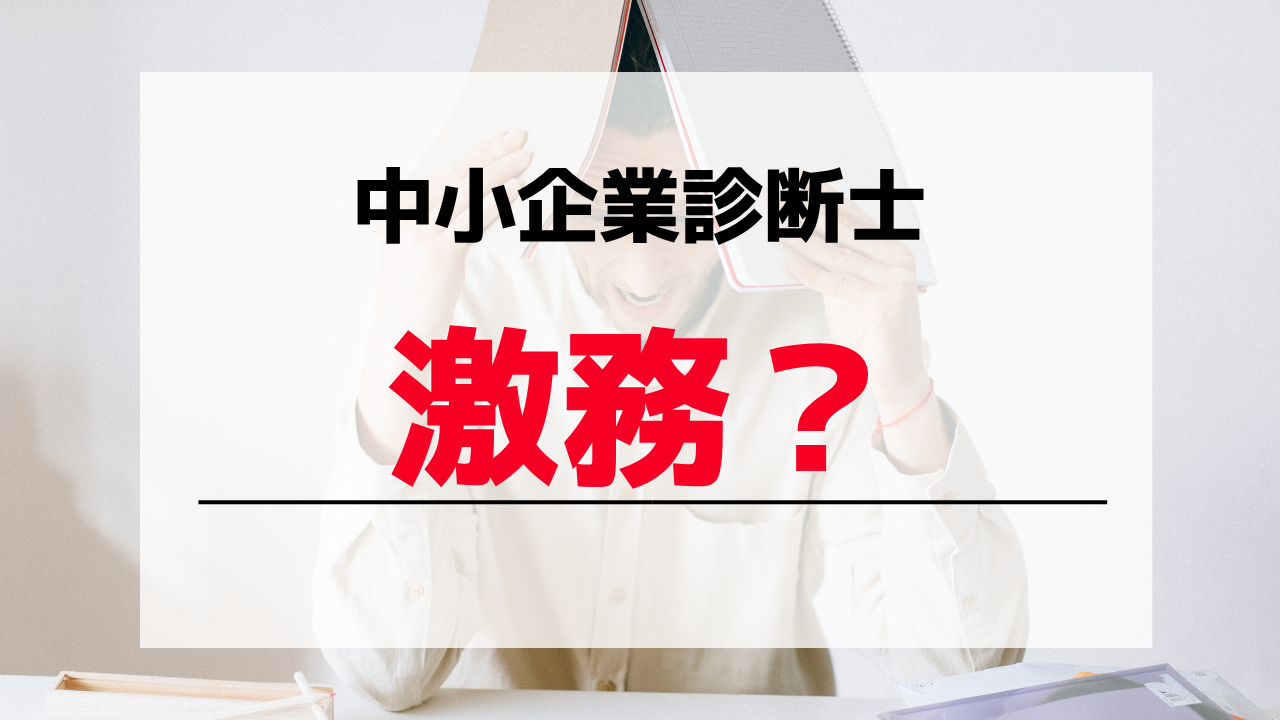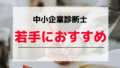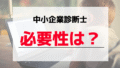中小企業診断士は激務なのか?
結論から言うと、「フェーズと働き方で大きく異なる」が答えです。
実務補習は確かに負荷が大きく、独立すれば裁量次第で繁閑の差も激しくなります。一方、企業内診断士なら本業のペースに合わせて安定的に活動できる人が多数派です。
本記事では、最新データと体験談、忙しさの比較表をもとに、“あなたに合う働き方”を見極めるヒントをお届けします。
中小企業診断士は本当に激務? 結論と3つのポイント
「激務かどうか」を左右するのは、次の3つの要素です。
(1)資格取得〜登録のフェーズ
(2)働き方の選択(企業内・副業・独立)
(3)繁忙期の有無
まず実務補習(15日間)について。
面談・現地調査・報告書作成がぎゅっと詰め込まれ、土日終日+平日夜の準備が標準です。受講手数料の目安は15日コースで17万8600円(税込)。5日×3回の分散型を選ぶこともできます。
一方、独立直後は営業(提案書・面談・登壇準備)に多くの時間を割き、案件獲得後は調査・設計・資料作成で稼働が膨らみやすいのが実情です。
企業内診断士は本業に診断士スキルを重ねる形で、月にプラス20〜40時間の範囲で両立する人が多数派。さらに補助金の公募期や決算期には、独立・副業ともに依頼が集中し、土日稼働が増える傾向があります。
要点は、時期を設計し、負荷を”自分でコントロールする”発想です。
短期合格を目指すなら、独学で最短400時間で合格した7STEPが参考になります。一次試験の時短にはスタディングだけで一次突破したロードマップが最短ルートづくりに役立ちます。
【フェーズ別】中小企業診断士が激務になる4つのタイミング
2次試験〜実務補習期間(最も激務)
最短で登録まで走り抜ける局面が、最もタフです。
2次合格後の実務補習15日は、連続型で詰めるか、5日×3回の分散型を選択できます。いずれも事前準備(調査・分析・章立て)に平日2〜3時間×約10日は見込むのが現実的。受講手数料は前述のとおり15日で17万8600円が目安です。
体験談スナップ:
- 「育休明けで受講、1か月の平均睡眠4時間。家族合意の大切さを痛感」(30代・会社員)
- 「分散型を3か月、毎週末が実質”補習デー”で趣味は一時休止」(40代・メーカー)
対策としては、分散型の活用/有休の前倒し取得/家族合意→家事外注がポイント。段取りテンプレを使うと報告書の執筆・整形時間を大幅短縮できます。
合格までの迷子を防ぐには、独学7STEPの実践記が効率的。一次の詰めはスタディングだけで一次突破をトレースするのがおすすめです。
独立開業初年度(営業・実績づくりで多忙)
「受注の谷」を超えるまでが勝負です。
初年度は面談・提案・見積・契約といった営業オペに月100時間超が乗りやすく、受注後は調査・伴走・資料で深夜作業も発生します。
“協業・外注・ニッチ特化”で単価と可処分時間を守るのが鉄則。公募・補助金支援に絡めばさらに稼働が増えるため、案件型(スポット)と顧問型のポートフォリオで平準化しましょう。
補助金の公募スケジュール(例:2025年のものづくり補助金の公募・申請期間)は、春先に集中する回が典型で短期の提出ラッシュになりがちです。
繁忙期(決算・補助金申請期)
3〜5月の決算期/春の補助金公募は”ダブルパンチ”です。
企業内でも決算・予算編成が重なるなか、副業・独立側の依頼も集中。週末の面談・原稿〆切が連続するため、“土日を使う前提でカレンダーを逆算”しておくと安全です。
補助金関連は年度や回次で変動しますが、例年、春〜初夏のラッシュが忙しさの山を作りやすい点は頭に入れておきましょう。
更新・研修義務(5年ごとの負担)
資格は”取りっぱなし”ではなく”鍛え続ける”設計です。
理論政策更新研修(オンライン可)や実務従事ポイントの確保は、年に1〜2件の実務を堅実に積むイメージ。企業内で機会が少ない人は、協会支部・研究会・外部実務サービスを活用して20時間前後の実務枠を計画的に押さえると安心です。
【働き方別】激務度を徹底比較! あなたに合うスタイルは?
| スタイル | 月間稼働の目安 | 収入レンジの目安 | 自由度 | 安定性 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業内診断士 | 20–40時間 | 年+50〜150万円 (手当・昇進含む) | △ | ◎ | 本業で評価を上げたい |
| 副業診断士 | 30–80時間 | 年+100〜400万円 | ◯ | ◯ | リスクを抑えて実績作り |
| 独立診断士 | 120–250時間 | 年300〜1200万円 | ◎ | △ | 収益上限を上げたい |
登録者は企業内が多数派で、独立・副業は少数ながら伸長というのが足元の傾向。繁忙期はどの形でも稼働が跳ねるため、事前の受注設計とカレンダー運用でならすのがコツです。
企業内での上振れや体験はサラリーマンが中小企業診断士を取る5つのメリット、独立・副業の跳躍は合格して人生が変わる理由の実例が参考になります。
激務を回避! 診断士が実践する5つの時間管理術
実務補習を乗り切る3つのコツ
①分散型受講で体力温存
②役割分担(章責任者・図表・数表)で執筆を並列化
③テンプレート活用で報告書の体裁・脚注・付録を時短
合格前から独学7STEPの型を取り入れると、「調査→構造化→文章化」の回転が速くなります。
独立診断士の案件選別基準
「単価×稼働×再現性」で機械的に選びましょう。
- 時給換算3000円未満は原則見送り
- 移動2時間超はオンライン化 or 交通費+拘束料で是正
- リピート率70%以上の顧客へ集中投下
補助金や決算タスクに偏ると稼働が波打つため、研修・顧問・アセスメント等の平準化メニューを一つ持つと安定します(公募の山谷は最新スケジュールを必ず確認)。
企業内診断士の両立テクニック
「本業で診断士を使う」発想へ転換しましょう。
経営企画・新規事業・営業企画・DXの小さなプロジェクトを主導し、四半期で”数字の改善”を1つ積む。実務ポイントは支部・研究会の案件で補完。有給・時短制度は実務補習前にブロックを確保しましょう。
一次の効率化はスタディングだけで一次突破の時短ノウハウが有効です。
激務の先にあるメリット! 中小企業診断士の3大魅力
①市場価値の向上
経営の共通言語が使える人材として、社内外での希少性が上がります。
②複数収入源
顧問/研修講師/執筆のレベニュー・ミックスで景気変動の耐性が高まります。
③ネットワーク
協会・研究会・金融機関・公的支援機関との接点が増え、紹介の連鎖が起きやすくなります。
中小企業白書2025でも、DX・選択と集中・人材育成を軸に、診断士的なアプローチが経営改革に有効な事例が示されています。
合格後の”広がり”は合格して人生が変わる理由にまとまっています。
こんな人は要注意! 激務で挫折する3つの失敗パターン
失敗①:家族合意なしで実務補習へ突入
15日+準備で家庭崩壊寸前、は”あるある”です。必ず事前説明と役割分担を。
失敗②:準備不足で独立
受注の波で現金枯渇。副業→協業→特化を1年かけて整えてからが安全です。
失敗③:就業規則を読まずに副業
規程違反で懲戒リスク。社内規程の確認・申請をセットで行いましょう。
まずは「働き方パターン」「補習の時期」「家族・上司への説明」の三点を綿密に設計しましょう。
【2025年最新】中小企業診断士の働き方トレンド
トレンド①:オンライン診断の普及
地方の受注チャンスが拡大しています。
トレンド②:DX・データ利活用の需要増
若手・デジタル強者が台頭。白書の事例でも診断士×ITで生産性向上の成果が多数報告されています。
トレンド③:企業内診断士向けマッチング
社外の案件と”低負荷で接続”する仕組みが広がっています。
“繁忙の山”になりやすい補助金回りの公募期は、直近の公募情報を都度チェックして計画的に動きましょう。
まとめ――中小企業診断士は「激務」だが、働き方次第でコントロール可能
- 実務補習・独立初期は確かに激務(15日補習+準備、独立は営業+納品で稼働増)
- 企業内・副業スタイルなら月20〜80時間で両立可。繁忙期の山はスケジュールで均す
- 時間管理・案件選別・家族合意で”自分に合った激務レベル”へ調整できる
今日できる行動:
①働き方パターンを選ぶ → ②補習時期を決めて有休を先押さえ → ③テンプレで準備
学習のロードマップは独学7STEP(最短400時間)、一次の時短はスタディング活用、継続の仕掛けは勉強は楽しい!、キャリアの広げ方は人生が変わる理由とメリット5つをどうぞ。
Q&A(よくある質問)
Q1. 実務補習15日はどれくらい忙しい?
A. 連続型なら15日間ほぼ終日拘束+平日夜に2〜3時間×約10日の準備が目安。分散型でも毎週末5〜8時間の作業が3か月続くイメージです。受講手数料(15日:17万8600円)や日程は公式案内を確認してください。
Q2. 本業と両立できる?
A. 企業内なら+20〜40時間/月で回る設計が現実的。繁忙期は一時的に増えるため、有休ブロックと家族合意を先に取っておきましょう。一次はスタディングだけで一次突破のスキマ活用が有効です。
Q3. 独立後はどれくらい忙しい?
A. 初年度は営業込みで150〜250時間/月になりがちです。補助金公募期はさらに上振れします。顧問・研修で平準化し、公募スケジュールを踏まえて前倒し準備を心がけましょう。
Q4. 繁忙期はいつ?
A. 多くの現場で3〜5月(決算・予算)と春〜初夏の補助金公募期がピーク。最新の回次・締切は都度確認してください。
Q5. 激務を避ける方法は?
A. 企業内で活用+分散型補習+副業は月1〜2件に限定が現実的。テンプレ・外注・オンライン化で”作業”を削り、”意思決定”に時間を配分しましょう。
※本記事は2025年10月時点の公開情報・制度ページ・白書等を参照し執筆しています。最新の受講手数料・日程・公募スケジュールは、必ず公式情報をご確認ください。