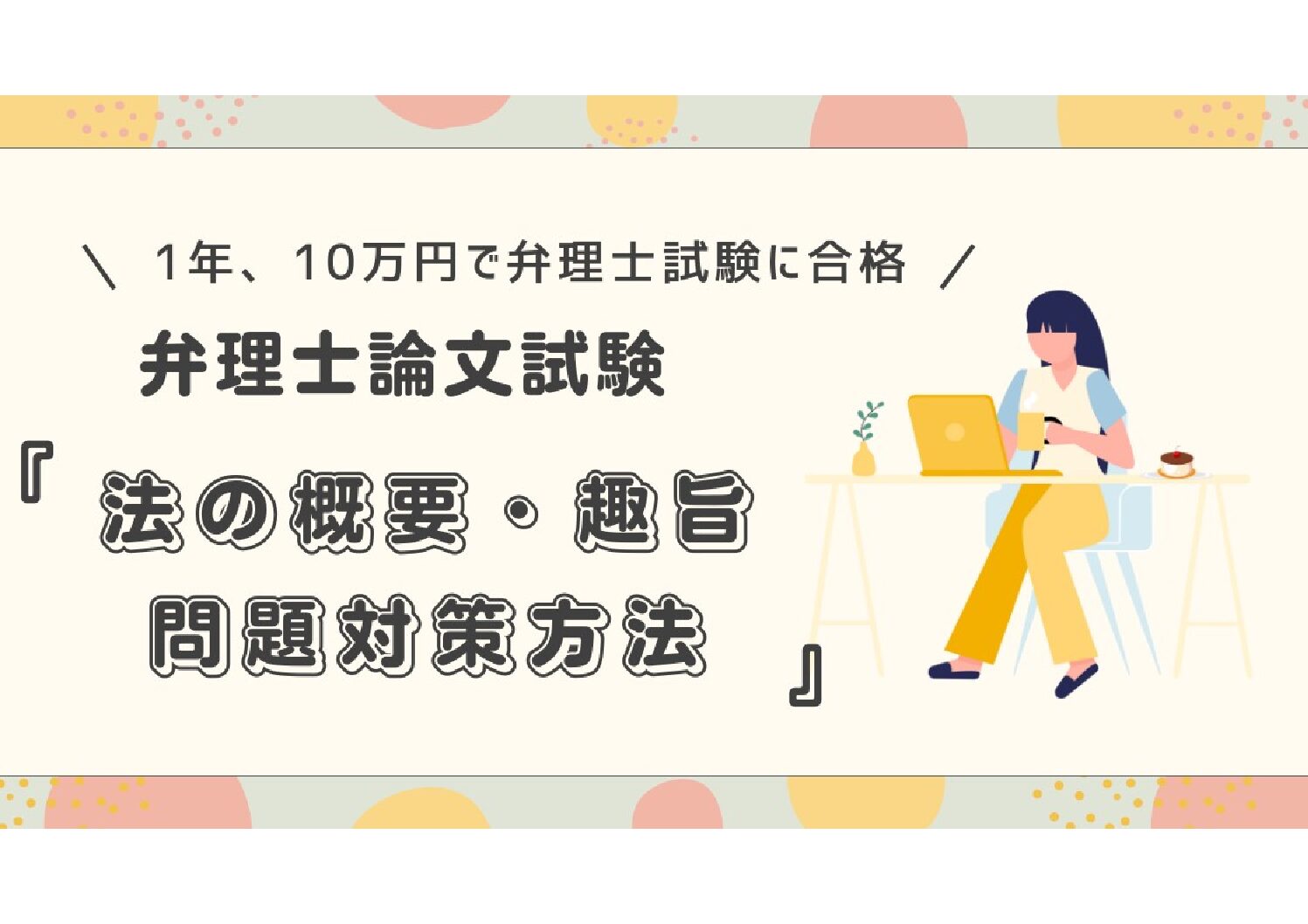この記事は、令和3年度に1年・10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が、実体験をもとに執筆しています。受験生だけでなく、知財実務に携わる方々、知財分野への転職を考えている方々にも役立つ内容です。今回は弁理士試験で重要かつ実務にも直結する「判例解説シリーズ④」として、選択発明および除くクレームについて深堀り解説します。
弁理士試験では多くの判例知識が求められますが、暗記に走るのではなく、「なぜ重要なのか」「実務でどう役立つのか」という視点を持つことで、知識が定着しやすくなります。そして、これは実務力を養ううえでも重要です。
選択発明とは何か?
概要
選択発明とは、先行技術に含まれる上位概念(例えば、ある範囲やグループ)の中から、特定の下位概念(より具体的な範囲や条件)を選び出して構成した発明を指します。ただし、選択した下位概念が単なる一例にすぎず、特に優れた効果や新しい技術思想を含まない場合は、新規性・進歩性が否定される可能性があります。
例(化学分野で典型的)
- 先行技術:A成分30~70%、B成分残部の化合物
- 発明:A成分45~55%、B成分残部の化合物
一見、範囲を絞っただけに見えますが、「45~55%」という狭い範囲に予測不能な効果があれば、特許性が認められます。
判例(平成14(行ケ)524、平成15年12月25日)
この判例では、選択発明の定義と進歩性の基準について以下のように示されています。
① 選択発明は特許法上の明文規定はなく、審査基準に基づく実務概念。
② 上位概念に包含される下位概念から選択し、先行発明に新規性を失わない発明。
③ 進歩性の有無は「刊行物に記載のない異質の効果」や「顕著に優れた効果」があるかどうか。
重要なのは、「単に範囲を絞っただけではダメ」で、「予測できない特有の効果」が必要という点です。
実務への影響
この判例は特に化学・医薬の分野で重要です。出願時には、選択発明の位置づけを意識し、明細書で効果の詳細なデータや実施例を丁寧に記載しておく必要があります。そうしないと、審査段階で「単なる範囲選択」と見なされ、進歩性が否定されるおそれがあります。
企業知財部でも、発明提案を受けた段階で「それは単なる選択発明では?」と疑う目を持つことが重要です。
知財業務全般については下記で解説をしています。
受験対策のコツ:選択発明をどう覚えるか?
選択発明は短答・論文ともによく問われるテーマです。勉強の際には以下を意識すると効果的です。
- 定義を言語化する練習をする。 → 「上位概念から下位概念を選び、予測困難な効果を奏する発明」
- 具体例をイメージする。 → 化学、医薬、材料系の例をいくつか押さえる。
- 他の重要判例と比較する。 → 例えば、「特許法29条の新規性・進歩性の一般論」や「パラメータ発明」との関係。
「暗記」だけではなく、「理解」と「例示」ができるようにすると、論文対策にも強くなります。
弁理士論文試験の「法の概要・趣旨問題」対策法についてはこちらで詳しく解説しています。
除くクレームとする補正とは?
概要
除くクレームとは、請求項の中から先行技術と重複する部分を除外することで、新規性や進歩性の要件を満たそうとする補正のことです。
例えば:
- 出願時の請求項:A、B、Cを含む装置
- 先行技術:A、B、Cを含む装置(公開済)
- 補正後の請求項:A、B、C(ただし、先行技術に係るA、B、Cを除く)
ただし、これは万能な手段ではなく、特許庁の審査基準や判例では以下の条件が必要とされています。
- 除外後の発明が当初明細書の記載範囲内であること。
- 単なる構成要素の削除ではダメ。
- 技術思想として先行技術と顕著に異なる発明であること。
判例(平成17(行ケ)10608、平成18年6月20日)
① 除くクレームは「先行技術との重複部分を除外する補正」である。
② 当初明細書の記載範囲内なら許される。
③ 技術的思想が顕著に異なり、本来進歩性を有する場合に限り、除く補正で特許が認められる。
④ そうでない場合、単に除いても進歩性欠如の拒絶理由は解消されない。
要するに、「単なるごまかし補正」は通用しないということです。
実務への影響
補正の実務では、除外対象とした先行技術との関係を明確化し、進歩性の根拠を論理的に主張する必要があります。また、クレーム補正に際しては、当初明細書の記載と矛盾しないよう細心の注意を払わなければなりません。
企業知財部では、代理人任せにせず、補正案の検討段階から関与し、拒絶理由対応の方向性を把握しておくとよいでしょう。
受験対策のコツ:除くクレームをどう攻略するか?
除くクレームは試験での出題頻度は高くありませんが、理解しておくと論文の論理展開に深みが出ます。
- 定義を正確に覚える。
- 「万能手段ではない」と意識する。
- 判例の具体的な結論を一行で言えるようにする。
論文試験での答案作成では、「安易に除くクレーム補正に頼らず、技術思想の差を論じる」ことが高得点につながります。
弁理士試験の論文対策にはStudyingの弁理士講座が最適です。私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)実務家・知財部員向け:さらに実務に役立つポイント
現場で特に意識したいのは次の点です。
- 出願時の明細書作成で、選択発明・除くクレームの要件を満たすデータや実施例を盛り込む。
- 拒絶理由通知が来た際、代理人との協議で判例・審査基準を意識した方針を立てる。
- 社内での発明発掘段階から、これらの概念を意識し、将来の出願・権利化リスクを見極める。
企業知財部にとって、弁理士試験の勉強は単なる資格取得ではなく、実務力の強化そのものになります。
【FAQ】弁理士試験・知財実務の選択発明&除くクレーム補正
Q1. 選択発明ってなぜ重要なの?
A1.
選択発明は、先行技術(例えば既知の化合物群や数値範囲)から特定の構成を選び出すことで特許性を主張する発明です。
例えば、先行技術で「100種類の化合物が有効」と記載されている中から、ある一種類の化合物Aが特に優れた効果を示すことを見つけた場合、このAの化合物が選択発明になります。
弁理士試験では、選択発明に関する新規性・進歩性の論点は非常に頻出で、特に化学・医薬分野の事例問題で多く問われます。実務では、クライアントの発明を権利化できるかどうかの判断や、拒絶理由への反論戦略に欠かせない知識です。
Q2. 選択発明の「予測困難な効果」とは具体的に何?
A2.
例えば、従来技術で「化合物A~Zが血圧降下作用を示す」とされている中で、化合物Mを選択した場合に、Mが単に同程度の効果を示すだけでは新規性・進歩性は認められません。
しかし、Mが「極めて強力な効果」「副作用が著しく低減する」など、従来技術からは予測できない特別な効果を発揮する場合、「予測困難な顕著な効果」があると評価されます。
つまり、単なる範囲の限定ではなく、「なぜその限定が意味を持つのか」という裏付けが求められます。実務では、実験データや比較例を出すことが重要です。
Q3. 「除くクレーム補正」はどんなときに使う?
A3.
例えば、あなたの出願が「A~Zの化合物」と広く請求していたとします。ところが審査で「A~Cは既知」という拒絶理由が来た場合、「本件発明はA~Zの化合物。ただしA~Cを除く」と補正することで、先行技術に含まれないD~Zだけを請求するようにします。
つまり、「問題となる部分を請求項から除外して」新規性や進歩性を確保するのが除くクレーム補正です。ただし、明細書に「A~Cは除外してよい」という示唆がないと、新規事項追加の違反になるため注意が必要です。
Q4. 除くクレーム補正は万能な回避策?
A4.
いいえ、むしろ使用は慎重であるべきです。
除くクレーム補正は、
- 技術思想として「A~Z」と「A~Cを除くD~Z」が成立する場合
- 明細書や図面に「A~Cを除外可能」と読める記載がある場合
のみ有効です。
例えば、機械の請求項で「ギアA~Z」としたものから「A~Cを除く」と補正しても、それが単なるパーツの削除で技術思想が変わるなら、補正は認められない可能性があります。
実務では、安易な除外補正はかえって権利範囲を不明確にしたり、拒絶理由を増やすリスクがあります。
Q5. 試験対策として判例集は何を使えばよいですか?
A5.
定評のあるものとしては『弁理士試験 判例マスター』『知財判例百選』があります。受験予備校のテキストや講座付属資料も非常に有用です。判例集だけでなく、講義動画や要件整理ノートと併用すると理解が深まります。
まとめ:試験知識を実務に活かす
弁理士試験の学習は、単なる資格取得のための勉強ではなく、実務に直結する知識の土台作りです。選択発明や除くクレーム補正といったテーマは、日々の出願、補正、審判対応の中で何度も顔を出します。
受験生の皆さんには、判例を「暗記する対象」としてではなく、「実務でどのように役立つのか」という視点で学んでいただくことを強くお勧めします。これは論文試験の答案作成や口述試験でも大きな武器になります。
弁理士試験、知財実務に役立つ判例編④~選択発明、除くクレームへの補正について本日は解説いたしました。
他にも弁理士試験の勉強方法、知財部で仕事内容に解説していますので、ぜひご覧ください。
私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。
知財関係の転職をご検討中の方はこちらをご参照ください。