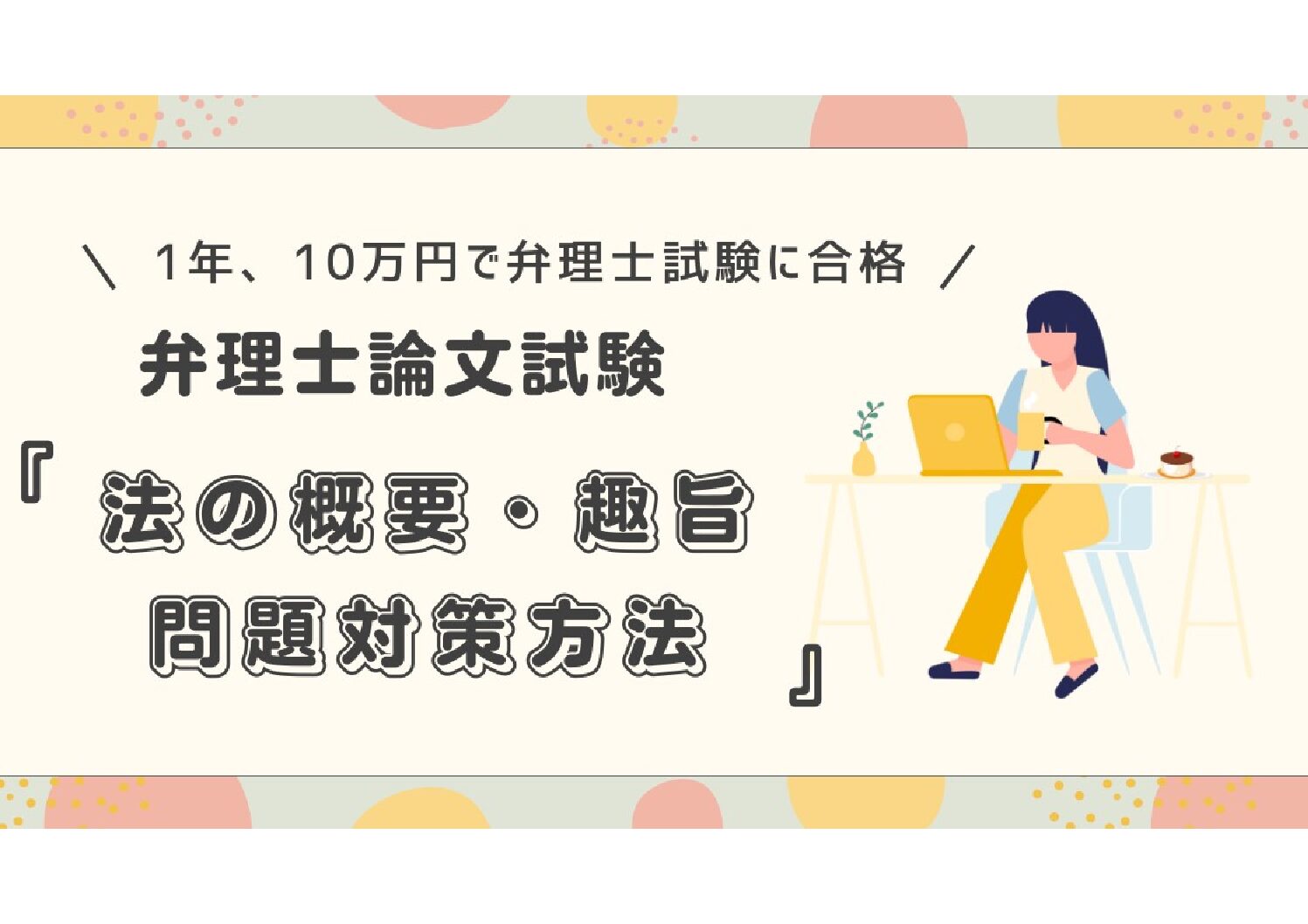この記事は、令和3年度にたった10万円以下の費用・約1年の勉強で弁理士試験に合格した、現役企業内弁理士が実体験に基づいて書いています。
今回は、弁理士試験の中でも「論文試験」の中で問われる法の概要や趣旨問題の勉強法について、次のような疑問に答える形で解説します。
- 趣旨問題ってどう対策すればいいの?
- 配点低そうだけど勉強する意味あるの?
- 何をどこまで覚えればいいの?
そんな悩みに、実体験を交えてお答えします!
本日は法の概要、趣旨の勉強をどのように勉強すればいいのかという点について書きます。
弁理士試験の論文試験では法概要や趣旨を答える問題がメインではないですが毎年出ており、勉強すべき範囲は広く皆さんもどのくらい勉強すればよいか迷われるのではないでしょうか。
論文試験全体の勉強法についてはこちらの記事をご参照ください。
法の概要・趣旨問題って何?どのくらい出題される?
まず、趣旨問題は論文試験でメインではありませんが、ほぼ毎年何かしらの形で出題されています。
【令和3年度の出題例】
・特許法 問題Ⅰ-1(1)
→ 国内優先権制度の趣旨に言及しつつ、関連条文を用いたあてはめ問題
出願Bが審査に付された場合に、出願Bの特許請求の範囲に記載された発明イが乙に
よる出願Dとの関係において拒絶理由を有するかについて、関連する特許法上の根拠条
文の規定を必要な範囲で引用した上で、国内優先権の制度が設けられた趣旨に必要な範
囲で言及しつつ、設問の事実をあてはめて結論付けよ(特許庁HPより)
・意匠法 商標法
→ 問題の一部として趣旨に軽く触れる設問
令和3年度は例年に増して趣旨問題の問われる量が少なかったです。しかも問題の一部に組み込まれており、丸覚えしていないと書けないというレベルの出題の出され方はされてませんでした。
しかしながら、令和2年度までは毎年商標法と意匠法で出題されており、対策は必要だと思います。
これらを踏まえて勉強法をアドバイスしたいと思います。

どんどん趣旨の丸覚え問題は減る傾向にあるね。
論文試験での優先順位の付け方【結論:趣旨暗記はサブでOK】
論文試験対策としては、「趣旨問題の暗記」は優先度はやや低めと考えるべきです。
なぜ優先度が低めか?
- 出題頻度・配点ともにメインではない
- 趣旨よりも、論理的に構成されたあてはめ力が評価される
- 学習負荷が高いわりにリターンが少ない
とはいえ「無視」はNG!
- 商標法・意匠法では依然として問われやすい
- 口述試験ではほぼ確実に聞かれるので、論文での学習は後に活きる

1年目の受験で短答突破してから論文試験の勉強始めたタイプの人はまず、論文の書き方を覚えるのを最優先に考えよう。
趣旨問題の対策方針:具体的にどこを勉強するべき?
優先順位を3ランクで仕分けしよう
細かく言うと特許法、意匠法、商標法で聞かれる範囲の広さと毎年どのくらい出ているかによって優先順位は変わります。意匠法、商標法は優先度少し高め、特許法はどこかで見切りつけないと泥沼にはまっていきます。
具体的に言うと、A,B,Cくらいでランク付けましょう。Aは必ず書けるようにしたい。Bは本番出たら全部ではないが、要点は書けるように。Cは時間あったらやろう(多分やらない)くらいの感じですね。
| ランク | 内容 |
|---|---|
| Aランク | 絶対に書けるようにする範囲(出題頻度・重要度ともに高) |
| Bランク | 要点だけは拾えるようにする範囲 |
| Cランク | 時間が余ったらやるレベル(多くは後回しでOK) |
まず過去問とか予想問題集とか問題で出てきたやつは抑えましょう。間違いなくAです。
そんでもって特許法で先願主義(39条)、国内優先権(41条)、補償金請求権(65条)、拡大先願(29条の2)、特許権の消尽、出願公開(64条)等特許法の根幹に関わるところは聞かれてもおかしくないかなと思います。この辺はAですかね。
特許異議申し立てや前置審査等はBです。
逆に並行輸入、リパーゼ事件とかはCでいいかなと僕は判断してました。
【Aランク例】
- 特許法:先願主義(39条)、国内優先権(41条)、補償金請求権(65条)、拡大先願(29条の2)、特許権の消尽、出願公開(64条)
- 商標法・意匠法:出題実績のある制度趣旨全般
【Bランク例】
- 特許異議申立て、訂正審判、前置審査など
【Cランク例】
- 並行輸入(リパーゼ事件)などマニアックな論点
あくまで自分の時間と相談してという話なので、前年度短答試験受かって、論文対策1年やってますみたいな人は全方位対策でがっつりやるべきだと思います。

口述試験で趣旨等は必ず聞かれるので、論文の時に勉強したことは決して無駄にはならないよ!
特許法は本当に覚えることが多いので、全部覚えようとすると失敗するよ~
勉強法:私が実践した効率的な方法
1,Wordに書き写して「自分用まとめノート」を作成
- 模範解答をWordに書き写す
- スマホで読めるようにPDF化して持ち歩く
- 1日1~2テーマずつ読む
📌 回転数の目安
Cランク:2周(時間があれば)
Aランク:5~6周
Bランク:3周
2. 「書ける言葉」でまとめ直す
- 丸写し厳禁。平易な日本語で、自分の言葉で言い換えよう
- 箇条書きでもOK。要は「本番で使えるか」が基準
- 覚えるのではなく「再現できるようにする」ことが大事
こういうのは覚えよう、覚えようとするとダメです。僕の場合だけかもしれませんが、覚えようとするとストレスになります。作業に落とし込みましょう。具体的には書き写す。まとめる、読むです。
趣旨の勉強で気を付けたいポイント3選 ~効率よく楽しく覚えるコツ~
趣旨の勉強は、弁理士論文試験の対策として確かに必要ですが、取り組み方を間違えると非効率になりがちです。ここでは、私自身の体験をもとに、「趣旨問題対策の注意点と効果的な進め方」をご紹介します。
① 趣旨の勉強を“メイン”にしない
これは一番大事です。
趣旨の勉強はあくまで“スキマ時間でやるサブ科目”と割り切りましょう。
- 机に向かって1日中趣旨だけを勉強するのはNG
- まとまった時間が取れるときは、論文問題の演習や条文の理解を優先
- 趣旨は「ながら学習」や「疲れたときの気分転換」にちょうどいい
✍️ 私の場合は、移動中やカフェ、美容院の待ち時間などにPDFで読んでいました。
② 趣旨は“楽しんで”学ぶのが正解
趣旨問題って、実は意外と面白いんです。
- 「なぜこの制度があるのか?」
- 「この条文って、どんなトラブルを防ぐためにあるんだろう?」
そんなことを考えながら読むと、法律の世界がぐっと身近になります。
実際、私も疲れたときや勉強に飽きたときに趣旨に触れて、「なんか楽しいな」と思いながら続けていました。
そもそも、楽しいと思うことこそ、最強の記憶法です。
好きな芸能人の名前って一瞬で覚えられますよね。それと同じ感覚です。
③ 解答の“丸写し暗記”は絶対NG
趣旨問題の対策として模範解答を読むのは大事ですが、そのまま丸写し・丸暗記するのはおすすめしません。
なぜなら、試験本番で「そのまま再現」はできないからです。
✅ こうするとうまくいく!
- 自分が本番で書けそうな言葉に言い換える
- 箇条書きにしてもOK(構成が整理されてわかりやすい)
- 使う言葉は「自分の書く言葉」に近づける
- 文量は減らしすぎず、「100~120字程度」を目安に
📌 重要なのは「再現できること」。
きれいな模範解答を書く必要はなく、「減点されないレベル」で再現できれば十分です。
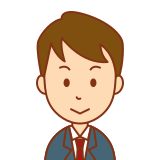
常に本番を意識する。これが合格の秘訣だよ!!
本番での実際の解き方についてはこちらでご紹介しています。
趣旨学習の注意点とコツまとめ
- 丸暗記厳禁! 自分の言葉でまとめる
- 合間時間で反復するのが鉄則
- メインの勉強(論文演習)を優先すること
- 趣旨問題を本番で楽しむくらいの余裕が最終ゴール
まとめ:趣旨問題対策はこうやる!
✅ 近年出題頻度はやや減少傾向にある
✅ とはいえ論文・口述で出るため対策は必要
✅ 優先順位をつけ、Aランク条文から重点的に学ぶ
✅ 丸暗記ではなく、「自分の言葉で再現」できるように
✅ 合間時間を活用し、趣旨学習を「習慣化」する
論文試験は、やればやるだけ上達します。趣旨問題も、完璧主義に走らず、自分なりのスタイルを作っていきましょう。
次回は、論文試験でやりがちなミスとその回避法について実例を交えて解説していきます。
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)