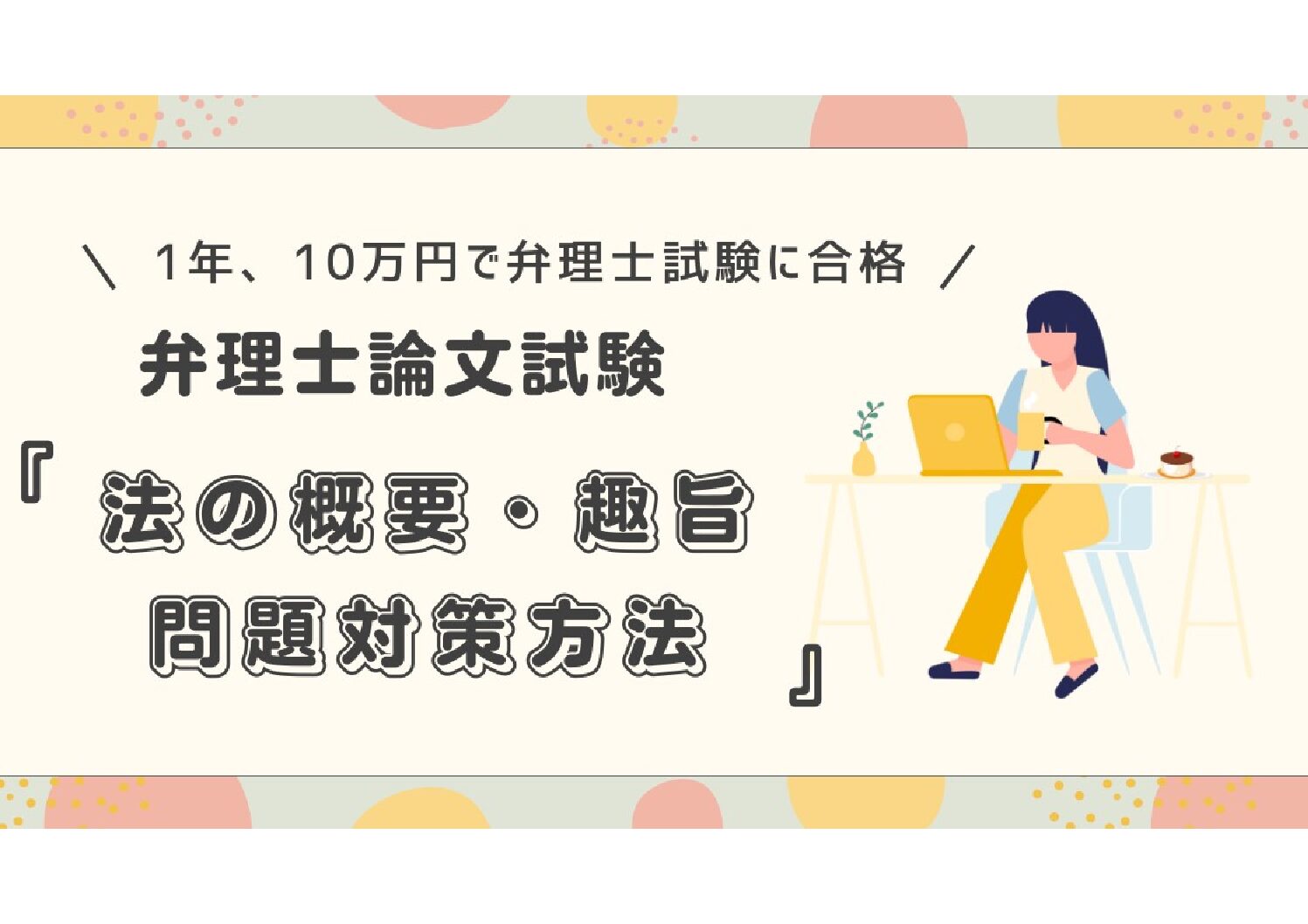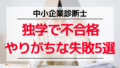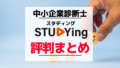知財の世界では条文の暗記だけではなく、「判例の理解」が合格・実務の鍵になります。
弁理士試験(特に論文試験)では判例趣旨を押さえておくことが強い武器となり、実務でも判例を知らないと間違った判断をしてしまうリスクがあります。
この記事では、知財実務・弁理士試験で特に重要な5つの判例を厳選し、
背景・争点・判示内容・試験での位置づけ・実務上の教訓まで、徹底解説します。
この記事を読み終わる頃には、ただの知識としてではなく、判例の「考え方」をしっかり身につけられるはずです。
◆ 弁理士試験における判例の重要性
弁理士試験は、単なる知識試験ではありません。判例の理解は、法文を単に暗記するのではなく、趣旨や背景を理解し、実務でどう使えるのかを考える訓練として非常に重要です。
判例を知ることで、以下のような力がつきます。
- 試験での論述力、説得力の向上
- 実務での審査官や弁護士、発明者との議論の基盤
- リスク予測力(失敗・トラブルの未然防止)
特に実務では、「判例を知らないこと」が大きなトラブルに直結することも珍しくありません。では、具体的な判例を見ていきましょう。
弁理士論文試験の「法の概要・趣旨問題」対策法についてはこちらで詳しく解説しています。
⚖ 1. 日東事件(最高裁平成10年7月17日)
◆ 背景
特許出願は誰が行ってもよいのでしょうか?実は特許法では発明者またはその承継人が出願人になることが大前提です(特29条、特38条1項)。
発明者の承諾なしに第三者が勝手に出願した場合、いわゆる「冒認出願」として特許無効の原因になります(特123条1項4号)。
日東事件は、この冒認出願に関する代表的判例です。
◆ 事案の概要
発明者が同僚や上司の承諾なしに自分単独で出願し、後から承諾の有無が問題となった事件です。
◆ 判旨・趣旨
最高裁は次のように判断しました。
- 出願時に発明者全員の承諾が必要。
- 発明者の承諾がなければ冒認出願にあたり、無効理由になる。
- 無効審判では、承諾がなかったことを主張する側(請求人)が立証する必要がある。
◆ 試験・実務上の重要性
- 試験では、特123条1項4号や共同発明者の意義に絡めて頻出。
- 実務では、共同研究の契約書で「出願の承諾」条項を入れることが重要。
うっかり承諾を得ないまま出願すると、後から無効を主張される危険があります。
◆ 教訓
発明者の確認・承諾は出願の最重要事項。
特に共同研究・社外の共同発明では、契約段階で「出願権限」を明確にしておくべきです。
知財業務全般については下記で解説をしています。
⚖ 2. キルビー事件(知財高裁平成17年1月28日)
◆ 背景
職務発明制度は企業にとって重要な制度です。
特35条では、会社が職務発明を承継した場合、発明者には「相当の対価」を支払う必要があります。
では、その「相当の対価」とは一体いくらなのか?
キルビー事件は、職務発明の報奨金の算定基準を示した画期的判例です。
◆ 事案の概要
TI(テキサス・インスツルメンツ社)のキルビー氏が発明した集積回路の技術(IC)が会社に巨額の利益をもたらしました。
しかし、発明者に支払われた報奨金はわずか。発明者が「もっと正当な対価を!」と訴えたのが発端です。
◆ 判旨・趣旨
知財高裁は次のように判示しました。
- 対価の算定は、発明による技術的価値(利益)、会社の貢献、契約・就業規則を総合考慮。
- 一律の計算式ではなく、実態を踏まえて判断する。
◆ 試験・実務上の重要性
- 試験では特35条の解釈問題に頻出。
- 実務では、職務発明規程の整備、特に対価算定の透明性が大事です。
キルビー事件以降、多くの企業が就業規則・発明報奨制度を見直しました。
◆ 教訓
- 発明報奨は「形だけ」ではダメ。実態に即した合理的な基準が必要。
- 後の紛争を防ぐには、発明者への説明責任を果たし、納得感ある制度を作ることが肝心。
⚖ 3. フェイスクリーム事件(東京高裁昭和61年3月26日)
◆ 背景
学会発表や展示会などで技術を公開してしまった後でも、特許出願できる場合があります。
それが**新規性喪失の例外(特30条)**です。
ただし、法定の手続きを踏まないと、例外の適用は認められません。
フェイスクリーム事件は、この例外適用を巡って重要な判断を示した事件です。
◆ 事案の概要
化粧品メーカーがフェイスクリームの開発発表を行った後に特許出願。
ところが、手続上の証明書提出を怠り、新規性喪失の例外が認められないとされた事件です。
◆ 判旨・趣旨
- 新規性喪失の例外は出願時に証明書提出が必要(当時は30条2項、現行法でも同様)。
- 公開後の手続怠慢は例外適用の救済にならない。
◆ 試験・実務上の重要性
- 試験では特30条の適用要件が頻出。
- 実務では社内ルールとして、発表・出展前に知財部門に必ず連絡させる仕組みが不可欠です。
◆ 教訓
- 公開前の「発表管理フロー」の徹底。
- 「出願→公開」の順番を守るか、やむを得ず公開するなら事前・事後の手続きを怠らない。
⚖ 4. 医療行為の発明(最高裁平成17年10月27日)
◆ 背景
医師による手術、治療法の特許出願は可能でしょうか?
特許法では「産業上利用可能性」(特29条1項柱書)が要件となります。
医療行為は人の生命・健康を直接対象とするため、産業の定義に含まれるかが問題になります。
◆ 事案の概要
外科手術の新しい縫合法に関する特許が産業上利用可能か否かが争われました。
◆ 判旨・趣旨
最高裁は次のように判示しました。
- 医師の医療行為は産業とはいえない。
(人の生命・健康を直接対象とし、営利事業として一般に提供されるものではない) - ただし、医療機器・薬剤・診断方法は産業上利用可能性あり。
◆ 試験・実務上の重要性
- 試験では産業上利用可能性の理解問題に頻出。
- 実務では、医療・ヘルスケア分野の出願戦略に直結。
特に機器メーカーやバイオベンチャーにとっては重要な判断基準です。
◆ 教訓
- 医療分野の発明は、行為そのものか、機器・薬剤かを峻別することが重要。
- クレームドラフティングで医療行為を回避する工夫が求められます。
⚖ 5. 発明の反復可能性(ステント事件:知財高裁平成19年5月30日)
◆ 背景
特許出願における明細書の記載要件として、「発明の反復可能性」(特36条4項1号)が求められます。
これは、当業者が明細書を読んで発明を実施できる程度の記載があるかという要件です。
ステント事件は、この反復可能性の重要性を示した典型例です。
◆ 事案の概要
心臓の血管を広げるステントに関する発明。
明細書の記載が不十分で、当業者が発明を実施できないとされた。
◆ 判旨・趣旨
- 明細書には当業者が容易に発明を実施できる程度の記載が必要。
- 実験結果の再現性・実施例の具体性が求められる。
- 記載不十分なら無効理由になる(特123条1項3号)。
◆ 試験・実務上の重要性
- 試験では記載要件(特36条)・サポート要件(特36条6項1号)との比較問題が頻出。
- 実務では、明細書作成時に「当業者の技術水準」を意識し、必要十分な実施例を盛り込むことが重要。
◆ 教訓
- 実験例・実施例の数はケチらない。
- 審査・審判・訴訟で致命傷にならないよう、明細書の段階で備えるべき。
💡 知財実務・弁理士試験対策まとめ
| 判例 | 主な論点 | 試験・実務の教訓 |
|---|---|---|
| 日東事件 | 冒認出願、承諾の有無 | 出願時に発明者の承諾確認を徹底。契約書で権利関係を明確化。 |
| キルビー事件 | 職務発明の対価算定 | 発明報奨制度を整備し、発明者に説明責任を果たす。 |
| フェイスクリーム事件 | 新規性喪失例外、手続の厳格性 | 公開管理の社内ルール化、出願→公開の順守。 |
| 医療行為の発明 | 産業上利用可能性の判断 | 医療行為か医療機器かを峻別。クレームの書き方に注意。 |
| 発明の反復可能性 | 明細書の記載要件 | 実施例・実験結果を具体的に記載。審査・訴訟に備える。 |
試験対策としてオススメの判例集
定評のあるものとしては『弁理士試験 判例マスター』『知財判例百選』があります。受験予備校のテキストや講座付属資料も非常に有用です。判例集だけでなく、講義動画や要件整理ノートと併用すると理解が深まります。
✨ 最後に:判例を「生きた知識」にしよう
判例は単なる知識ではなく、法の運用の生きた証です。
試験のために丸暗記するのではなく、「なぜこう判断されたのか」「実務ではどう応用できるのか」を考えながら学ぶことで、理解が一段深まります。
私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。
知財関係の転職をご検討中の方はこちらをご参照ください。