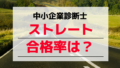この記事は、令和3年度に1年・10万円以下のコストで弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が、実体験をもとに執筆しています。これから弁理士試験を目指す方、知財実務を学びたい方に向けて、特に重要な判例をわかりやすく解説していきます。
弁理士試験に合格するためには、法律条文だけでなく重要判例の理解が不可欠です。また、これらの判例知識は試験合格後の実務、特に特許出願の明細書作成や中間処理、審判対応、訴訟実務などでも役立ちます。この記事では、「プロダクトバイプロセスクレーム」と「用途発明」という2つの重要概念を取り上げ、関連判例を詳しく解説します。
1. 知的財産法・弁理士試験について
知的財産(IP: Intellectual Property)は、発明、デザイン、ブランド、著作物といった人間の創造的活動から生まれる無形の財産です。企業にとって知財は競争力の源泉であり、模倣防止や市場独占、ライセンス収入などの手段として極めて重要です。
日本における知財保護の中核を担う制度が「特許制度」であり、その専門家が弁理士です。弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標の出願代理、異議申立・審判対応、訴訟支援、ライセンス交渉、知財戦略立案などを担います。
弁理士試験は知財の専門家になるための国家試験で、例年の合格率はわずか6〜10%程度と非常に難関です。試験範囲は、
- 特許法・実用新案法
- 意匠法
- 商標法
- 著作権法・不正競争防止法(選択科目)
- 条約
- 民法(短答式のみ)
などに加え、重要判例の理解が強く求められます。
判例知識は条文の単純暗記では対応できない実務的・応用的な問題に強くなるため、特に論文式試験や口述試験、さらには実務で力を発揮します。
私が弁理士試験にかけたコスト・時間・おすすめ講座はこちらにまとめています。
ぜひご参照ください。
2. プロダクトバイプロセスクレーム(Product by Process Claim)
概要
特許法第36条第5項では、特許請求の範囲(クレーム)の記載は「発明が特定できるよう明確に記載しなければならない」とされています。この範囲の記載方式として、物の発明に対し製造方法で特定するのが「プロダクトバイプロセスクレーム」です。つまり、物の発明を「〇〇方法で製造された△△」のように記載します。
通常、物の発明はその構造・組成・物性などで特定しますが、製造方法でしか特定できない場合に限り例外的に認められます。出願人の自由ではあるものの、無制限に認めると権利範囲が不明確になるため、判例上も制限が設けられています。
判例のポイント(平成11(行ケ)437、平成14年6月11日)
以下は判決文の重要抜粋です。
① 発明が物の発明である場合、クレームに製法が含まれていても、そのクレームは物自体を対象とする。したがって、製法部分は物の構成を特定する要件に過ぎない。
② 製法部分の特許性は、物の製造方法としてではなく、あくまで物の構成を特定する要素として評価される。
③ 本来、物の発明は直接的に構造・性質・組成で特定すべきである。製法による特定が認められるのは、構造等では特定できない、あるいは不適切な場合に限られる。
④ 新規性・進歩性の判断も、物の構成を特定する観点から製法要件を評価し、製法そのものの新規性・進歩性を検討する必要はない。
実務・試験の意義
プロダクトバイプロセスクレームは、化学・材料分野で頻出します。製品の微細構造や性質が製造条件に依存し、製造方法を除外すると特定困難な場合に有効です。試験では特許請求の範囲の明確性、新規性・進歩性、サポート要件(特36条6項1号)、実施可能要件(同6項2号)との関係で論点化されます。実務でも無効理由となり得るため、判例趣旨の理解は不可欠です。
知財業務全般については下記で解説をしています。
プロダクトバイプロセスクレームの国際比較・海外判例
プロダクトバイプロセスクレーム(Product-by-Process Claim)は、「製造方法によって特定される製品」に関する特許クレームの形態です。日本日本においては、2009年の最高裁判決(平成17年(行ヒ)第326号、平成21年6月5日判決)で「同一構造・同一特性の製品であれば、製造方法にかかわらず特許権の技術的範囲に属する」という厳格な解釈が確立されました。しかし、海外では国や地域によってプロダクトバイプロセスクレームの取り扱いは大きく異なり、知財実務に携わる者はその差異を十分に理解する必要があります。
アメリカにおける取り扱い
アメリカの特許法(35 U.S.C. §112)では、クレームは「発明を明確に説明し、かつ特定すること」が求められます。プロダクトバイプロセスクレームは、原則として「製品の特性や構造によって特定されるべき」であり、製造方法は製品の特性が不明確な場合にのみ許される補助手段とされています。米国の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、AbbVie Deutschland GmbH & Co. v. Janssen Biotech, Inc.(759 F.3d 1285, Fed. Cir. 2014)などの判例で、「製造方法によって特定された製品は、方法に制限される」との原則を示しています。つまり、米国では日本よりもむしろ方法要素が権利範囲に影響を与える可能性が高い点が重要です。
欧州における取り扱い
欧州特許庁(EPO)の実務では、プロダクトバイプロセスクレームは基本的に「製品の構造や組成によって特定できない場合」に限って認められます(EPC, Article 84およびRule 43(1))。EPO審査基準(Guidelines for Examination)によれば、「製造方法は特許性の基準には影響しないが、権利範囲を明確化する手段として例外的に認められる」とされ、比較的厳格な運用です。欧州の判例としては、T150/82(OJ 1984, 309)が有名で、「製造方法が製品特性を反映する場合に限り、プロダクトバイプロセスクレームは認められる」としています。
日本の実務との相違点
日本の最高裁判例では、製造方法を通じて特定された製品であっても、「製品が同一であれば、他の製造方法による製品も技術的範囲に含まれる」としています。この点が、製造方法に制限されるアメリカや、限定的にしか認めない欧州と大きく異なる特徴です。ただし、日本でもプロダクトバイプロセスクレームは特許法36条6項2号(明確性要件)および29条1項(新規性・進歩性)の観点から厳格に審査されるため、明確な記載が求められます。
国際出願(PCT)時の留意点
プロダクトバイプロセスクレームを含む国際出願を行う際には、各国の実務を十分に理解し、クレームを適切に調整することが不可欠です。例えば、日本で許される「製造方法に依拠する表現」が米国では拒絶理由になるケースや、欧州では不明確とされるケースが珍しくありません。また、国によっては「マルチマトリクレーム」や「パラメータクレーム」との使い分けが重要になります。実務では、現地代理人との綿密な連携が成功の鍵となります。
多国籍企業の知財戦略への示唆
グローバル企業においては、プロダクトバイプロセスクレームをめぐる各国実務の差異を把握し、特許ポートフォリオを最適化することが求められます。例えば、材料系や医薬品系の発明では「プロダクトバイプロセス表現を使うか否か」が国ごとに慎重に判断されます。近年はAI技術やバイオ分野でもプロセスクレームの扱いが問題となっており、知財部門は海外判例や現地実務に精通した弁理士・弁護士との連携を強化する必要があります。
3. 用途発明(Use Invention)
概要
用途発明とは、既知の物質に未知の属性を発見し、その属性によって新たな用途に使用できることを見出した発明です。特に医薬、農薬、食品分野の化学系特許で頻出します。
例えば、「既知の化合物Aが血圧降下剤として作用する」ことを新たに発見し、「血圧降下剤としてのA」として出願する場合です。
判例のポイント(平成10(行ケ)401、平成13年4月25日)
① 「タピオカ澱粉12~15重量%と殻粉類88~50重量%とからなる即席冷凍麺類用殻粉」という発明は、タピオカ澱粉の新たな属性と使用用途に基づく用途発明である。
② 用途発明では、既知物質の未知の属性が発見され、その属性によって適用範囲が従来用途を超える必要がある。
③ 出願前に当該用途が未発見であれば、新規性は否定されない。
④ 新規性判断では、比較対象も用途発明である必要がある。
⑤ 発明の完成性は、反復実施可能な具体性・客観性が必要。
実務・試験の意義
用途発明は新規性・進歩性判断の実務論点として重要です。特に化学・医薬分野で、「用途発明か物の発明か」「医薬用途発明としてのクレーム記載の適否」などが問題となります。
試験では、条文だけでなく、判例を前提とした新規性・進歩性、サポート要件の応用問題が出題されます。また、実務では特許取得後の権利行使(例えば、ジェネリック医薬品との争い)で用途限定の解釈が大きな争点となるため、深い理解が必要です。
4. 判例学習のすすめ方と実務への活かし方
判例学習のコツ
- 要件を抽出する癖をつける
判例文は冗長な場合が多いので、何が論点で何を要件としているかを整理する練習をしましょう。 - 条文と結びつける
判例は必ず条文とリンクしています。条文を確認し、「なぜそのような判断がされたか」を理解することが重要です。 - 具体例に落とし込む
抽象的な要件だけでなく、具体的な事例をイメージできると応用力がつきます。 - 過去問で繰り返し確認
弁理士試験の過去問で実際に出題された判例を確認し、答案構成を練習しましょう。
弁理士試験についての勉強方法についてはこちらにまとめておりますのでご参照ください。
実務への応用
- 出願時のクレーム記載方針の検討
- 中間対応時の拒絶理由通知に対する主張
- 無効審判・訴訟対応時の先例引用
- 社内での教育・指導資料としての活用
試験対策としてオススメの判例集
定評のあるものとしては『弁理士試験 判例マスター』『知財判例百選』があります。受験予備校のテキストや講座付属資料も非常に有用です。判例集だけでなく、講義動画や要件整理ノートと併用すると理解が深まります。
5. 弁理士試験を目指す方へ:私の体験談とおすすめ情報
私は令和3年度に弁理士試験に10万円以下・約1年の勉強で合格しました。一般的には数年・数百万円かかるともいわれる試験ですが、以下の工夫で効率化しました。
- 独学+講座の組み合わせ
独学で基礎を固めつつ、過去問・判例対策は安価なオンライン講座を活用。 - 早期から論文練習
短答対策だけでなく、論文・口述を意識した答案練習を並行。 - 情報発信で理解を定着
ブログやSNSでアウトプットすることで知識が定着。
おすすめ講座・教材、費用の内訳、具体的な勉強スケジュールについては以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
知財関係の転職をご検討中の方はこちらをご参照ください。
6. まとめ
本記事では、弁理士試験や知財実務で重要な判例である「プロダクトバイプロセスクレーム」「用途発明」について詳しく解説しました。
- プロダクトバイプロセスクレーム → 構造等で特定できない物の発明に例外的に認められる。
- 用途発明 → 既知物質の未知属性を発見し、新用途を見出した発明。
これらの判例理解は、試験対策だけでなく、合格後の実務で強力な武器になります。
今後も弁理士試験対策、知財実務、勉強法、キャリア情報などを発信していきますので、ぜひ他の記事もご覧ください。