この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。
弁理士試験に興味を持った方が、まず最初に悩むのはこの点ではないでしょうか?
- 仕事と両立できるのか?
- 独学でも合格できるのか?
- どれくらいの時間をかけるべきか?
- 結局、いつから始めるのがベストなの?
今回は、勉強開始時期と合格までのリアルなスケジュール感を、実際に一発合格した私の体験をもとにお伝えします!
そもそも「弁理士」とは?
弁理士とは、知的財産法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)を取り扱う専門家です。知的財産の権利の取得やライセンス交渉、訴訟の代理などは弁理士の独占業務とされています。
少し簡単な言葉で言うと、特許庁に対して、代理人として特許などの出願をして権利取得を行うことは弁理士にしかできません。
つまり、出願業務などは高度な法律的な知識、手続きに対する専門的知識が必要なため、弁理士試験に合格した弁理士にのみ業務を認めているのです。

法律の知識の無い人が勝手に出願業務とかしちゃうと企業も、特許庁も困っちゃうよね。
弁理士試験のスケジュール【最新版】
弁理士試験は1年を通して行われる長丁場。以下の流れで進みます(※特許庁HPより)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 3月中旬~4月上旬 | 願書提出 |
| 5月中旬 | 短答式筆記試験 |
| 6月上旬 | 短答式 合格発表 |
| 6月下旬~7月上旬 | 論文式(必須・選択) |
| 9月中旬 | 論文式 合格発表 |
| 10月中旬~下旬 | 口述試験 |
| 11月上旬 | 最終合格発表・合格証書発送 |
合格までに必要な勉強時間はどれくらい?
一般的には3000時間が必要と言われていますが、私は約1500時間で一発合格しました。
1日平均6時間 × 週7日 × 約9ヶ月
= 合計 約1500時間
つまり、以下のようなスケジュールで逆算して勉強を始めるのがおすすめです。
| 週あたりの勉強時間 | 必要な期間 |
|---|---|
| 40時間/週 | 約9ヶ月前〜 |
| 30時間/週 | 約12ヶ月前〜 |
短答試験は“記憶勝負”!― 週20時間以下の学習が非効率な理由 ―
短答試験は、知識を「正確に」「素早く」アウトプットする力が求められます。
つまり、限られた選択肢から瞬時に正解を導く「記憶ゲー」に近いとも言えます。
🔍 なぜ記憶が重要なのか?
短答試験では以下のような問題が出題されます:
- 「特許法第30条の規定に基づく例外規定に該当するのはどれか」
- 「無効審判の請求期限について正しいものを選べ」
→ 細かい条文の文言や要件を正確に覚えていないと太刀打ちできません。
週20時間以下で勉強するリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 📉 忘却の罠 | 学習間隔が空くと、記憶が定着せず忘れてしまう |
| 🔁 効率低下 | 忘れた内容を再インプットする時間が余計にかかる |
| 🌀 モチベ低下 | 「また忘れてる…」と挫折しやすくなる |
🧠 人間の記憶は24時間で約70%忘れる(エビングハウスの忘却曲線)
→ だからこそ「毎日繰り返す量学習」が超重要!
| 学習ペース | 9か月で必要な時間 | コメント |
|---|---|---|
| 週40時間 | 約1500時間 | 私の合格時のペース |
| 週30時間 | 約12か月必要 | バランス型、現実的 |
| 週20時間 | 約18か月必要 | 非推奨、記憶効率が落ちやすい |
【完全公開】私の一発合格スケジュール
▶︎ 2020年8月:弁理士に興味を持つ
- 社内研修で知財と出会う
- 特許庁HPやブックオフで知財検定を買って読んでみる
- 公認会計士や税理士とも比較し、弁理士が自分に合っていると判断
✍️この期間は「情報収集と比較」で迷走してました。今ならすぐ講座を始めていたと思います(笑)
ちょうど社内の研修の講師をしてた方が社内弁理士の方でなんとなく興味を持ちました。
このころは本当に軽い気持ちで、特許庁のHP眺めたり、知財検定をブックオフで買ってみたり、各予備校の無料講座を聞いてみたりそのレベルの興味でした。
他にも公認会計士や税理士なども並べて考えてやっぱり理系のバックグラウンド生かせるのは弁理士しかないと感じて弁理士になろうと決意するも、お金が無いので独学で何とかならないのかと考えていました。

今考えるとこの時間は無駄だったね
すぐ弁理士講座に飛びついた方がよかったね~
▶︎ 2020年10月:Studyingの弁理士講座に申し込む
- 決め手は「圧倒的コスパの良さ」
- ここから本格的な勉強スタート!
独学では、無理なことに気づきstudyingの弁理士講座を受講始めました。
理由は安かったからです。正直もう少し早く受けてもよかったなとは思いましたね笑。
このころからなんとなく弁理士試験受かるとかっこいいなというのと知財部に異動してみたいなという気持ちが強くなり始めました。
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)▶︎ 2020年10月〜2021年2月:インプット期
- 平日6時間/休日8時間のペース
- Studyingの基礎講座を3周(約110時間 × 3)
- 問題集は使わず、ひたすら講座を聞き続ける
- 移動中や食事中も音声学習を活用!
🎧通勤やお風呂でも講座を聞いて“知財漬け”の毎日!
とにかく勉強にはまりました。
在宅が多かったのもあり、平日は6時間、休日は8時間くらい講座を聞いてたと思います。
このころは、問題集は買わずにとにかく基礎講座を聞いてました。朝起きたら講座をとにかく講座を付けて、ご飯食べるときもお風呂でも電車の中でも聞いてました。
基礎講座だけで110時間×3周くらいしてましたね。問題演習はstudyingの問題演習講座を解くのみでした。
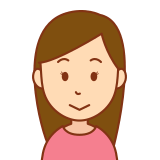
割と講座聞くのが楽しくてずっと聞いてたなあ
▶︎ 2021年3月:アウトプット開始
- 過去問に着手(1日100問が目標)
- 模試は3週間前に受験 → 点数は29点(合格点に届かず…)
- 過去問は最終的に5周繰り返す
そろそろ問題を解かないとまずいことに気づき、過去問を買って1日100問を目標に解きました。
短答試験本番の3週間前に模試を受けて29点くらいでした。過去問解いても結局一回も合格点取れないまま謎のポジティブさで本番を迎えてました笑
ちなみに過去問は、本番までに5周くらい解きました。

とにかく繰り返し勉強したのが良かったかなと思うね。
短答試験対策はこちらをご覧ください。
▶︎ 2021年5月:短答試験本番(45点で合格)
ここまでに1日平均6時間×9か月くらいで1500時間弱くらいは勉強してたかなと思います。
コロナで例年より試験日程が延びたのは私にとってはラッキーでした。あまり自信はなかったですが45点で合格でした。
▶︎ 2021年6月〜7月:論文試験対策
- 休まず論文対策へ突入(短答後の1ヶ月)
- 1日10時間勉強し、問題の写経・答案練習に集中
短答受けた後はちょっと休めという人がいますが、僕はそうは思いません。論文の勉強をできる喜びをぶつけましょう笑
ただここの1か月間は結構追い込みすぎて精神的にも、ちょっときついときもありました。。。それでもとにかく量をこなすことに集中して問題の解答写しまくった1か月間でした。
実質4週間くらいで論文の対策やり切れました。
早く始めるに越したことはないけれど、僕は全然この期間だけで論文試験対策は間に合うと思います。
論文試験対策について知りたい方はこちらをご覧ください。
▶︎ 2021年8月:論文試験受験
手ごたえとしては、大きな失敗はしなかったなといったぐらい。。。時間配分もミスしなかったし、大きな書き漏れも無かったので、あとは祈るのみ。
論文試験後は、もちろん口述試験に向けてある程度の対策をするのが基本ですが、燃え尽きてあんまりこのころは勉強してなかったですね笑
来年は勉強したくないなあと思ってました笑
▶︎ 2021年11月:論文合格発表(平均59.5点)
なんとか合格してました。
結果は平均59.5点で高いのか低いのかも分からず、とにかく安堵といったところでした。急いで口述試験用のテキストを買い、勉強を始めました。
口述試験の模試は各弁理士クラブで開催しているのですが、2回ほど無料で受けました。
ZOOMで行うのですが、こんなことも知らないの?みたいな感じで、試験官役の弁理士の人にはあきれられたりもしましたが、試験までは頑張って勉強しました。
口述試験の対策はこちらをご参照ください。
2021年12月口述試験
- 各団体の模試を2回受験(Zoom)
- 緊張の中でも全問回答し合格を確信!
- 試験官の一人が小泉進次郎似で和んだ(笑)
2022年1月合格発表

やっと正式に合格しました!!
2022年1月~5月 弁理士実務研修
弁理士試験の実務研修も無事終えました。結構長い話になるので、別でまたお話しします。
まとめ:一発合格を目指すなら「逆算して勉強開始時期を決めよう」
- ✍️ 1週間に40時間の勉強なら、短答の9ヶ月前には開始すべし
- ✍️ 30時間/週のペースなら1年前スタートがおすすめ
- ✍️ 短答式は記憶勝負なので、短期集中がカギ!
- ✍️ インプット(講座)とアウトプット(過去問・演習)のバランスが大切
- ✍️ 勉強時間を記録し、PDCAを回すと効果的
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)







