この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。
弁理士試験で最初に当たる壁が短答試験です。令和4年はなんと合格率10.3%でした。
短答試験を攻略するために日々頑張ってる皆さんのために、私の実践していた勉強方法をお教えします。
✅ はじめに:弁理士試験の短答ってどう勉強すればいいの?
弁理士試験を目指す方の中で、最初に大きな壁として立ちはだかるのが「短答式試験」です。
「何から手を付ければいいの?」「暗記量が多すぎて覚えられない…」と悩む方も多いのではないでしょうか?
この記事では、令和3年度弁理士試験に10万円以下の独学で短答を突破した筆者が、実際に行った勉強法・使用教材・スケジュールをすべて公開します!
以下のような方には特に役立つ内容です👇
- 独学で弁理士試験の短答突破を目指している方
- お金をかけずに効率よく勉強したい方
- 初学者でも短答を合格ラインに持っていきたい方
弁理士試験とは?試験スケジュールと概要
まずは弁理士試験全体のスケジュールと構成について簡単に把握しましょう。
弁理士試験の年間スケジュール
| 項目 | 時期 |
|---|---|
| 願書提出 | 3月中旬~4月上旬 |
| 受験票発送 | 5月上旬~中旬 |
| 短答式筆記試験 | 5月中旬~下旬 |
| 合格発表(短答) | 6月上旬頃 |
| 論文式試験(必須・選択) | 6月下旬~7月上旬 |
| 合格発表(論文) | 9月中旬頃 |
| 口述試験 | 10月中旬~下旬 |
| 最終合格発表 | 10月下旬~11月上旬 |
詳細は特許庁の公式ページをご参照ください:
👉 特許庁 弁理士試験概要
私が弁理士試験に合格した際のスケジュールと勉強法についてはこちらで紹介しています。
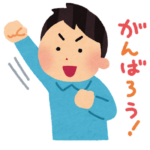
弁理士試験で一番最初に受ける試験になるよ。
例年ゴールデンウィーク明けに試験があるので、ゴールデンウィーク中は死ぬほど勉強するイメージ(笑)
3. 弁理士試験における短答試験の特徴と合格基準
出題科目と出題数
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 特許・実用新案法 | 20問 |
| 意匠法 | 10問 |
| 商標法 | 10問 |
| 工業所有権に関する条約 | 10問 |
| 著作権法・不正競争防止法 | 10問 |
| 合計 | 60問 |
試験方式と時間
- 形式:五枝択一(マークシート方式)
- 試験時間:3時間30分
合格基準
- 総合得点の65%以上が目安
- 各科目で満点の40%未満になると不合格(足切り)
- 科目ごとのバランスも非常に重要

3.5時間連続で試験を受けるのは驚きだよね~
僕は本番も一度手を挙げてお手洗いに行きました(笑)
基礎講座と過去問の使い方【Studying活用体験談つき】
📘 弁理士試験の短答試験対策の基本方針
弁理士試験の短答式試験は、知識の正確性とスピードが問われる難関です。限られた時間で最大の効果を出すためには、「最短ルートで必要な情報を効率よく頭に入れる」戦略が不可欠です。
その戦略の中核を担ってくれたのが、私にとっては Studying(スタディング) の通信講座でした。
ここでは、Studyingを活用しながら進めた勉強方法を時系列で紹介しつつ、過去問との効果的な併用法も詳しく解説していきます。
🎧 基礎講座の視聴は“聞き流し”から始める
弁理士試験の学習は、まず 法律の概要を理解すること から始まります。特許法・意匠法・商標法・実用新案法などは法律用語が多く、最初は何を言っているかすら分からないこともあります。だからこそ、ここで重要なのは「全部理解しよう」とせず、まずは ざっくり“雰囲気を掴む” ことです。
Studyingの基礎講座は、各論点が10~15分単位で細かく区切られており、テンポよく進められる点が非常に優れています。また、倍速機能が0.1倍刻みで細かく調整できるのも魅力です。
私は以下のように段階的に倍速を上げながら、繰り返し聞き流していました:
- 1周目:1.0倍速(理解重視)
- 2周目:1.25倍速(定着)
- 3周目:1.5倍速(総復習)
このように「速度を変えながら複数回聞く」ことで、自然と内容が頭に入っていきました。理解が曖昧な箇所は何度も戻して聞き直し、徐々に“聴いて分かる”レベルに持っていくのがコツです。
🔁 最低でも2周、可能なら3周は聞き流すのがおすすめ!
📦 Studying講座のおすすめポイント
- 価格が圧倒的にリーズナブル
基礎・短答・論文をカバーした総合コースがたったの79,800円(税込)で受講可能。他社と比べてもコスパ最強。 - スマホだけで完結
全講義がオンラインで視聴可能。私は通勤時間や昼休みにスマホで講義を流し聞きしていました。
スキマ時間を最大限に活かせます。 - 学習管理機能が優秀
進捗が自動で記録されるので、学習漏れが起きません。ToDoリスト的に管理できるのが便利でした。
👉 私のStudying講座レビュー記事はこちら:
📚 過去問題集の選び方と使い方(時期別)
【前半:学習初期~試験2か月前】
基礎講座の1~2周目が終わったら、次に取り組むのが「条文順の過去問」です。
おすすめ書籍:
📘『弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集』(早稲田経営出版)
- 条文順に並んでおり、法文集を見ながら問題演習ができる
- 薄くて持ち歩きやすい
- 学習初期の“法文集と仲良くなる”トレーニングに最適
私もこの教材で、「1条→2条→3条…」というように、法文集を片手にコツコツ進めていました。重要なのは、「解けたかどうか」よりも「条文とのつながりを意識しながら問題を解く」ことです。
📝 法文集には気づきをどんどん書き込んで、自分専用の知識データベースにしていきましょう!
書き込み用の法文集はこちらをご利用ください。

僕はこの問題集を本番までに4周はしたよ。
【後半:試験2か月前~本番直前】
基礎が固まってきたら、より実戦的な問題集に取り組みます。
おすすめ書籍:
📕『弁理士試験 体系別短答過去問』(東京リーガルマインド)
- 過去10年分の短答試験を収録
- 特許・実案・意匠・商標で1冊、条約・著作権・不競で1冊
私もこの問題集を4周しました。ポイントは、「確実に覚えた問題は削除していく」こと。チェックマークや色ペンを活用し、徐々に「自分が覚えるべき問題」だけに絞っていきましょう。
✅ この時期は、“精度重視”。間違えた問題には法文集で根拠確認を必ず!
【直前期:試験3週間前~本番前日】
最後の仕上げ期間。新しい知識の詰め込みよりも、「今ある知識の精度と瞬発力」を最大化することに集中します。
おすすめ勉強法:
📘 法文集の通読+直近5年の過去問の再演習
・法文集は「書き込み済み」のものを繰り返し読み込み
・過去問は「一度間違えたもの」「迷ったもの」を中心に絞って復習
・本試験と同じ時間で1セット解く「シミュレーション演習」も効果的
私はこの時期、「全範囲を少しずつ、毎日触れる」ことを徹底しました。1日で全科目にふれるように、分野ごとの代表問題を選んで解くと、試験当日も「どこが出ても対応できる」という安心感につながります。
✅ ポイントは、“抜けをなくす”こと。忘れがちな条文や苦手分野をリストアップして、すき間時間にチェック!
弁理士試験の暗記には語呂合わせを使おう
弁理士試験の暗記すべきことって本当に多いですよね。そんな時は語呂合わせを使いましょう。
下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください。
【模試は“知識の棚卸し”と“本番シミュレーション”の場】
模試は、単なる実力確認にとどまりません。本番に向けた「総合的なリハーサル」として活用すべきです。
おすすめ模試:
📝 LEC全国公開模試
📝 TAC全国公開模試
📝 資格スクエア 模試(オンラインで受験可能)
これらは本番の出題傾向に近い良問が揃っており、問題のクオリティ・分量・難易度ともに信頼できます。
私は本番約1か月前にTacの模試を受け、そこで見つかった弱点(特実の一部テーマ、条約の紛らわしい条文)を重点的に見直しました。
✅ ポイントは、「模試の後の復習が本番の点数に直結する」こと。
模試で間違えた問題は必ず根拠条文までたどり、「なぜ間違えたか」「今後どう防ぐか」をメモしましょう。模試の点数に一喜一憂するのではなく、「得点源と失点源を可視化するツール」として活用してください。
さらに、本番に向けては「解く順番」「時間配分」「マークミス対策」などの戦略面も模試で試行錯誤しておくと安心です。
模試の体験については、こちらをご覧ください。
【要注意!短答対策でやりがちな間違い】
短答試験では、以下のような「ありがちな落とし穴」に注意が必要です。
❌ 「暗記中心」で進めてしまう
→ 条文や知識を“丸覚え”しようとすると応用が効きません。根拠と理由を理解して覚えることで、応用問題やひっかけにも対応できます。
❌ 過去問を1回しか解かない
→ 短答は“記憶の競技”です。最低3回以上の反復で「この選択肢は○/×」が瞬時に判断できるようになるのが理想。
❌ 模試の点数に一喜一憂して終わる
→ 点数より大切なのは「何を間違え、なぜ間違えたか」です。模試は分析ツールとして使い倒しましょう。
❌ 条文を軽視する
→ 意外と多いのが、「過去問は解けるけど条文を引いたことがない」状態。短答は条文ベースの出題が中心なので、法文集で裏を取る癖をつけましょう。
短答試験でやりがちな間違いについてはこちらでご紹介しています。
【まとめ:短答試験対策は“量より質”の戦略で】
弁理士試験の短答対策では、「膨大な範囲をいかに効率的に、確実に固めるか」がカギになります。
高得点を狙う必要はありません。合格ラインを着実に超えるために、次の3点を意識しましょう。
- 基本書・講座で知識の土台をつくる
- 過去問で出題傾向とパターンを体にしみこませる
- 模試や直前期の演習で弱点補強と本番シミュレーション
そして何より大切なのは、「今の自分にとって必要な学習に集中すること」。
すべてを完璧にやろうとせず、「取捨選択」と「繰り返し」によって、合格に必要な知識だけを最短距離で積み上げていきましょう。













