弁理士試験の勉強を始めた方なら誰もがぶつかるのが「条文の暗記の壁」ではないでしょうか。
特に、パリ条約やPCT(特許協力条約)は条文が抽象的で文章も長く、短答式試験では数条の知識が問われるにも関わらず、内容を正確に理解・記憶しておくのが非常に難しい分野です。
本記事では、令和3年度に費用10万円以下&1年の独学で弁理士試験に合格した現役企業知財部員である筆者が、自らの受験体験を踏まえて活用した語呂合わせ・記憶術をご紹介します。
「覚える時間が惜しい」「語呂を考える時間すら惜しい」そんな方のために、即使える語呂合わせ集+実践的な勉強法+おすすめ法文集まで網羅的にお届けします。
なぜ語呂合わせが弁理士試験に有効なのか?
弁理士試験は短答・論文・口述と三段階に分かれており、どのフェーズでも「条文の正確な理解と記憶」が求められます。
特に短答では、条文の逐条知識が問われるため、
- 数字(期間)
- 要件(項目)
- 条文構造(号や項の関係)
を正確に暗記する必要があります。
語呂合わせは、こうした「記憶のハードル」を下げてくれる非常に強力なツールです。
メリット:
- 意味が分からなくても響きで覚えられる
- 難解な文章もリズムで記憶に残る
- 思い出しやすくなる(口述対策にも◎)
デメリット:
- 語呂だけで覚えると意味理解が疎かになる
- 人によって合う合わないがある
語呂合わせは「暗記を補助するツール」であり、「理解を代替するものではない」ことを念頭に置いて活用することが大切です。
短答試験対策についてはこちらでご紹介しているのでこちらもご参照ください。
【パリ条約】短答対策のための語呂合わせまとめ
第1条(2):「とくじついしょうさごうげんげんふ」
元の条文:
「本条約において、工業所有権とは、特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、原産地表示又は原産地名称、不正競争の防止に関するものをいう。」
語呂:「とくじついしょうさごうげんげんふ」
【分解】
ふ=不正競争防止
とく=特許
じつ=実用新案
い=意匠
しょう=商標
さ=サービスマーク
ごう=商号
げんげん=原産地表示・原産地名称
リズムがよく、音読しながら口に出すと覚えやすい定番ゴロ。
第2条(3) 内国民待遇と手続き等
元の条文(一部要約):
「内国民待遇の原則に基づき、締約国の国民には司法上及び行政上の手続に関しても同一の待遇が与えられる。…また住所の選定または代理人の選任を求められることがある。」
語呂:「しさいじゅうだい」
- し=司法上
- さ=行政上
- い=手続
- じゅう=住所の選定
- だい=代理人の選任
解説:
条文の構成を漢字の頭文字で整理した語呂です。「手続関係」の要素として短答でも問われやすく、「誰にどこまで求められるか」を把握するのに便利です。
第4条C(4) 優先権の取り下げ等
元の条文(一部要約):
「最初の出願が撤回、放棄、拒絶された場合であっても、その出願がまだ公開されていなければ、優先権の主張は可能。」
語呂:「どうどうえつけんさげききょゆう」
- どう=同一
- どう=同盟国(=同盟締約国)
- え=延長不可
- つ=通知
- けん=権利
- さげ=出願の「下げ」(撤回・放棄)
- き=拒絶
- きょ=拒絶
- ゆう=優先権
解説:
語呂自体が複雑ですが、記憶すべきは「取り下げや拒絶があっても、一定条件で優先権は有効」。語呂で無理やり覚えるよりも、「優先権の存続条件」が記載された条文であることと併せて記憶するのがポイントです。

これは定番で有名だよね~
第6条の5(2) 本国の定義
元の条文:
「本条にいう本国とは、営業所、住所、国籍の順に優先して判断する。」
語呂:「営住国(えいじゅうこく)」
- 営=営業所
- 住=住所
- 国=国籍
解説:
パリ条約では出願の「本国」が重要になりますが、その決定ルールを順番付きで簡略化したものです。「営」が最も優先度が高く、なければ次に「住所」、それもなければ「国籍」を見るという構造になっています。
【PCT条約】語呂合わせと記憶のコツ
第11条(1)(iii):「しげいてしめせ」
元の条文(一部要約):
(1)受理官庁は次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(ⅰ)出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
(ⅱ)国際出願が所定の言語で作成されていること
(ⅲ)国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
(a)国際出願をする意思の表示。
(b)少なくとも一の締約国の指定
(c)出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d)明細書であると外見上認められる部分
(e)請求の範囲であると外見上認められる部分
語呂:「しげいてしめせ」
出願に必要な要素:資格、言語、意思、締約国、氏名、明細書、請求項の7要素
し=資格/げ=言語/い=意思/て=締約国/し=氏名/め=明細書/せ=請求項
解説:
国際出願が有効になるための7つの要件。この語呂は「短答定番」の内容です。
理解のためには、「何がなければ出願日が与えられないのか?」という観点で記憶すると効果的です。
第14条 国際出願の欠陥
元の条文(一部要約):
「国際出願の方式的欠陥として、署名の欠如、発明者・出願人情報の欠如、発明の名称、要約の欠如などが挙げられる。」
語呂:「しょめいがんじんはつようよう」
- しょ=署名
- めい=名称(発明の名称)
- がん=願書
- じん=出願人
- はつ=発明者
- よう=要約
- よう=様式
解説:
PCTにおいて「欠陥」とみなされる項目の代表例です。欠けていたら出願日が認められなかったり、修正が求められたりするものばかり。試験では「どの欠陥が致命的か」を問う選択肢で登場します。
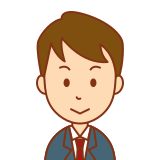
意味は不明だけど、響きはなぜか頭に残る感じね。。
第42規則 国際調査のための期間
内容:
国際調査報告書は、「国際出願日から3か月」または「優先日から9か月」のうち遅い方までに作成される。
語呂:「調査は削減(3・9)」
解説:
「さくげん」という語感で「3と9」を覚える。短答で問われる場合、「どちらか早い方か遅い方か?」という点に注意が必要です。
第46規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
内容:
国際公開から2か月以内、または優先日から16か月以内のいずれか遅い日までに補正可能。
語呂合わせ:「虹色(にじいろ)=2・16の19条補正」
解説:
「に=2」「じいろ=16」の語呂で補正期限を暗記します。「19条補正」の期限として重要な暗記事項です。
第54規則の2 国際予備審査の請求をするための期間、69.2 国際予備審査までの期間
内容(一部要約):
- 審査請求の期限:調査報告から3か月 or 優先日から22か月(早い方)
- 審査報告の提出期限:優先日から28か月または請求日から6か月(遅い方)
語呂合わせ:「サニブラウン、日本ハム入団」
- サ=3か月(調査報告後)
- ニブラウン=22か月(優先日)
- 日本=28か月(報告期限)
- ハム=6か月(請求日から)
解説:
4つの数値(3・22・28・6)を1つのストーリーでまとめた語呂。試験でこの数字の比較が問われやすい箇所です。
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(ⅰ)優先日から28か月(日本ハムの28ですね。)
(ⅱ)69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6か月(日本ハムの6ですね。)
(ⅲ)55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査期間が受理した日から6か月(日本ハムの6ですね。)
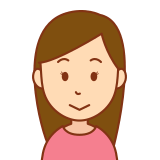
昔、陸上選手で代走専門でプロ野球に入団した人いたらしいよ~
よくある質問(FAQ)
Q1. 語呂合わせは弁理士試験対策として本当に有効なのでしょうか?
A. 語呂合わせは、単なる暗記ではなく「記憶のフック」として機能する高度な学習補助技法です。特に、条文番号と要件・効果などの構造的記憶が求められる弁理士試験において、語呂を用いた情報の圧縮と即時想起の手段として有効です。ただし、語呂に依存しすぎると理解の浅い記憶に留まる可能性があるため、語呂=入口、理解=出口という認識で活用すべきです。
Q2. 語呂合わせを使うことで論文式試験にも対応できますか?
A. 語呂合わせ自体は論文式試験の直接的な解答力に直結するものではありませんが、条文構造を素早く再現できる点では有効です。論文では条文の趣旨や要件の的確な説明が求められますが、前提として記憶に条文の正確な骨格が定着していることが必要です。語呂はその構造記憶を支える補助として機能します。つまり、語呂だけでは不十分ですが、適切な知識運用の基盤となり得ます。
Q3. どのような条文が語呂化に適していますか?基準はありますか?
A. 語呂化に適した条文には共通点があります。主に以下のような特性を持つ条文です:
- 数字や期限が含まれる(例:審査請求期間、損害賠償の時効)
- 複数の構成要件が列挙されており、順番が重要(例:新規性喪失の例外、優先権)
- 他法域と比較して似た構造を持つが、要件が異なる(例:特許法と意匠法の無効理由)
このような条文は、理解だけでは記憶があいまいになりやすいため、語呂で構造を固定化することが有効です。
Q4. 語呂を使った学習が本試験でどのように活きるのでしょうか?
A. 実際の短答式試験では、限られた時間の中で複数肢を迅速に判断する必要があります。語呂が活きるのは、「条文の正確な構造を即座に思い出し、正誤判定の判断材料とする場面」です。特に、条文番号とセットで覚えている語呂があると、根拠に基づいた消去ができ、解答の精度が向上します。また、記憶の曖昧さが生じた際にも、語呂が補助的に記憶を呼び戻す役割を果たします。
弁理士試験勉強方法 語呂合わせの使い方
語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。
書き込みをするなら四法横断法文集がオススメです。書き込みのためのスペースが広く、まだ買われてない方は購入されてはいかがでしょうか

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。
その他の分野の語呂合わせ
下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください。
最後に
いかがだったでしょうか?本日はパリ条約、PCTのゴロ合わせを紹介してみました。ぜひぜひ使ってみてください。
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)










コメント