この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。
本日は弁理士試験を受けて弁理士になるメリット、デメリットについて語っていきたいと思います。
そもそも全く別の仕事をしていて弁理士という資格に興味があるけど、周りになかなか弁理士になった人がいない。。。僕もそうでした。そういった人の参考になれば幸いです。
「弁理士」ってどんな資格?
まずは簡単に弁理士資格について説明します。
弁理士とは、知的財産(特許・意匠・商標など)の専門家であり、特許庁に対して代理人として出願業務を行ったり、ライセンス契約・訴訟対応など、知財に関するあらゆる法的支援を行う職業です。
弁理士には以下のような独占業務があります。
- 特許出願や中間処理(補正・意見書など)の代理
- 審判請求・無効審判などの手続き
- 知財関連のライセンス契約支援
- 一部の訴訟代理(特定侵害訴訟代理業務)
要するに、「知財法+技術+ビジネス」を融合させるプロフェッショナルなんです。
なぜ僕が弁理士を目指したのか?
正直に言うと、僕も最初は「弁理士ってなんか難しそうだし、周りに受かった人いないな…」と思ってました。
でも、ある日ふと考えたんです。
「せっかく理系のバックグラウンドあるし、社会人として“武器になる資格”が欲しいな」
そこから少しずつ勉強を始め、結果的に約1年、10万円以下という最小限のコストで合格することができました。
弁理士になる6つのメリット
① キャリアの幅が一気に広がる!
これは本当に実感しています。僕はもともとメーカーの開発部にいましたが、「弁理士試験に挑戦したい」と公言したことがきっかけで、社内の知財部に異動することができました。
弁理士資格があると、
- 特許事務所への転職が現実的に可能
- 大手企業の知財部でも即戦力として評価される
- 将来的な独立・起業という道も見える
実際に僕の周りでも、弁理士資格を活かして自分の興味ある業界に転職した人が多数います。
弁理士資格を生かした転職については下記でご紹介していますのでご参考にしてください。
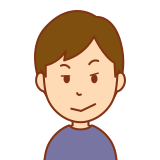
将来的に特許事務所に勤務したり、興味ある分野の企業に転職するのもありかなって思ってるよ。
②「どこでも働ける」という安心感が手に入る
弁理士資格は国家資格であり、全国どこでも通用します。特に近年は、スタートアップや海外企業との知財連携も増えているため、知財の専門性はますます求められています。
「この会社がダメでも、他に行ける」というキャリアの安心感は、精神的にもかなり大きな支えになります。

弁理士資格を取って強気で興味あるベンチャーに就職する人は最近よく聞くね。
一つの会社に依存するより、その時々にあった好きなことをし続ける人生目指したいよね~
③最新の技術に毎日触れられる!
知財の仕事って、「最先端の技術」を一番最初に知る仕事なんです。
特許出願の内容って、まだ製品化されていない段階の技術も多くて、「未来の技術を先取り」している感覚があります。
僕は技術オタクではないんですが、それでもこの仕事をしていると自然と学びのモチベーションが上がるので、勉強好きな方には本当におすすめです。
④自分のペースで働ける自由さ
弁理士や知財の仕事はかなり個人プレイです。
リモートワークがしやすい職種であり、僕も週1回出社する程度で、あとはほぼ在宅勤務。朝ジムに行ってから仕事したり、夕方には仕事を切り上げて趣味を楽しんだり、フレキシブルな働き方が可能です。
ある先輩は、「朝6時から仕事して、午後3時には終わる生活」をしていて羨ましかったですね。
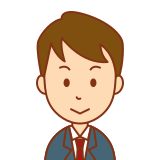
僕は毎日ジムに行ってから仕事をしているよ。前回出社したのは2か月前かな笑
⑤人脈が広がる!
弁理士になると、同業者同士のつながりが一気に増えます。
- 弁理士会のイベント
- 知財関連の勉強会・講演会
- 合格者限定の交流会や飲み会
こういった場に参加することで、特許事務所や企業の知財部の実情、フリーランス弁理士の話など、普段聞けない情報をたくさん得ることができます。
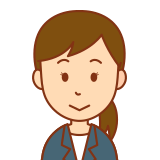
弁理士になってたくさん飲み会に参加して、人脈を広げていこう!
⑥評価・待遇が上がる!
これは特許事務所だけでなく、企業内でも確実に変化がありました。
僕の場合、
- 同期よりも早く役職がついた
- 弁理士登録費用を会社が全額負担
- 開発部署の人から一目置かれるようになった(笑)
資格を取った瞬間に、「この人、専門家なんだ」という空気感が社内で生まれるのも不思議なところです。
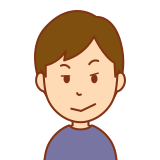
弁理士資格を取ってから、開発部署の人が話をよく聞いてくれるようになったよ(笑)
弁理士資格を取るデメリット
もちろんメリットばかりではありません。現実的なデメリットもお伝えします。
①時間とお金がそれなりにかかる
一般的には、
- 学習時間:約3,000時間
- 費用:約100万円
と言われています。正直、片手間では無理です。
でも僕は、最短ルート+費用を徹底的に抑えた方法で、10万円以下で合格できました。そのノウハウは今後の記事でも詳しくシェアしていきます。
▶ 実際の勉強スケジュールはこちら
②最後まで合格しないと評価されにくい
TOEICのように「途中経過の点数」で評価される資格ではありません。
- 短答試験だけ合格 → あまり評価されない
- 論文までいっても口述で落ちる → 資格として意味がない
なので、「受けるからには絶対最後までやり切る覚悟」が必要になります。将来のキャリアや人生設計と向き合いながら進めることをおすすめします。
最後に:このブログで伝えたいこと
私は現在、30歳、社会人5年目の企業内弁理士です。もともと開発職でしたが、29歳で知財に興味を持ち、独学で勉強を始め、1年で弁理士試験に合格しました。
正直、決して楽な道ではありませんでしたが、振り返ると「やってよかった」と心から思えます。
このブログでは、同じように迷っている人、興味があるけど一歩踏み出せない人に向けて、
- 最短合格法
- おすすめ教材
- 働きながらの勉強術
- 知財業界のリアル
などをどんどん発信していきます。
弁理士は、人生を自分の力で切り開いていける資格です。
ぜひ一緒に、知財の世界を楽しんでいきましょう!

他にも筋トレとか英語とか趣味があったりするよ。プロフィールのページも見てコメントとかもらえるとうれしいな。
まとめ
弁理士試験を取るメリットは?
- キャリアの幅が広がる
- どこの企業でも働ける安心感
- 最先端の技術に触れられる
- 自分のペースで働ける
- 人脈が広がる
- 評価・待遇が上がる
デメリットは?
- 時間とお金がかかる
- 最後まで合格しないと評価されない
「やってみたいかも」と思ったら、それが一歩目。
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)






コメント