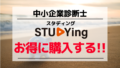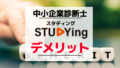この記事は、令和3年度にわずか10万円以下、勉強期間約1年で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が、実体験をもとに執筆しています。
弁理士試験の最初の壁である短答式試験は、毎年多くの受験生が苦戦する関門です。
令和4年度の短答式試験の合格率はわずか 10.3% という狭き門。
今回は、短答試験合格を目指して頑張っている皆さんに向けて、 やりがちな間違い・落とし穴 を徹底解説します。
さらに、この記事では以下の内容も網羅します。
✅ 弁理士試験・短答式試験の概要とポイント
✅ 合格に必要な勉強時間とスケジュール
✅ 短答試験の具体的な対策・おすすめ教材
✅ やりがちな間違いとその改善策【10選】
✅ 合格後のキャリア・知財部の仕事内容
これを読めば、短答式試験の合格への道筋がはっきりと見えてきます。
【はじめに】弁理士試験・短答式試験とは?
弁理士試験は、知的財産権(特許、商標、意匠など)の専門家である弁理士になるための国家試験です。試験は以下の3段階に分かれます。
- 短答式試験(マークシート方式・60問)
- 論文式試験(記述式)
- 口述試験(面接形式)
特に短答式試験は、論文式試験の受験資格を得るための「足切り試験」であり、ここを突破しないと次に進めません。
主に法律の条文知識・判例・実務の理解が問われるため、暗記力と理解力の両方が必要です。
弁理士試験全体についてはこちらで詳しく紹介しています。
【背景】短答式試験の合格率と難易度
令和4年度(2022年):合格率10.3%
令和3年度(2021年):合格率15.7%
令和2年度(2020年):合格率19.7%
年によって多少の変動はあるものの、例年 10~20%前後の合格率 で推移しています。
つまり、10人に1~2人しか合格できない狭き門です。だからこそ効率的な学習戦略が重要です。
【合格のための目安】勉強時間とスケジュール
短答試験合格までの目安時間は 800~1200時間 と言われます。
社会人の場合のモデルスケジュールは以下の通り。
- 半年間(基礎固め):基礎講座・法文集の精読、300~500時間
- 4か月間(問題演習):過去問・模試・演習、400~600時間
- 直前1~2か月:全科目の総復習・模試、100~200時間
短期集中型が有利な試験であるため、1~1.5年で一気に駆け抜けるのが理想です。
実際の弁理士試験のスケジュールについては下記の記事をご参照ください。
短答式試験でやりがちな間違い7選
① 間違えた問題だけを繰り返し解く
一見、間違えた問題を重点的にやり直すのは効率的に見えます。しかし、これは 「忘却曲線」を無視した危険な方法 です。
人間は学習後、1日で約70%の情報を忘れ、1週間後には90%を忘れると言われています。つまり正解した問題も放置すれば忘れていきます。
対策:
- 正解・不正解に関わらず、定期的に全範囲を復習
- 直前期は1日で全科目に触れる「バランスよく勉強」を実践
- ノートやチェックリストを作り、周期的に全範囲を回す

そういえば、大学受験の時に問題集を破って二度と解かなくてもよいくらいの覚悟で暗記しなきゃいけないって先生が言ってたなあ。
② 基礎講座を1回見ただけで過去問に突入
基礎講座は1回では定着しません。
「法律の全体像」や「趣旨」を3回は繰り返し視聴し、全体のつながりを頭に入れるべきです。1回目でわからなかった部分は2回目・3回目で腑に落ちます。
対策:
- 1回目:1倍速で基礎理解
- 2回目:1.25倍速でつながり確認
- 3回目:1.5倍速で定着確認
過去問に進むのは基礎が完成してから。基礎が曖昧な状態で過去問に挑むと、解答解説が意味不明で挫折します。

1回目は1倍速、2回目は1.25倍速、3回目は1.5倍速で聞くようにするといいよ!
私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)③ 「記念受験」や2年計画に逃げる
今年は記念受験だから…という逃げは危険です。
なぜなら短答式試験は記憶勝負の側面が強く、短期集中の方が記憶が維持されやすいからです。
対策:
- 半年間で基礎講座を完成
- 直後の4ヶ月で過去問・答練を全力投入
- 本番は「今年絶対受かる」という覚悟で挑む
覚悟の有無は、勉強効率・集中力に直結します。

厳しい言い方だけど記念受験とか言ってる人は一生受からないと思う。
④ 捨てる科目を作る
捨てる科目を作ってはダメです。そもそも短答試験は下記のような合格基準点があります。
合格基準
総合得点の満点に対して65%の得点を基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、科目別の合格基準を下回る科目が一つもないこと。なお、科目別合格基準は各科目の満点の40%を原則とする。
合格点:39点(例年39点です。)
科目別合格基準点
特許・実用新案に関する法令 8点
意匠に関する法令 4点
商標に関する法令 4点
工業所有権に関する条約 4点
著作権法及び不正競争防止法 4点
よく不正競争防止法は簡単だから、満点を取って著作権法は捨てても良いという方がいますが、それはオススメしません。
年によって難易度は変わりますし、そうやって捨て科目を作ると例えば不正競争防止法で満点を取らないといけないという変なプレッシャーがかかってしまいます。
均等に勉強した上で大体、特許法6~7割、意匠法9割、商標法9割、条約5~6割、著作権及び不競法5~6割の合格点を目指すべきかなと思います。

もちろん、特許法、意匠法、商標法に対して重点を置くというのは、配点の面からも論文試験へつながるという面からも必要だよ。
⑤法文集へ書き込みをしない
はい、特に四法横断法文集(早稲田経営出版、TAC弁理士講座 編著)を使って空いているスペースに、どんどん書き込みをしていきましょう。
問題集を解いたりすると、何度も条文を引くことになります。そのたびに条文の周りに書いてあることが目に入ります。その際に重要なところをマーカーしたり、語呂合わせなどを書いたり、条文に書いてない施行規則などを書いておくと一緒に覚えることができます。
例えば、特許異議申し立てのページを四法横断法文集で開くと特許法と商標法にしか特許異議申し立てが無いことが分かります。
例えば、特許法は公報発行日から6か月であるのに対し、商標法は2か月であることが分かります。こういったところは、必ずマークしときましょう。
ちなみに下記が短答に必須の四法横断法文集です。
弁理士試験 四法横断法文集 (TAC弁理士講座)
毎年細かい法改正が行われているので、ケチらずに最新のものを買うようにしましょう。
弁理士試験に必要な参考書はこちらの記事にまとめています。

僕は勝手にこじつけて、商標法は商標登録の瑕疵を見つけやすい(特許法は発明の把握に時間がかかる)から。って書いてたよ。記憶の定着につながることは何でも書いとこう。
⑥ 問題演習の質より量を重視する
「1日何問解いたか」にこだわりすぎ、解説を読み込まないのはNGです。
対策:
- 問題演習の後、必ず「なぜそうなるか」を確認
- 選択肢ごとに○×理由を説明できるようにする
- 解けた問題でも、解説は精読する
⑦ 難問・奇問に執着する
過去問には毎年のように「誰も解けない問題」が紛れています。これに時間を費やすのは非効率です。
対策:
- 過去問10年分の中で頻出論点を優先
- 難問は「解けたらラッキー」で割り切る
- 基礎と標準問題を完璧にする
まとめ
短答式試験は確かに難関ですが、正しい勉強法とマインドセットで乗り越えられます。
この記事の「やりがちな間違い」を徹底回避し、短期集中で合格を勝ち取りましょう。
私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。