弁理士試験の受験生にとって、判例の学習は避けて通れない重要なポイントです。特に化学分野の発明に関する判例は、覚えるべき要件や判断基準が他の技術分野と異なるため、しっかり理解しておく必要があります。
この記事では、実体験を踏まえ、重要判例をわかりやすく解説します。また、これらの知識が実務でどのように役立つのかも具体的に紹介します。
はじめに:弁理士試験と判例の重要性
弁理士試験に合格するためには、単に条文や審査基準を暗記するだけでなく、判例の理解が欠かせません。判例は、試験問題の背景にある考え方を理解し、応用力を養うのに役立ちます。
また、企業知財部や特許事務所での実務でも、判例の知識は大きな武器になります。発明の内容を評価したり、出願戦略を立てたり、拒絶理由通知への対応方針を考える際、判例に基づく考え方が非常に重要だからです。
特に化学分野の発明は、機械や電気の分野と比べて特有の厳しい要件が課されるため、判例を通じてその背景を理解しておくことは必須です。
弁理士論文試験の「法の概要・趣旨問題」対策法についてはこちらで詳しく解説しています。
化学に関する発明①:実施例の必要性
概要
化学分野の発明では、単なるアイデアや構想だけでは発明として認められません。実験に裏付けられた実施例が必要であるとするのが基本的な考え方です。

機械の分野などは、結構アイデア発明とかいっぱいあるけど化学はだめなんだよね~
判例の内容(昭和43(行ケ)132、昭和52年1月27日判決)
- ①化学反応の特性
- 従来知られている反応を基に、原料から所望の化合物を得る過程を化学式で表すことは比較的容易。
- しかし、書いた通りに反応が進むとは限らない。原料を混ぜるのは人為的にできても、その後の反応は自然法則に委ねられるため。
- ②実験の必要性
- 化学反応は、実際に試してみなければ進行するか不明。
- だからこそ「化学は実験の科学」といわれる。
- ③明細書の記載要件
- 明細書には、実験を行ったことを証明する資料が必要。
- 実施例は最も適切な資料で、これに代わるものがなければならない。
実務への応用
特許明細書を作成する際、化学分野では必ず実施例を充実させることが求められます。逆に言えば、実施例が不足していると、出願段階で補正や拒絶理由の対象となるリスクがあります。実務家はこの判例を踏まえ、発明の有効性を担保する記載を意識しなければなりません。
知財業務全般については下記で解説をしています。
化学に関する発明②:合金発明の性質・用途の開示
概要
合金に関する発明では、単に元素の割合を記載するだけでは不十分です。その合金の性質や用途まで開示する必要があります。

合金の組成って限られているから適当な組成でたくさん出願されちゃうと困っちゃうよね~
判例の内容(昭和55(行ケ)176、昭和58年11月16日判決)
- ①元素の組み合わせの限界
- 合金は既知の元素の組み合わせで成り立つため、組成の範囲が限られる。
- ②完成された発明の要件
- 単に組成比を記載するだけでは発明として成立しない。
- 性質(例:耐食性、硬度)や用途(例:航空機材料、電子部品)を明らかにすることが必要。

どちらかというと実務に役立つ判例だね。受験生はそういう判例もあったなぐらいの認識で良いと思います。
実務への応用
特許実務では、出願書類において合金の性能評価や用途例を漏れなく記載することが重要です。この判例を知らないと、記載不備で特許要件を満たさずに権利化に失敗するおそれがあります。例えば、単なる組成記載では拒絶されやすいことを念頭に置き、技術的効果を明確化する工夫が必要です。
化学に関する発明③:有用性の開示
概要
化学物質発明では、「産業上の利用可能性」、すなわち有用性の開示が必須です。有用性がなければ、発明として成立しないとされます。
判例①(平成2(行ケ)243、平成6年3月22日判決)
- ①有用性の必要性
- 産業上利用できることが必要。
- 化学物質の性質は構造から予測困難で、実際に試験しなければ確認できない。
- ②明細書での有用性の開示
- 製造や構造記載だけでは不十分。
- 実験データや既存試験から有用性を示す必要がある。
判例②(平成13(行ケ)219、平成15年1月29日判決)
- 化学物質発明の本質は「新規で有用な化学物質の提供」であり、単に存在が確認され、製造可能なだけでは足りず、有用性が開示されていなければならない。

化学物質の発明は、総じて結構要件が厳しいことが分かるね~
実務への応用
有用性の記載漏れは、特許審査での拒絶理由の定番です。実務では、用途例や実験データを可能な限り多く盛り込むことが推奨されます。弁理士はこの点を開発者に積極的に確認し、不足があれば早期に補足データを用意する段取りを整えましょう。
判例の覚え方と試験対策
化学分野の判例は細かく難解ですが、以下のポイントを押さえて効率的に学習するのがおすすめです。
- キーワード学習法
→ 実施例、性質・用途、有用性という3本柱をまず押さえる。 - 条文とリンクさせる
→ 明細書記載要件(36条)、産業上の利用可能性(29条)との関係を意識。 - 実務事例と結びつける
→ 勉強だけでなく、実務で見た案件を思い出して判例を復習。 - 過去問・答練で繰り返し確認
→ 判例知識は論文試験・口述試験でも問われるので、何度も繰り返す。
弁理士試験の論文対策にはStudyingの弁理士講座が最適です。私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。
【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)実務でのトラブル・失敗談から学ぶ!知財担当者・弁理士のリアルな現場
弁理士試験に合格したあと、知財実務の現場では試験では学ばない“生きた知識”が求められます。ここでは、化学分野の出願で私が実際に見聞きした失敗談をいくつかご紹介します。受験勉強にも実務にも役立つので、ぜひ参考にしてください。
【ケース1】実施例不足で拒絶理由を受けた出願
ある化学系メーカーが新規合成法に関する特許を出願したケースです。明細書には理論的な化学式や反応式が詳細に書かれていましたが、実験データはわずか1例だけ。それもスケールが小さく、再現性が不明でした。
審査段階で特許庁から「実施可能要件を満たさない」として拒絶理由通知が届き、担当弁理士は大慌て。結局、追加実験を行い、データを提出する補正書を作成しましたが、時間と費用が大幅にかかってしまいました。
このケースの教訓は、「実施例は最低限の数ではなく、発明の再現性・汎用性を示せる内容を準備すること」。受験生の勉強でも、なぜ実施例が重要かを実務的な視点で意識すると理解が深まります。
【ケース2】性質・用途の記載漏れで補正が難航
合金に関する出願で、組成比率だけを詳細に記載した明細書が提出されました。しかし、実は発明の核心は「耐熱性の向上」や「腐食耐性の改善」といった性質にありました。
ところが、これらの性質や用途が明細書に明示されていなかったため、審査で「完成された発明とはいえない」と指摘されます。補正で性質や用途を追加しようとしましたが、新規事項追加と見なされるおそれがあり、結局、分割出願で対応せざるを得ない事態に。
実務では「組成や構造を追うだけでなく、どのような技術的課題を解決し、何に役立つかを明記する」ことが極めて重要です。弁理士試験では一見知識問題のように見えますが、実際は明細書作成や出願戦略に直結する内容だと知っておきましょう。
【ケース3】有用性データ不足で追加実験を急ぐ羽目に
新しい化学物質の特許出願では、「この物質が何に使えるのか」が明細書にしっかり書かれている必要があります。ある企業では、化学構造の斬新さにばかり注目し、有用性の説明をおろそかにしたまま出願してしまいました。
審査で「有用性が確認されていない」と拒絶理由が届き、追加データの提出が必要になりました。しかし、追加実験には数か月かかり、海外出願の期限にも間に合わない可能性が出てきます。結果として、権利化までのスケジュールが大幅に遅れ、海外出願も一部断念することに。
このように、有用性データの準備はスムーズな権利化のための鍵です。試験勉強でも、単なる暗記ではなく、「なぜ有用性が問われるのか」「どうすればそれを立証できるか」を意識することで、学習効果は格段に上がります。
試験対策としてオススメの判例集
定評のあるものとしては『弁理士試験 判例マスター』『知財判例百選』があります。受験予備校のテキストや講座付属資料も非常に有用です。判例集だけでなく、講義動画や要件整理ノートと併用すると理解が深まります。
最後に
今回は、弁理士試験や実務に役立つ重要判例として、化学分野に関連するものを紹介しました。
受験生の方は、細かく丸暗記するのではなく、「化学分野は要件が厳しい」という全体像を理解した上で、各要件の具体的内容を抑えるのが効率的です。
また、実務家の方は、明細書記載や出願戦略の際にこれらの考え方を応用することで、より強い特許を取得しやすくなるでしょう。
私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。
知財関係の転職をご検討中の方はこちらをご参照ください。


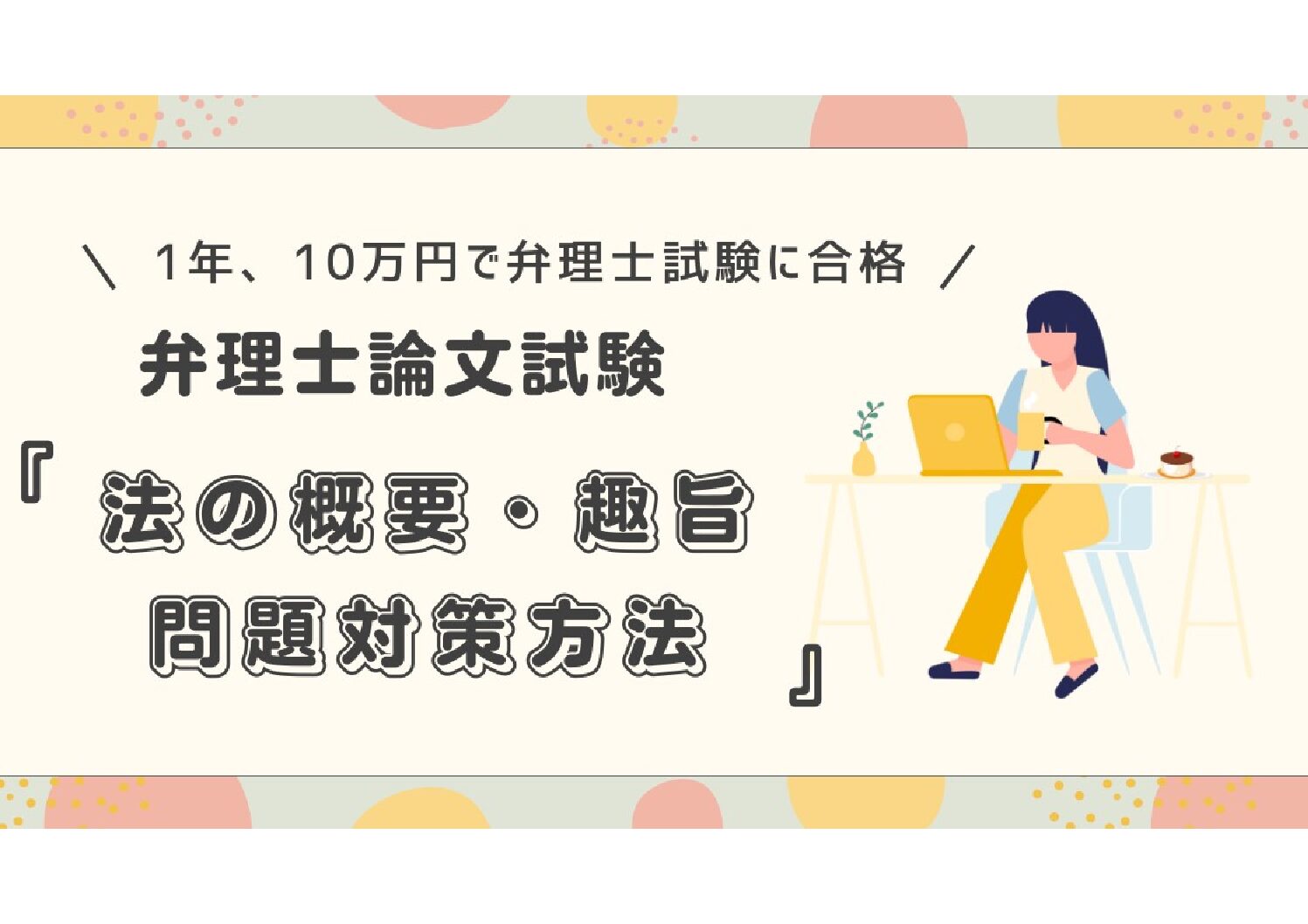




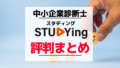

コメント